主婦の逸失利益

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
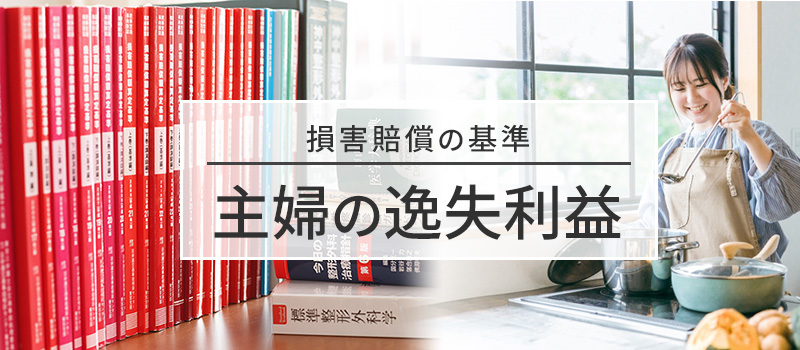
主婦の逸失利益は、女性の平均年収を元に計算することが多いです。
この記事では主婦の交通事故被害者にむけて、主婦の逸失利益の計算方法を交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
なお気になることがある場合、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
―――― 目次 ――――
主婦の逸失利益とは
逸失利益とは事故により発生する将来の収入の減少です。後遺障害が認定されたとき、逸失利益を請求できます。
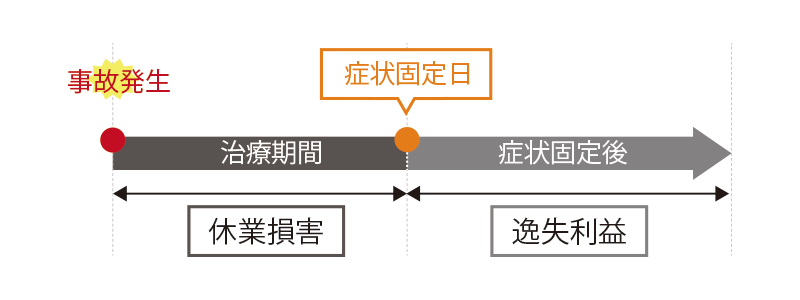
関連情報
逸失利益の計算は次の通りです。
基礎収入は事故時の職業により計算方法が大きく異なります。主婦の基礎収入は女性の平均年収を基準に計算することが多いです。
主婦の逸失利益の基礎収入の基準
では自賠責保険や裁判での主婦の逸失利益の基礎収入の基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。
赤い本の基準
- 賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とする。
- 有職の主婦の場合、実収入が上記平均賃金以上のときは実収入により、平均賃金より下回るときは平均賃金により算定する。家事労働分の加算は認めないのが一般的である。
青い本の基準
- 女性労働者の平均賃金(賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計の全年齢平均賃金又は年齢別平均賃金)を用いる。
- 通常の場合は全年齢平均賃金額を基礎収入額とすることが多い。
- 高齢者の場合は、年齢別平均賃金が採用される傾向にある。相当な高齢者の場合には、身体状況や家族との生活状況を考慮して、賃金センサスの金額の何割かに減額した額を基礎収入額とする例もある。
- 家事に従事しつつ、給与所得者としてあるいは事業により収入を得ているものも多いが、その場合でも、実収入部分を女性平均賃金に加算せず、平均賃金額を基礎収入とする。金銭収入が平均賃金額以上のときは、実収入額によって給与所得者あるいは個人所得者等として損害額を算定する。
基準の解説
専業主婦
専業主婦は女性の平均年収を基準に計算することが多いです。
あわせて読みたい
兼業主婦
兼業主婦は仕事の年収と女性の平均年収を比較します。比較して多い金額を基準に計算することが多いです。
あわせて読みたい
高齢の主婦
高齢の主婦は、女性の平均年収または女性の平均年収をある程度減額した金額を基準に計算することが多いです。
あわせて読みたい
主婦の逸失利益が賠償対象となった事例
では主婦の逸失利益が賠償対象となった事例にはどのようなものがあるでしょうか?
代表的なパターンをご紹介します。
女性の平均年収全額が逸失利益の基礎収入となった事例
次の理由で年収349万9900円を基礎とした逸失利益が賠償対象となりました。
- 主婦の64歳の女性
- 非器質性精神障害(後遺障害12級)、左股関節機能障害(後遺障害10級)、左大腿部知覚鈍麻(後遺障害14級)の後遺障害併合9級
- 女性の主婦平均年収は349万9900円
(東京地方裁判所平成23年10月24日判決)
70歳以上の女性平均年収の90%が逸失利益の基礎収入となった事例
次の理由で年収271万3320円を基礎として逸失利益が賠償対象となりました。
- 専業主婦の81歳の女性
- 右大腿骨転子部骨折後の疼痛(後遺障害14級)
- 家事全部を負担
- 無職の夫と二人暮らし
- 賃金センサス女性学歴計70歳以上平均の90%の年収271万3320円が相当
(東京地方裁判所令和元年7月12日判決)
まとめ:主婦の逸失利益
専業主婦は女性の平均年収を基準にした計算が多いです。兼業主婦は仕事の年収と女性の平均年収を比較して多い金額を基準にした計算が多いです。
ただし、高齢の主婦は女性の平均年収をある程度減額した金額を基準にした計算となることがあります。
(監修者 弁護士 大澤 一郎)
 JR千葉駅徒歩3分 / JR柏駅徒歩3分
JR千葉駅徒歩3分 / JR柏駅徒歩3分


