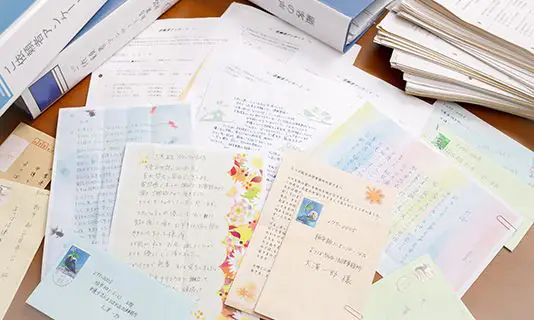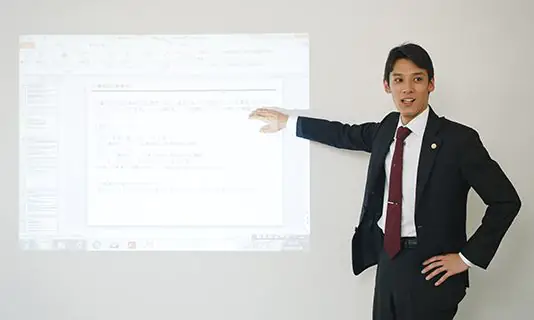弁護士費用
弁護士費用特約の有無によって、かかる費用が異なります。特約がある場合とない場合の費用は次のとおりです。
弁護士費用特約が
ある場合の費用
ほとんどの方が
弁護士費用実質0円です。
- 弁護士費用特約とは、弁護士に相談したり依頼したりする費用を保険会社が補償する特約です。
- すべての保険会社の特約が使えます。
- 弁護士費用の自己負担が発生する可能性があるときは、契約前に弁護士が説明しますのでご安心下さい。
弁護士費用特約が
ない場合の費用
| 初回相談料(60分) | 0円 |
|---|---|
| 着手金 | 0円 |
| 報酬金(後払い) | 22万円+ 獲得金額の11%(税込) |
- 裁判所を利用する場合、27万5000円の追加費用が発生します。
- 交通事故紛争処理センターを利用する場合、22万円の追加費用が発生します。
- 裁判や交通事故紛争処理センターを利用する場合等は、弁護士の日当が発生します。
- 事案によっては着手金無料での対応ができないことがあります。
- その他実費が発生します。
相談料とは
相談料とは、弁護士に相談をする場合にかかる費用です。よつば総合法律事務所では、初回相談料は一切いただいておりません。
着手金とは
着手金とは、弁護士に依頼した場合にかかる費用です。
報酬金とは
報酬金とは、弁護士に依頼した事件が終了した場合に、成功の程度に応じてかかる費用です。
よつば総合法律事務所は、保険会社から受け取った保険金の中から費用をお支払いいただく完全成功報酬制です。費用を気にすることなく安心して弁護士に頼めます。
弁護士費用へのよくある質問
- Q弁護士費用特約とは何ですか?
- 弁護士費用特約とは、弁護士に相談したり依頼したりする費用を保険会社が補償する特約です。
- Q弁護士費用特約があるときの詳しい費用はどのようになりますか?
-
相談料
1時間まで 11,000円(1時間を超える場合15分ごとに2,750円)着手金
請求額が125万円以下 11万円 125万円を超え300万円以下 請求額の8.8% 300万円を超え3000万円以下 請求額の5.5%+9万9000円 3000万円を超え3億円以下 請求額の3.3%+75万9000円 3億円を超える場合 請求額の2.2%+405万9000円 報酬金
請求額が125万円以下 22万円 125万円を超え300万円以下 獲得金額の17.6% 300万円を超え3000万円以下 獲得金額の11%+19万8000円 3000万円を超え3億円以下 獲得金額の6.6%+151万8000円 3億円を超える場合 獲得金額の4.4%+811万8000円 ※その他、よつば総合法律事務所の弁護士費用特約基準によります。
- Q弁護士費用特約があっても自己負担が発生することはありますか?
-
通常はありません。
ただし、重度の後遺障害が残った場合など、請求する金額が高額になるときは自己負担が発生する可能性があります。自己負担が発生する可能性があるときは、契約前に弁護士が説明しますのでご安心下さい。
- Q弁護士費用特約の上限300万円を超えて自己負担が発生することはありますか?
-
通常はありません。
ただし、重度の後遺障害が残った場合など、請求する金額が高額になるときは弁護士費用が300万円を超えて自己負担が発生する可能性があります。自己負担が発生する可能性があるときは、契約前に弁護士が説明しますのでご安心下さい。
- Qすべての保険会社の弁護士費用特約が使えますか?
- すべての保険会社の特約が使えます。
- Q家族の車に付いている弁護士費用特約を使えますか?
-
ご家族の保険でも、特約を使えることが多いです。
夫婦、同居の家族、別居の未婚の子供は特約が使えることがほとんどです。保険会社の担当者に確認してみましょう。
- Q知人の車に同乗中に事故にあいました。乗っていた車に付いている弁護士費用特約を使えますか。
- 乗っていた車に付いている特約を使えることが多いです。保険会社の担当者に確認してみましょう。
- Q歩行中や自転車運転中でも弁護士費用特約を使えますか?
- 歩行中や自転車運転中でも特約を使えることがあります。保険会社の担当者に確認してみましょう。
- Q日当とは何ですか?
- 弁護士が事務所所在地から移動したり裁判等に参加したりすることによって、時間的に拘束される場合にかかる費用です。
- Q実費とは何ですか?
- 交通費、通信費などの実際にかかる費用です。
- Q交通事故紛争処理センターとは何ですか?
- 交通事故被害者の中立・公正かつ迅速な救済を図るため、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっせん及び審査業務を無償で行う公益財団法人です。
- Q裁判とは何ですか?
- 裁判所が法律を用いて、トラブルを最終的に解決する手続きのことです。
- Q弁護士に頼んで費用で損をしてしまうことはありますか?
-
通常はありません。
弁護士に頼んで損をしてしまう可能性がある場合、初回の無料相談の段階で事前にお伝えします。
- 費用はすべて税込表記です。
- 獲得金額とは、弁護士が代理したことを保険会社に通知した後の、自賠責保険や任意保険等からの支払です。
- 委任事務が終了するまでの間、委任契約を解除できます。解任や辞任等により中途で終了したときは、受任事件の進行の程度に応じて清算を行います。
- 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先します。