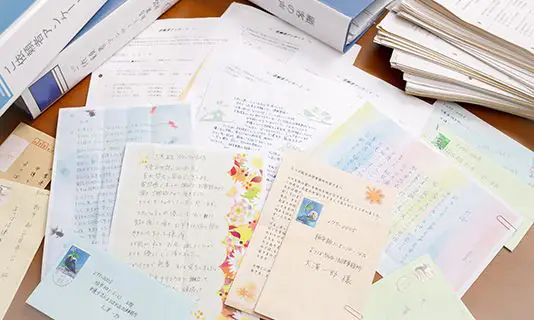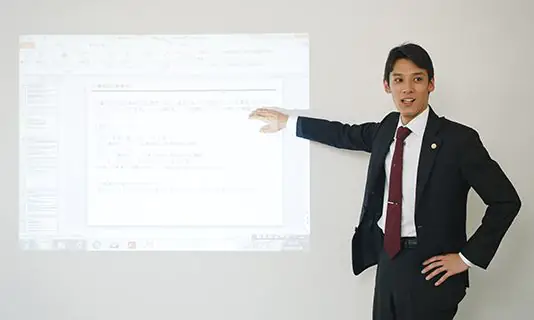自転車の交通事故
最終更新日:2025年01月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 坂口 香澄

自転車事故で適正な補償をもらうためにはルールを正しく理解することが必要です。
この記事では自転車事故の被害者に向けて、自転車事故で残りやすい後遺障害や自転車事故の交渉のポイントなどを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすくお伝えします。
なお、自転車事故は交渉が難しいことがあります。弁護士へのご相談をお勧めします。
1. 自転車事故の特徴
自転車事故には「加害者が自転車」と「被害者が自動車」の2つがあります。
自転車事故は自動車事故とは異なる特徴があります。次の特徴です。
- 重症になりやすい
- 過失割合が決まりにくい
- 加害者に賠償する経済力があるか分からない
- 交渉でもめやすい
2. 自転車事故は重傷になりやすい
被害者は自転車ごと道路に倒れ、体や頭を道路に強打することが多いです。自転車事故は重傷になりやすいです。
頭部を打った場合
くも膜下出血、脳挫傷、高次脳機能障害などの可能性があります。
脳外傷があった場合、症状が後に出てくる場合や、「障害」と認識されにくい症状が残る場合もあります。たとえば「怒りっぽくなる」「注意が散漫になる」「気力がわかない」などの症状は気のせいと見過ごされやすいものの、高次脳機能障害の典型的な症状です。
体を打った場合
圧迫骨折、脊髄損傷などの可能性があります。たとえば、背中の打撲だと思っていたが痛みが強く、MRI検査にて圧迫骨折が見つかる場合もあります。
肩や手首、膝、足首などに強い痛みがある場合
腱板損傷、半月板損傷、手関節、足関節の骨折などの可能性があります。ただの捻挫・打撲だと思っていたら、MRI検査により腱板損傷や骨折が見つかる場合もあります。
特に腱板損傷や関節部位の骨折はレントゲンやCT検査では見過ごされることも多いです。
3. 自転車事故は過失割合が決まりにくい
自転車事故は過去の事例による標準的な過失割合が自動車事故と比べて決まっていません。
そのため個別に過失割合を交渉することが多いです。過失割合が決まりにくいです。
特に、自転車同士や自転車対歩行者の事故は過失割合が決まりにくいです。
話し合いで過失割合が決まらないと、最後は裁判で過失割合を決めます。
このように、自転車事故は過失割合が決まりにくいです。
4. 自転車事故は加害者に賠償する経済力があるか分からない
加害者が車やバイクの場合、自賠責保険の加入が義務となっています。多くの人は任意保険にも入っています。そのため被害者は保険会社から賠償を受けられることが多いです。
一方、加害者が自転車の場合には、加害者が保険に入っているとは限りません。
自転車にぶつけられて怪我した場合、まずは加害者の保険の加入状況を確認しましょう。「自転車保険」という名前ではなくても、本人や家族の自動車保険・火災保険・生命保険に自転車事故でも使える「個人賠償保険特約」があることがあります。
また、自分の保険で使えるものがないか確認しましょう。
たとえば、会社員の仕事中や通勤中の事故であれば労災保険が使えます。
自分や家族が加入している自動車保険で治療費などが補償されることもあります。「人身傷害保険特約」や「無保険車特約」という名前が多いです。
保険も使えず、加害者に賠償する経済力もないと、補償を受けられない場合もあります。
5. 自転車事故は交渉でもめやすい
保険が使えない場合には被害者と加害者が直接交渉します。
保険が使える場合でも、保険会社が交渉は行えず、当事者が直接交渉することもあります。
そのため自転車事故は交渉でもめやすいです。
また、後遺障害が残りそうな場合、後遺障害認定を誰もしてくれないために交渉でもめることもあります。保険に入っている場合は第三者が後遺障害認定をすることもありますが、保険に入っていない場合は裁判で後遺障害を決める確率が高くなります。
このように、自転車事故は交渉でもめやすいです。
6. お読みいただきたいQ&A
- Q自転車と歩行者の事故でも交通事故証明書は発行されますか?
- 発行されます。自動車安全運転センターが発行します。
- Q自転車に自賠責保険はありますか?
- 自転車に自賠責保険はありません。
- Q自転車が加害者になった場合の保険にはどのような保険がありますか?
- いわゆる自転車保険のほか、個人賠償保険が使える場合があります。個人賠償保険は自動車保険、生命保険、火災保険にセットで付いているときもあります。家族の保険が使えるときもあります。
- Q自転車を運転する加害者が保険未加入でした。どうすればよいですか?
-
自分の保険で利用できる保険を探しましょう。次のような保険があります。
- 労災保険 通勤中や仕事中の事故に使える保険です。
- 人身傷害保険特約 自分の自動車保険の特約等で付いていることがある保険です。
- 無保険車特約 自分の自動車保険の特約等で付いていることがある保険です。
- 弁護士費用特約 自分の自動車保険や火災保険の特約等で付いていることがある保険です。
7. まとめ
- 自転車事故には、①重症になりやすい、②過失割合が決まりにくい、③加害者に賠償する経済力があるか分からない、④交渉でもめやすいという特徴があります。
- 自転車にぶつけられて怪我した場合には加害者の保険の加入状況を確認しましょう。また、自分の保険で使えるものがないか確認しましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 坂口 香澄