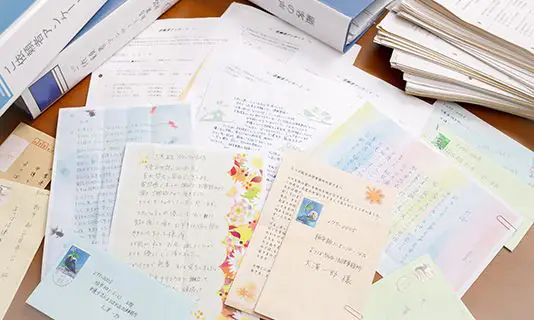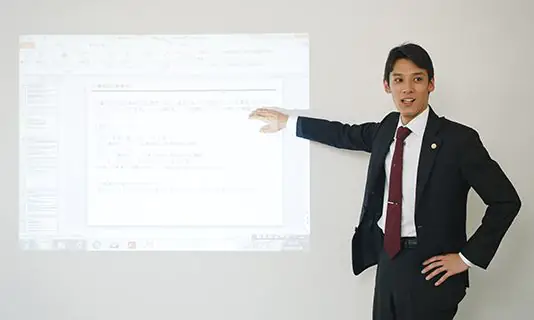バイクの交通事故
最終更新日:2025年01月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 坂口 香澄

バイク事故で適正な補償をもらうためにはルールを正しく理解することが必要です。
この記事ではバイク事故の被害者に向けて、バイク事故で残りやすい後遺障害やバイク事故の交渉方法のポイントなどを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすくお伝えします。
なお、バイク事故は交渉が難しいことがあります。弁護士へのご相談をお勧めします。
1. バイクの交通事故の特徴
①死亡事故や重大な怪我になりやすい、②過失割合で争いになりやすい、という特徴があります。
死亡事故や重大な怪我になりやすい
バイクでの事故の場合、死亡事故や重大事故になりやすいです。たとえば次のような怪我をすることが多いです。
警視庁の二輪車の交通死亡事故統計2023年をみると、交通事故による死者のうち二輪車の死亡事故比率は30.3%(都内)です。
バイクでの事故の場合、死亡事故や重大事故になりやすいです。
過失割合が争いになるケースが多い
交通事故の過失割合は、過失割合を事故態様ごとに類型化した「別冊判例タイムズ38」を基に検討します。別冊判例タイムズ38では「単車と四輪車との事故」として多くの類型がまとまっています。
バイク事故の過失割合は、道路状況、交差点の状況、減速の程度、信号の色など個別具体的な状況により全く異なります。個別具体的な事故ごとの検討が不可欠です。
バイク事故の過失割合は自動車の交通事故と共通しているものも多いです。他方、バイク事故に特徴的な要素もあります。
そのためバイク事故では過失割合が争いになるケースが多いです。
2. バイクの交通事故による怪我
高次脳機能障害
バイク事故では、ヘルメットをかぶっていても頭を道路に強打して重症となることがあります。特に後遺障害が残りやすいのは高次脳機能障害です。
高次脳機能障害では事故直後からの弁護士の関与が望ましいです。後遺障害等級は1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級の段階があります。
認定等級の違いで金額にすると数百万円から数億円の差になります。
検査結果や後遺障害診断書の内容により後遺障害認定等級が変わることがあります。
医師は治療の専門家です。全ての医師が後遺障害認定や後遺障害診断書の作成方法に詳しいわけではありません。
そのため、後遺障害が残ってしまった場合に備えて、バイク事故で頭部を強打したような場合には詳しい弁護士への相談をお勧めします。
骨折に伴う動く範囲の制限(可動域制限)
バイク事故では手足や指の骨折が多いです。
手足や指の骨折では、治療をしても関節が事故前より動きにくくなることがあります。関節が動きにくくなることを「関節の可動域制限」といいます。特に、手首、肩、膝などの関節面での骨折があると可動域制限が残りやすいです。
関節の可動域制限は①傷病名、②画像上の異常所見の有無、③可動域の範囲(角度)等により後遺障害等級が決まります。撮影した画像の内容や、角度5度単位の微妙な判断により数百万円以上保険金に差が出ることもあります。
バイク事故で骨折を伴う場合には詳しい弁護士への相談をお勧めします。
3. バイクが加害者の場合における被害者の注意点
バイク運転者が加害者の場合、加害者が任意保険に加入しているかを確認する必要があります。
バイク運転者が任意保険に加入していない場合は、加害者から十分な補償を受けられない可能性があります。
人身傷害保険、無保険車傷害特約など自分が加入する保険を利用できないか検討しましょう。健康保険や労災保険を利用できないかも検討しましょう。
4. お読みいただきたいQ&A
- Qバイク事故と車の事故で手続の流れに差はありますか。
- 差はありません。壊れたバイクの補償額が低い場合には弁護士と作戦を立てましょう。
- Qバイク事故と車の事故で賠償額に差はありますか。
- 差はありません。ただしバイク事故は重大な怪我になりやすいため、結果的に賠償額が多額となることはあります。
- Qバイク事故と車の事故で過失割合に差はありますか?
- 差はあります。車と比べるとバイクは過失が少なくなることがあります。
- Qバイク運転中の被害事故です。私が所有する車の保険も使えますか?
- 使える場合があります。車の保険の契約内容を確認しましょう。弁護士費用が支払われる弁護士費用特約が使えることもあります。
5. まとめ
- バイク事故は死亡事故や重大怪我になりやすく、過失割合も争いになりやすいです。
- 高次脳機能障害や骨折に伴う動く範囲の制限(可動域制限)が生じそうな場合には早めに詳しい弁護士に相談しましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 坂口 香澄