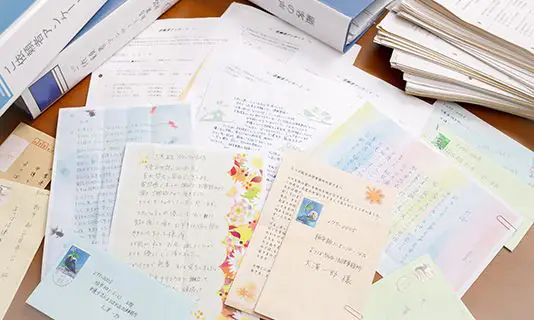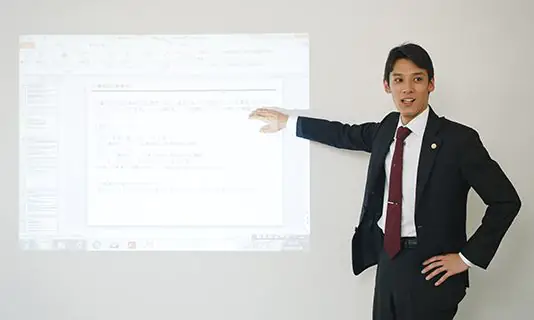慰謝料
最終更新日:2025年02月06日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 佐藤 寿康

適正な慰謝料を獲得するにはルールを正しく理解することが必要です。
この記事では交通事故の被害者に向けて、慰謝料の計算方法や適正な慰謝料をもらうためにしてはいけないことなどを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすくお伝えします。
なお、慰謝料の計算方法は複雑ですので弁護士へのご相談をお勧めします。
1. 交通事故の慰謝料は3種類
交通事故の慰謝料は3種類です。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料です。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我で入通院したことに対する慰謝料です。
傷害慰謝料ともいいます。入通院期間や日数が長くなると金額が増えます。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故の怪我で後遺障害が残った場合に、後遺障害の内容や程度により認められる慰謝料です。
後遺障害は1級から14級までの等級があり、等級が重いほど後遺障害慰謝料が高額になります。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で死亡したことに対する慰謝料です。
死亡した人がどのような人であったかにより金額が変わります。家族構成によっても変わります。
2. 交通事故の慰謝料には3つの基準
交通事故の慰謝料には3つの基準があります。自賠責基準、任意保険基準、裁判基準です。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険で保険金を計算するときの基準です。自賠責基準は3つの基準の中で一番低額となることが多いです。
自賠責保険基準ということもあります。
任意保険基準
任意保険基準とは、加害者の任意保険会社が保険金を計算するときの基準です。
任意保険基準は各保険会社の内部基準であり非公開です。保険会社によっても異なります。ただ、だいたいの相場はあります。
任意保険基準は自賠責基準と裁判基準の中間となることが多いです。
裁判基準
裁判基準とは、裁判所が判決のときに使う基準です。弁護士が示談交渉をするときも裁判基準で請求します。
裁判基準は3つの基準の中で一番高額となることが多いです。
赤本基準、赤い本基準、弁護士基準ということもあります。
3. 入通院慰謝料
では自賠責基準、任意保険基準、裁判基準で入通院慰謝料はどのように計算するのでしょうか?
自賠責基準
自賠責基準で入通院慰謝料を計算する場合、4,300円×日数で計算します。
日数は①入通院期間、②実通院日数×2のうち少ない日数で計算します。
たとえば、むちうちで2ヶ月間(60日)通院を継続し、2ヶ月の中で45日病院に行ったとします。
- 入通院期間は60日、
- 実通院日数(45日)×2は90日
となり60日の方が少ないです。そこで、日数は60日で計算します。
【計算式】 4,300円×60日=172,000円
自賠責基準の慰謝料は172,000円となります。
任意保険基準
任意保険基準の入通院慰謝料の計算方法は非公開です。各保険会社によっても異なります。
一般的には入院期間や通院期間が長いと入通院慰謝料が増えます。
たとえば、ある保険会社の基準だと次の通りです。
- 通院1ヶ月 126,000円
- 通院2カ月 252,000円
- 通院3カ月 378,000円
- 通院6ヶ月 642,000円
入院した場合は慰謝料が増えます。
たとえば、入院1カ月と通院1カ月の合計2カ月だと慰謝料は378,000円です。
自賠責基準と比べると、任意保険基準の入通院慰謝料は高額となることが多いです。
裁判基準
裁判基準で入通院慰謝料を計算する場合、入院期間や通院期間が長いと入通院慰謝料が増えます。
裁判基準の入通院慰謝料には2つの基準があります。
- 骨折など重症の基準
- むちうち、軽い打撲、軽い挫傷などの基準
具体的な慰謝料は次の表の通りです。
(単位:万円)
| 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
| 1ヶ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
| 2ヶ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
| 3ヶ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
| 4ヶ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
| 5ヶ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
| 6ヶ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
| 7ヶ月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 |
| 8ヶ月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
| 9ヶ月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
| 10ヶ月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
(単位:万円)
| 入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
| 1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
| 2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
| 3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
| 4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
| 5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
| 6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
| 7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
| 8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
| 9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
| 10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
たとえば、骨折で2カ月通院した場合の慰謝料は52万円です。むちうちで2カ月間通院した場合の慰謝料は36万円です。
骨折で1カ月入院し5カ月通院した場合の慰謝料は141万円です。
自賠責基準や任意保険基準と比べると、裁判基準は高額となることが多いです。
【動画で見る交通事故】慰謝料は「通院日額4300円」は嘘!?正しい慰謝料の計算方法
4. 後遺障害慰謝料
では、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準で後遺障害慰謝料はどのように計算するのでしょうか?
後遺障害慰謝料は後遺障害等級により決まります。具体的には次の表の通りです。
| 等級 | 自賠責基準※1 | 任意保険基準(推定)※2 | 裁判基準 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 1,150万円 | 1,300万円 | 2,800万円 |
| 2級 | 998万円 | 1,120万円 | 2,370万円 |
| 3級 | 861万円 | 950万円 | 1,990万円 |
| 4級 | 737万円 | 800万円 | 1,670万円 |
| 5級 | 618万円 | 700万円 | 1,400万円 |
| 6級 | 512万円 | 600万円 | 1,180万円 |
| 7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |
| 8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
- ※1 令和2年4月1日以降発生の事故を対象とした基準です。
- ※2 任意保険基準は保険会社によって異なります。
5. 死亡慰謝料
では、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準で死亡慰謝料はどのように計算するのでしょうか?
自賠責基準
自賠責保険の死亡慰謝料は家族の有無や人数で決まります。
| 被害者本人分 | 400万円 |
|---|---|
| 家族分 (家族とは被害者の父母、配偶者、子です。) |
請求者1名の場合 550万円 請求者2名の場合 650万円 請求者3名以上の場合 750万円 ・被害者に被扶養者がいる場合には200万円を加算 |
具体的には次の通りです。
- 家族が全くいない場合 400万円
- 子供が事故で死亡し両親がいる場合 1,050万円 本人分400万と家族の請求者2名分650万の合計です。
- 夫が事故で死亡し妻と子供2人がいる場合 1,350万円 本人分400万、家族の請求者3名分750万、被害者に被扶養者がいる場合の加算200万の合計です。
任意保険基準(推定)
任意保険基準の死亡慰謝料の計算方法は非公開です。各保険会社によっても異なります。
だいたいの基準は次の通りです。
| 被害者の属性 | 任意保険基準(推定) |
|---|---|
| 一家の大黒柱 | 1,500万円~2,000万円程度 |
| 配偶者や母親 | 1,300万円~1,600万円程度 |
| 独身者 | 1,200万円~1,500万円程度 |
| 高齢者 | 1,100万円~1,400万円程度 |
| 子ども | 1,200万円~1,500万円程度 |
自賠責基準と比べると、任意保険基準の死亡慰謝料は高額です。
裁判基準
裁判基準の死亡慰謝料は次の通りです。
| 被害者の属性 | 裁判基準 |
|---|---|
| 一家の大黒柱 | 2,800万円 |
| 母親、配偶者 | 2,500万円 |
| 独身の男女、子供、幼児等 | 2,000万円~2,500万円 |
自賠責基準、任意保険基準と比べると、裁判基準の死亡慰謝料は高額です。
6. 慰謝料が増額される場合
被害者や加害者の個別事情により、慰謝料が増額されることがあります。
たとえば、次のような場合です。
加害者の事情
- 無免許運転
- ひき逃げ
- 酒酔い運転
- 著しいスピード違反
- ことさらに信号無視
- 薬物の影響により正常な運転ができない状態での運転
- 証拠隠滅
- 被害者に対する不当な責任転嫁
被害者の事情
- 流産した
- 離婚した
- 学校に入学できなくなった
- 留学できなくなった
- 留年してしまった
- 昇進が遅れた
- 退職になった
- 自営業を廃業した
7. 慰謝料が振り込まれる時期
慰謝料が振り込まれる時期はいつでしょうか?
誰が支払をするかにより支払時期が異なります。
自賠責保険の場合
自賠責保険への請求から1カ月~3カ月で支払されることが多いです。
加害者の任意保険の場合
合意後1週間~1カ月で支払されることが多いです。ただし、裁判の判決だと裁判の確定後1カ月程度支払まで時間がかかることがあります。
加害者本人の場合
約束をした支払日までに支払されることが多いです。ただし、約束通り支払されないこともあります。
8. 慰謝料の時効
時効とは、一定期間が経過すると請求ができなくなってしまう制度です。交通事故の慰謝料の時効は原則として5年間です。
| 事故の種類 | 時効の起算点 | 時効期間 |
|---|---|---|
| 物損事故 | 事故の翌日 | 3年 |
| 人身事故 (傷害のみ) |
事故の翌日 | 5年 |
| 人身事故 (後遺障害有) |
症状固定日の 翌日 |
5年 |
| 死亡事故 | 死亡日の翌日 | 5年 |
| 加害者が判明 しない事故 |
事故の翌日 | 20年 |
| 後日加害者が 判明した場合 ※いずれか早い方 |
加害者を知った 日の翌日 |
5年 |
| 事故の翌日 | 20年 |
- 注 上記の期間は加害者に請求する場合です。自賠責保険等に請求する場合には期間が異なることがあります。
9. 慰謝料増額のポイント
慰謝料を増額させるため次の点を検討しましょう。
- 適切な期間の通院を行いましょう。
- 適切な計算方法(裁判基準)で慰謝料を計算しましょう。
- 後遺障害認定の可能性がある場合には後遺障害申請を行いましょう。
- 弁護士へ相談・依頼しましょう。
10. 適正な慰謝料をもらうため「してはいけないこと」
適正な慰謝料をもらうため、次のようなことはやめておきましょう。
- 症状があり治療継続を医師に指示されたにもかかわらず通院治療をやめてしまう。
- 弁護士に相談せずに保険会社の提示額で合意してしまう。
- 後遺障害が認定されそうなのに後遺障害申請をしない。
- 長期間交渉を放置して時効にしてしまう。
11. よつば総合法律事務所の慰謝料増額事例
当事務所の解決事例のうち慰謝料などが増額となった事例をご紹介します。
-
【死亡事故】死亡慰謝料の増額無職の被害者の死亡事故について6,900万円の賠償金を獲得した事例
- 【遷延性意識障害・後遺障害等級1級】親族固有の慰謝料歩行中の被害者が遷延性意識障害により1級1号の認定を受け1億1,000万円を獲得した事例
- 【後遺障害10級】慰謝料について裁判基準100%の事案女子高校生が、左上腕骨頚部骨折に伴う左肩関節の機能の症状について後遺障害10級10号の認定を受け、1,900万円(既払い金を含めると2,150万円)の損害賠償を受領した事例
- 【慢性硬膜下血腫・後遺障害12級】2種類の慰謝料についていずれも裁判所基準で示談成立弁護士依頼により休業損害が17倍以上に増額するなど総額で220万円増加した事例
- 【頸椎捻挫・後遺障害14級】2種類の慰謝料について…示談交渉開始当初裁判所基準の8割→裁判所基準での示談解決保険会社からの提案を弁護士に見せて相談。依頼の結果2倍以上に増額した事例
12. まとめ:慰謝料
- 交通事故の慰謝料は入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類です。
- 交通事故の慰謝料には3つの基準があります。自賠責基準、任意保険基準、裁判基準です。
- 自賠責基準が一番低く裁判基準が一番高いことが多いです。
- 適切な期間の通院を行い、裁判基準など適切な計算方法で慰謝料を請求しましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 佐藤 寿康