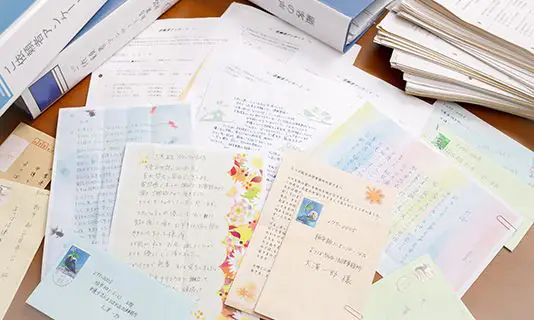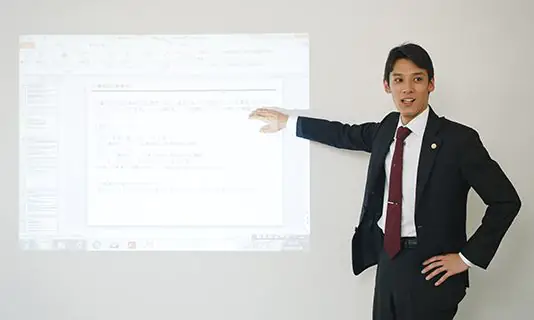労災保険
最終更新日:2025年01月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 加藤 貴紀
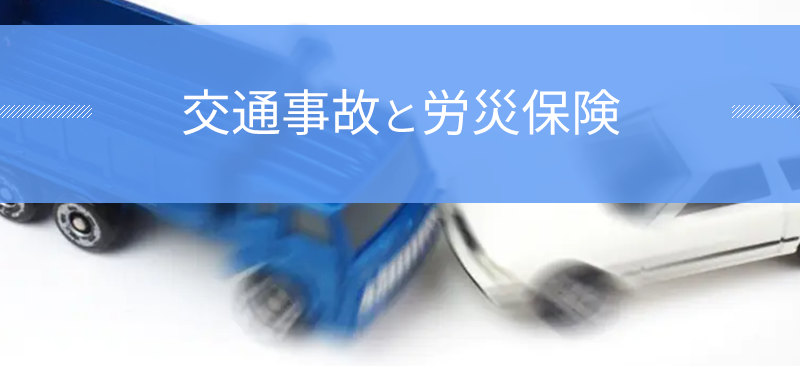
交通事故でも労災保険を使えます。労災保険を使わないと大幅に損をする事案もあります。
この記事では交通事故の被害者にむけて、労災保険の補償内容、労災保険のメリットやデメリットを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
なお、交通事故と労災保険の問題は複雑です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
1. 労災保険とは
労災保険とは、業務や通勤による労働者の負傷や障害、死亡に対して必要な保険給付を行う制度です。
労災保険には業務災害と通勤災害があります。業務災害は労働者が業務中に負傷等する場合です。通勤災害は労働者が通勤中に負傷等する場合です。
交通事故でも労災保険は利用できます。
2. 労災保険の補償内容
労災保険の主な補償内容は、次の通りです。- 療養給付
- 休業給付
- 障害給付
- 遺族給付
- 葬祭料・葬祭給付
- 傷病給付
- 介護給付
①療養給付
病院での治療費などに対する補償です。実費相当額が補償対象です。
②休業給付
休業に伴う給料減に対する補償です。休業4日目以降、休業1日につき約60%に相当する金額が補償対象です。
③障害給付
後遺障害に対する補償です。事故前の収入や後遺障害等級に基づき、一定の金額が補償対象です。
④遺族給付
死亡に対する補償です。死亡前の収入や遺族の数に基づき、一定の金額が補償対象です。
⑤葬祭料・葬祭給付
葬儀費に対する補償です。死亡前の収入に基づき、一定の金額が補償対象です。
⑥傷病年金
1年6カ月を経過しても治癒していない重度障害への補償です。事故前の収入や後遺障害等級に基づき、一定の金額が補償対象です。
⑦介護給付
介護に対する補償です。介護内容や後遺障害等級に基づき、一定の金額が補償対象です。
3. 労災を使うメリット
では、交通事故で労災保険を使うメリットは何でしょうか?
交通事故で労災を利用すると、次のようなメリットがあります。- 治療費が打ち切られにくい
- 休業損害が打ち切られにくい
- 後遺障害認定がされやすい
- 特別支給金を受領できる
- 被害者の過失が考慮されない
- 加害者に関係なく補償がある
①治療費が打ち切られにくい
労災保険と加害者任意保険を比較すると、労災保険は治療費が打ち切られにくいです。労災保険は国が行う保険であり、任意保険は民間企業が行う保険であることが理由です。
②休業損害が打ち切られにくい
労災保険と加害者任意保険を比較すると、労災保険は休業損害が打ち切られにくいです。
ただし、労災保険の休業給付は約60%分の補償です。残りの約40%は加害者の任意保険会社に休業損害の請求をする必要があります。
③後遺障害認定がされやすい
治療しても症状が残り症状固定 となった場合、後遺障害の申請を行うことが多いです。
経験上、労災保険と自賠責保険を比較すると、労災保険は後遺障害が認定されやすいです。労災保険は認定される後遺障害等級も高くなる傾向です。
ただし、労災保険と自賠責保険は後遺障害が認定されたときの支払額が異なります。また、自賠責保険で後遺障害が認定されると、加害者の任意保険会社に後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。
そのため、労災保険に後遺障害申請をしたとしても、別途自賠責保険にも後遺障害申請をすることが多いです。④特別支給金を受領できる
労災保険は、休業給付や障害給付などの特別支給金という制度があります。
たとえば、休業損害は、20%分の特別支給金を労災保険から受領できます。うまく手続きが進めば、合計120%分の休業損害が受領できます。
- 労災保険からの休業補償給付 60%
- 労災保険からの特別支給金 20%
- 加害者任意保険会社からの休業損害 40%
- 合計 120%
⑤被害者の過失が考慮されない
労災保険は被害者の過失が考慮されません。自賠責保険や任意保険では被害者の過失が考慮されます。
労災保険を利用しない場合、利用した場合を比較してみましょう。
たとえば、治療費100万円、慰謝料100万円、総損害額200万円、過失割合8対2とします。被害者にも20%の落ち度がある事案です。
- 治療費 100万円
- 慰謝料 100万円
- 損害総額 200万円
- 過失割合 8対2
労災保険を利用しない場合
損害総額200万円で過失割合が80%ですので受領額は160万円です。
【計算式】損害総額200万円×80%=受領額160万円
労災保険を利用する場合
労災保険が支払った治療費は過失相殺の対象となりません。他方、慰謝料は過失相殺の対象となります。そのため、受領額は180万円です。
【計算式】治療費100万円+慰謝料100万円×80%=受領額180万円
労災保険を使うと、最終的な手取額が20万円増えます。
労災保険は被害者の過失が考慮されません。自賠責保険や任意保険では被害者の過失が考慮されます。被害者に過失があるときは、労災保険を使うと手取額が増えることが多いです。
⑥加害者に関係なく補償がある
労災保険は加害者に関係なく補償があります。
たとえば、次のような事故でも労災保険は補償対象です。- 加害者がいない事故
- 加害者不明の事故
- 加害者が無保険の事故
- 加害者が保険利用を拒否している事故
4. 交通事故で労災を使うデメリット
では、労災保険を使うデメリットは何でしょうか?
交通事故で労災を使うと手続きが若干複雑です。会社が手続きへの協力を拒否したときなど、手続きが面倒になることがあります。
5. 労災保険を利用するかどうか悩んだとき
では、労災保険を利用するかどうか悩んだときはどうすればよいでしょうか?
労災保険を利用して損をすることは経験上少ないです。そのため、労災保険を利用するか悩んだときは、労災保険の利用が望ましいことが多いです。
交通事故で労災保険を利用するかは専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
6. まとめ:交通事故と労災保険
労災保険とは、業務や通勤による労働者の負傷や障害、死亡に対して必要な保険給付を行う制度です。業務災害と通勤災害があります。交通事故でも労災保険は利用できます。
労災保険の給付には、①療養給付②休業給付③障害給付④遺族給付⑤葬祭料・葬祭給付⑥傷病給付⑦介護給付などがあります。
労災保険を使う主なメリットは次の通りです。- 治療費が打ち切られにくい
- 休業損害が打ち切られにくい
- 後遺障害認定がされやすい
- 特別支給金を受領できる
- 被害者の過失が考慮されない
- 加害者に関係なく補償がある
労災保険を使うデメリットは手続きが面倒という程度です。そのため、労災保険の利用を悩んだら労災保険の利用が望ましいことが多いです。
交通事故で労災保険を利用するかは専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 加藤 貴紀