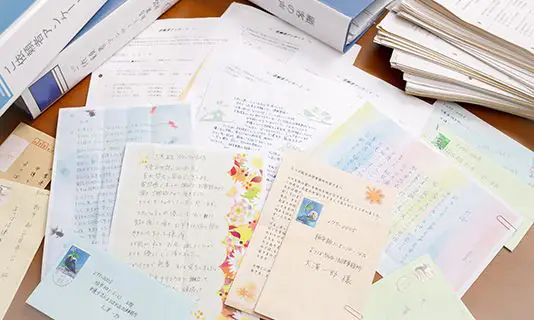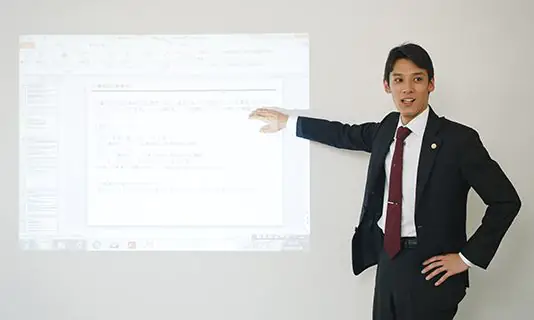6. ご相談をお悩みの方へのメッセージ
早期相談のススメ(弁護士 村岡 つばさ)
はじめに
「弁護士に相談したいけど、どのタイミングで相談したら良いの?」‐こんなお悩みを抱えていませんか?このお悩みへの回答としては、「早ければ早いほど良い」というのが適切な回答だと思います。
交通事故に遭われてしまった場合には、事故直後に弁護士に相談することを強くお勧めします。

事故直後にしかできないアドバイスがあります!
⑴ 治療期間・賠償について
例えば、むち打ちの場合、おおよそ3か月~半年間が相当な治療期間と言われています(勿論、治療状況や症状により相当な治療期間は異なります。2週間程度で治る方もいれば、1年以上かかる方もいます。)。 しかし、「むち打ちは一般的に3か月で治るから、それ以降の治療は一切認めません。」といった説明をする保険会社も中にはあります。当事務所に相談に来る方の中にも、「3か月で治療終了と保険会社に言われたから、痛みはあるけど、治療を諦めた。」というお話をされる方も多くおられます。
保険会社は、いわば交通事故対応のプロであるのに対し、多くの被害者様は、交通事故の十分な知識を有しておりません(当然です)。そうすると、保険会社の説明がすべて真実のように思えてしまい、保険会社に言われるがまま、治療・補償が進んでいってしまい、適切な治療・補償を受けられないといった事態が出てきます。
事故直後に、交通事故に詳しい弁護士に相談し、交通事故治療・賠償の相場観や一連の流れを知ることができれば、適切な治療・補償を受けられる可能性が高まります。
⑵ 後遺障害について
不幸にも症状が完治せず、症状が残ってしまった場合には、適切な後遺障害の認定を受け、適切な補償を受けることが、非常に大事です。 後遺障害の認定に当たっては、事故態様、MRI・レントゲン等の検査結果、治療状況(頻度・内容等)、症状の一貫性等、様々な事情が考慮されます。
MRI・レントゲン等の検査については、事故からそれほど日が経っていない段階で検査を受けることが重要となってきます(早ければ早いほど良いです)。事故からかなり時間が経った段階で検査を受け、異常が見つかったとしても、「事故後に別の原因で異常が生じた可能性がある(=因果関係がない)」などと保険会社から争われる可能性があるからです。
また、仕事の都合等であまり通院できず、通院頻度が非常に低い場合には、症状もそれほど重くないものと考えられてしまうことがあり、この場合にも後遺障害が認定されない可能性が高くなってしまいます。お身体を治すという観点だけでなく、後遺障害認定の観点からも、痛みがある場合には、無理のない範囲で通院をすることが大事です。
さらに、自覚症状として様々な痛みを抱えていても、それが主治医の先生に伝わっていない場合には、症状の一貫性がないとされることがあります。現在ある自覚症状は、全て主治医の先生に伝えたうえで、診断書等に記載してもらい、しっかりと証拠を残すことが重要となってきます。
おわりに
私が事故直後の時点での相談を強く薦めるのは、上記のような「適正な補償を受ける」という観点だけではありません。予期せぬ事故に遭われ、お身体の痛みも抱える中で、「いつまで治療を続けられるのか?」「補償はどうなるのか?」といった不安でいっぱいの方も、多くおられると思います。私は、このような被害者様の不安を少しでも解消したいという想いから、この「想いとこだわり」を書かせていただきました。
事故に遭われてしまった際は、ぜひ一度、早い段階で弁護士にご相談ください。
(文責:弁護士 村岡 つばさ)
弁護士に気軽に聞いてみる(弁護士 根來 真一郎)
保険会社担当者の説明が正しいとは限らない
交通事故の被害者の方は、保険会社担当者から様々なことを言われます。保険会社担当者から明らかな虚偽の説明を受け、担当者に無理やり説得されてしまう被害者の方も多くいらっしゃいます。
「そんなことを言うのはあなたくらいだ。そんな請求認められるわけがないでしょう。」と被害者の方が保険会社担当者から言われていた内容について、依頼をいただき弁護士が請求をしたところ、保険会社担当者は悪びれることなく認めることもよくある話です。
また、交通事故の被害者の方と保険会社担当者の間で、過失割合が問題になっていることも多いかと思います。「このような事故態様の場合、この過失割合で決まっています。」と被害者の方が保険会社担当者から言われていた内容について、被害者の方に有利な内容が隠されているなんてことは、もはや日常茶飯事です。依頼をいただき弁護士が請求をしたところ、保険会社担当者が渋々認めることもよくある話です。
弁護士であれば、保険会社担当者の説明が正しいのか虚偽であるのか判断することができます。なので、保険会社担当者の説明に納得ができなければ、気軽に弁護士に聞いてみようと思っていただければと思います。
巷に溢れる情報が正しいとは限らない
インターネットには、交通事故の情報が溢れています。パソコンだけでなく、スマホがあれば本当に簡単に調べることができるようになりました。しかし情報が余りにも多く、突然の被害に遭った方にとってどれが適切な情報なのか分からないのではないかとも思います。
また、インターネットで確認することができる情報の質は様々です。例えば、弁護士が名前を記して作成している原稿もあれば、誰が作成したのか全く分からない原稿もあります。中には、明らかに間違っている情報を載せてしまっているサイトもあります。
被害者の方は、インターネットで調べてみることも多いと思います。しかし、インターネットで請求できないと書かれていても、それが本当に今回の被害においても請求できないのかは分かりません。当然のことながら、事案は1つ1つ異なるからです。
弁護士であれば、インターネットの情報が正しいか、今回の被害において請求ができるのか判断することができます。インターネットで調べてみて疑問があれば、気軽に弁護士に聞いてみようと思っていただければと思います。
弁護士に気軽に聞いてみる

とにもかくにも、突然事故に遭われた被害者の方にとって、分からないことが多いのは当然です。
弁護士であれば、保険会社担当者の説明が正しいのか、インターネットの情報が正しいのか判断することができます。
ぜひ、弁護士に気軽に相談をしていただければと思います。
(文責:弁護士 根來 真一郎)
保険会社担当者には裏がある(弁護士 根來 真一郎)
保険会社担当者の対応には満足していたが・・・
「賠償金の額が低過ぎるのではないか」と相談にいらっしゃった被害者の方から、交渉の依頼をいただきました。
とても穏やかな依頼者の方で、交通事故の被害者であるにもかかわらず、相手方保険会社担当者には充分な対応をしてもらっており、特に不満はないとおっしゃっておられました。

しかし実際は・・・
しかし、依頼者の方が相手方保険会社より提示された和解の内容は、驚く程に低額の内容でした。約300万円の提示がされていてもおかしくない事案にもかかわらず、約150万円の提示がされていたのです。私は、提示された内容が低額であることを説明し、交渉の依頼をいただきました。
保険会社担当者のあからさまな対応
その日の夜、たまたま保険会社担当者が、依頼者の方に電話を掛けたとのことです。依頼者の方が「弁護士に依頼するつもりである」旨を伝えたところ、保険会社担当者は「弁護士に依頼しないのであれば、さらに70万円増額します」と依頼者に告げたとのことでした。 依頼者の方からその報告をいただいた際には、私は保険会社担当者の余りにあからさまな対応に唖然としながら、それでもなお低額なので、交渉を続けることとしました。
保険会社担当者が隠していた特約の存在
その後交渉を続け、相手方保険会社より、約290万円位であれば支払うとの回答を引き出しました。私は依頼者の方と相談し、粘り強く交渉を続けることにしました。しかし保険会社担当者は、「これ以上は絶対に無理である」と要求を拒絶し続けました。それでもこちらが要求を続けたところ、保険会社担当者は、「実は、特約がありまして・・・」と賠償が増額される特約の存在を明かしました。私は、特約の存在をこの段階まで隠し続けた保険会社担当者に呆れつつ、最終的に約350万円で和解することとなりました。
保険会社担当者には裏がある
保険会社は営利企業であり、保険会社担当者は保険金支払額が少ない程社内で評価されます。そう考えると、被害者の方がどんなにいい保険会社担当者と思っていても、裏では保険会社担当者は保険金支払額を少なくするため、あらゆる手を尽くしていることが想像できると思います。交通事故被害者の方には、保険会社担当者には裏があるということだけは、頭の隅に置いておいていただければと思います。
(文責:弁護士 根來 真一郎)
誰だって初めての交通事故(弁護士 前原 彩)
「一生のうち、交通事故に遭う確率と宝くじに当たる確率を比べると、宝くじに当たる確率の方が高い」
こんなウワサ聞いたことありませんか?
私は高校生くらいの時に初めてこのウワサを聞きました。
昔から巷でまことしやかに流されているウワサだと思います。
では、本当のところはどうなのでしょうか。

だいぶ古いデータですが、国土交通省が2002年に示した資料によると、一生のうち交通事故に遭う人は2人に1人とのことです。 意外や意外、予想より多くの人が事故に遭うとの数字ですね。
しかし、裏を返してみれば「2人に1人の人は一生事故に遭うことはない」という数字ですし、上記の統計が交通事故の加害者になるパターンも含めた数字ですので、交通事故の被害者になる場合だとその確率はもっと下がります。
私たちが普段、交通事故のご相談をお受けしていても、ほとんどの人が初めての経験で、2回も3回も事故に遭う人はそうそういません。
そうすると、いざ交通事故に遭った場合、「自分がどうすればいいのか良くわからない!」という事態になりかねません。
誰だって初めての交通事故なのですから、事故に遭ったその後どうすればいいのかわからなくて当然です。
ところが、被害者になった方が事故のことについて話す相手はほとんど加害者の入っている保険会社の担当者です。
保険会社は交通事故の事故処理が日常業務であるゆえ、交通事故のことは熟知しています。
被害者は交通事故に遭うのが初めてで、他方、加害者(保険会社)は交通事故の処理は日常茶飯事。
これってすごく不公平だと思いませんか? また、交通事故と言っても、保険の種類や損害賠償金の基準など、実に様々な仕組みがあり、これが事故に初めて遭う被害者の方と、事故の処理は日常茶飯事の保険会社との情報格差をより一段と大きくしています。
そこで、被害者の方も、弁護士に相談するなどして、きちんと情報格差を埋める必要があります。
私たちはそのような被害者の方が「交通事故について知らなかった」がために損をする、ということが決してないよう、被害者の方に寄り添い、分かり易い説明を心がけて日々、交通事故の業務にあたっています。
今はネットに情報が溢れる時代になりましたが、交通事故の等級や賠償について説明しているサイトを見ると、私たち弁護士から見ると明らかに説明が間違っているサイトも良く目にします。
そういった誤った情報に基づく行動をしないためにも、事故にあったらまず弁護士に相談して、病院への通院の仕方や等級、賠償までの流れについて一度正確な情報を把握することをおすすめします。
(文責:弁護士 前原 彩)
オーダーメイドの解決(弁護士 今村 公治)
オーダーメイドの解決方法をとること
交通事故で初めてご相談いただいた方とお話ししていると、弁護士に頼むと裁判をすることになるとお考えの方が一定数います。
ドラマなどのイメージから、“弁護士は裁判をするのが仕事だ”と思われがちですが、一般的に、実は裁判を起こさずに解決する事件のほうがどちらかというと多いです。
事件の内容によっては、解決手段によって受領できる賠償金額が大きく変わることがあります。裁判をすることによって賠償金額が下がってしまう事案もあります。

そのため、交通事故の事件を解決するにあたっては、診断書やMRI画像等の資料を精査することはもちろん、事案によっては事務所の協力医である整形外科医の先生に意見を聞いたり、リサーチ会社に調査を依頼したりしながら、どの解決手段をとるのがよいのかを時間をかけて検討します。
もちろん、解決手段を選択するにあたっては、依頼者の方の意向が一番大事になります。そこで、それぞれの解決手段のメリット、デメリットをお伝えして、依頼者ひとりひとりに応じて、事件ひとつひとつに応じて、適切な解決手段がなにかを依頼者の方と一緒に考えるようにしています。
裁判での解決をとること
事件の内容次第ですが、多くの場合で、裁判をすると賠償金額が一番大きくなります。依頼者の意向を聞いたうえで、裁判を選択する場合には、こちらの利益が最大限補償されるように徹底的に訴訟活動をするようにしています。
さまざまな解決手段をとること
紛争の解決方法として、大きく分けると、裁判での解決か、裁判以外での解決(訴外での解決といったりします。)かに分けられると思います。
意外かもしれませんが、件数としては、訴外での解決のほうが多いと思います。
訴外での解決には、交渉での解決や、ADRという裁判外の紛争解決機関を利用することがあります。
たとえば、交通事故の分野でいうと、交通事故紛争処理センター(紛センといったりします。)という、自動車事故をめぐる損害賠償の和解をあっせんしてくれる機関があります。交通事故紛争処理センターを利用すると、事案によっては、交渉時よりも賠償金額が上がることが多く、裁判よりは短い期間で解決できるため、よく利用される解決手段です。
また、弁護士が介入して、交渉によって事件解決する事案もたくさんあります。(一般的に、事故態様などの事実関係に争いが少ない場合には、交渉による解決が件数としては一番多いと思います。)裁判と比較して、交渉で解決する場合には、依頼者の方の精神的負担が少ない、解決までの時間が早いというメリットがあります。
相手方保険会社は、弁護士が介入しない限りは賠償金の交渉にほとんど応じないということもあります。弁護士が介入すると、交渉で賠償金が増額することがほとんどです。
(文責:弁護士 今村 公治)
裁判における尋問(弁護士 川﨑 翔)
裁判において、争点になりやすいのは「事故態様」や「後遺症による影響の程度」です。
書証で争点に関する決着がつけばよいのですが、いつもそうとは限りません。書証が十分でない場合、最終的には尋問を行うことになります。
尋問を行うためには、依頼者から争点について詳しく事情を聴きとることが必須です。
それだけではなく、必要に応じて尋問の予行練習をする必要もあります。

尋問は、証人席で原告代理人、被告代理人及び裁判官の質問に答えるという形式で進みます。当然、尋問を受ける方は緊張すると思います。
(私も新人弁護士の時はとても緊張したものです。今でも弁護士活動の中で最も緊張する場面のひとつと言えます。)
そのため、入念な準備が必要になるのです。
このように、尋問には手間がかかるため、裁判所も弁護士も尋問をすることに消極的になりがちです。
(特に裁判所は時間の確保や録音反訳の手間があり、尋問に消極的です。)
しかし、被害者側代理人としては、書証のみで十分に事故態様や損害が立証できない場合、尋問を躊躇すべきではないと思います。
特に事故態様の立証については、被害者側が不利な状況におかれることはめずらしくありません。
というのも、事故態様を立証する書証として実況見分調書が用いられることが一般的ですが、加害者の言い分によって作成されているものがほとんどで、被害者の言い分をもとにした実況見分調書が作成されていない場合もあるためです。
そのような場合、尋問できちんと事故態様を証明していく必要があります。
もちろん、事故から長期間が経過しており、記憶のみで証言をしていくことには困難が伴いますが、ひとつひとつ証言をつなぎ合わせ、加害者側の証言の矛盾や不自然な点を指摘していくことで困難な状況を打開できることもあります。
「尋問は万能でない」ということに注意を払う必要はありますが、被害者側弁護士として真実を明らかにするためには、積極的に尋問を行うことが重要だと思っています。
(文責:弁護士 川﨑 翔)
あきらめないって大事(弁護士 前原 彩)
交通事故は「あきらめがち」
私たちが交通事故の被害に遭われた方からの相談を受けている中で、思うことは、交通事故はあきらめがちになっている方が多いということです。
- 保険会社から支払えないと言われた
- 保険会社から自分の事故の場合は請求できないと言われた
- 医者が書類を書いてくれなかったからそのままにしてしまっている
- 保険会社から一方的に打ち切りを受けてもうダメなのかと思った
- 保険会社から何も説明がなかったので自分の場合は何もできないと思った
等々の理由により、治療、損害賠償、手続のあらゆる面で仕方ないとあきらめてしまい、そこで何もせずに終了してしまっている方を多く見かけます。
その説明は正しいのか
しかし、本当にそれでいいのでしょうか。保険会社や医者から受けたその説明は、本当に正しいのでしょうか。
保険会社は「賠償金を支払わなければいけない側」です。支払う額は少なければ少ないほどいいはずです。そのような立場の人の説明を鵜呑みにしてしまっていいのでしょうか。
お医者さんは怪我や病気を治すプロですが、交通事故のプロではありません。交通事故のプロではないお医者さんが交通事故の手続に必要な書類をかかないと言っていることに従ったままでいいのでしょうか。
あきらめるのはまだ早い
保険会社やお医者さんから言われたことをそのまま鵜呑みにするのではなく、言っていることが正しいのかそうでないのか、まずその確認から始めてみませんか。
そういった問題にぶつかった時に、正しいかそうでないのかがわかるだけでも、その後の解決の方向性が大きく変わります。
その点弁護士は交通事故のプロであり、正しいかそうでないのかの判断をすることができるので、まず、弁護士に相談しましょう。
そして、私たちはすぐにあきらめません!私たちと一緒に粘り強くどのような方法が良いのかを一緒に探しましょう。
(文責:弁護士 前原 彩)
ひとりひとりに合った適切な解決方法をご提案(弁護士 前原 彩)
実は弁護士に依頼すべき事例と依頼すべきでない事例がある
ご相談者にやみくもに弁護士を使うことはおすすめしません。弁護士に依頼すべきでない事例もあるからです。
例えば、既に相談に来た方に有利な内容で話合いが進んでいる場合です。そういった場合に弁護士を使うと保険会社も弁護士を入れてきたりして、今までの話合いの内容が白紙撤回される場合も間々あります。
そのため、お話しを聞いた上で、どうすべき事案なのかを一緒にじっくりと検討させていただきます。

弁護士を使わない方がいい事例でも解決までの道筋をきちんと示す
また、弁護士に依頼すべきでないパターンであったとしても、その後ご相談者がどうすればいいのかをきちんと示します。
「弁護士を使わない方がいいですね」とだけアドバイスされても、何の解決にもならないからです。
そのまま保険会社と交渉を続けた方がいいのか、続けるとしてどの点に着目してどういう理由づけで交渉した方がいいのか、交渉は打ち切りにして紛争処理センターへの申立てをした方がいいのか、など細かくアドバイスするようにしています。
弁護士を使った方がいい事例でも、複数の解決方法をご提案
弁護士を使った方がいい事例と判断した場合には、弁護士を使ったとしてその後どうなるのか、解決までにどういう選択肢があってどれを選んだ方がいいのかについてまで、きちんと説明します。
交通事故の場合、
- 保険会社との交渉
- 紛争処理センターへの申立て
- 日弁連交通事故相談センターへのあっ旋申込み
- 調停申立て
- 訴訟提起などなど
たくさんの解決方法があります。
事故の態様や被害の内容は千差万別。ただ単に「交渉が決裂したら裁判」というものではありません。
ご相談者の方の事故の内容や経過等をしっかりと踏まえ、また各手続のメリットデメリットをしっかりと説明した上で、ひとりひとりに合った最適な解決方法を提案します。
(文責:弁護士 前原 彩)
保険を駆使して受けた被害をすぐに回復!(弁護士 前原 彩)
交通事故に遭って困った!
交通事故の遭ってしまった被害者が困ることは何だと思いますか。
内閣府が出している統計を見てみると、交通事故に遭って困ったこととして

- 1位:精神的なショックや苦痛
- 2位:身体的な苦痛や障害
- 3位:家事育児の負担
- 4位:示談交渉や民事訴訟などの負担
- 5位:医療費や失職などの経済的負担
が挙げられています。
「困った!」をどう解決するか
今回は、上記の「困った」の中で、経済的負担についての「困った」について述べたいと思います。
(4位の「困った」については「保険会社の思うツボにはならない」の記事をご覧ください。)
交通事故の被害に遭った場合には、通常、加害者が入っている任意保険会社の担当者が出てきて、治療費や仕事ができない間の損害(休業損害)の支払いの手続などを行います。
しかし、中には加害者が自賠責保険や任意保険に加入していなかったり、加入していたとしても保険会社が一方的に治療費等の支払いを拒否してくることもあります。(これは結構よくあります。)
そのような時に、「そういうものか」と思ってあきらめるのはまだ早いです。どうにかしてどこからか支払いを受けられないか探しましょう。
保険を良く知ろう!
保険って複雑なので(請求されないためにあえて複雑にしているのかと勘繰りたくなります…)、どういったときにどういう費用を請求できるのかパッと見よくわかりません。
しかし「わからないから/面倒くさいからいいや」ではなく、今一度、自賠責や加害者の任意保険会社、はたまたご自身が加入されている任意保険や個人賠償責任保険や共済等々から何らかの支払いを受けられないか確認してみましょう。
また、私たちは、交通事故に関係する保険の内容について日々勉強を重ねているので、お話しを聞いた上で、それが通常保険から支払われる類のものかどうか判断することができます。
特に、仕事ができなくなったことに対する補償などは、生活に直結する大事な問題となります。「こういった費用って支払われないの?」と思ったら、一度弁護士に相談することをお勧めします。
(文責:弁護士 前原 彩)
困ったらすぐ相談(弁護士 前原 彩)
交通事故に遭った!どうしよう?
今まで3回も4回も交通事故に遭いました、という人はめったにいません。
みなさん初めて交通事故に遭うという方ばかりです。交通事故に限った話ではないですが初めてのことってよくわからないことだらけですよね。
交通事故に遭ってしまった!どうしよう?今後どうなるの?と不安をたくさん抱えていらっしゃる方も多いと思います。

交通事故って複雑
そういう時に、インターネットを使って調べるという方法が最も手軽です。今の時代、インターネットで何でも調べられることが多いです。
しかし交通事故については、私たちから見ると、いろんな情報が溢れすぎていて、かえってわかりにくい場合が多いです。そして困ったことに、間違った情報が堂々と載せられている場合も多いです。
それは、交通事故の複雑さゆえだと思います。
交通事故の賠償額一つとっても、自賠責の場合は、任意保険の場合は、はたまた際弁所の場合は…など、基準だらけです。その上、過失割合の話まで出てきたりして、もうちんぷんかんぷんです。
困ったらすぐ相談
そこで、私は、困ったらすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
そして相談するタイミングは早ければ早いほど良いです。
相談するタイミングが早いほど、私たちは様々な解決策・解決までの道のりを示すことができます。もう既に色々なことが行われてしまった後では、どんな敏腕弁護士でもできることは限られてしまいます。
弁護士に相談したら依頼しなくちゃいけないなどということは全くありません。相談していただくだけでも、その後の解決方法が全く異なってくる可能性が多いにありますので、交通事故で「困った」が出てきたらすぐに相談してみてください。
ちなみに当事務所は、初回60分のご相談が無料になっていますので、是非ご活用ください。
(文責:弁護士 前原 彩)
交通事故の直後にするべきこと(弁護士 今村 公治)
事故直後の対応が必要であること
交通事故に遭ってしまった場合、直後に対応を迫られることがいくつかあります。
人生のうち何度も経験することではないため、あまり慣れている方はいないと思いますが、初動の違いで結論が大きく変わることもあります。
警察や保険会社との対応、適切な治療等について、事故直後から検討しなければなりません。

まずは記録化が必要です
交通事故に遭ってしまったら、まずは警察に通報します。警察官に、事故の態様を正確に記録化してもらいましょう。
また、相手方の氏名、住所、連絡先、保険会社を把握しておいたほうがよいです。
また、病院にいって、適切な検査・治療を受け、事故直後のケガの状態を正しく記録化してもらう必要があります。
できるだけ早期のアドバイスが必要です
万が一、自転車事故の被害に遭われてしまった場合には、早期に病院で適切な治療を受けることはもちろんですが、適正な補償を受けるためには、事故直後か、できるだけ早い時期に、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故の案件は、弁護士のなかでも専門性の高い分野の案件になります。
交通事故にあまり詳しくない弁護士に相談した場合、「治療が終了してから相談に来てください」と、初回相談を先延ばしにされることがあるようですが、これは間違いです。
弁護士に相談するのは事故後いつがよいのかというと、事故後早ければ早いほど良いということになります。
早期の段階で専門家からのアドバイスを受けることによって、適正な後遺障害の等級認定をしてもらうことができ、賠償金額が大幅に増えることがあります。
他方で、事故直後の対応や症状固定前の対応を間違ってしまうと、適正な賠償を受けられない可能性が高いです。
たとえば極端な話、後遺障害が残るような事案でも、医師が診断書に何も記載していなければ、あるいは適切な検査結果のデータがなければ、後遺障害がないと判断されてしまうことも考えられます。
警察への事故の伝え方、医師への症状の伝え方、事故直後に受けておくべき病院の検査、健康保険や労災保険の利用、相手保険会社への対応の仕方など、事故に遭った直後から様々な対応を迫られますが、ただでさえ事故による被害を受けて大変なのに、全ての対応を1人で行うことは相当な苦痛を伴います。
そこで、適切な賠償を受けるためには、できるだけ早期の段階で、交通事故に詳しい専門家に相談し、正しい知識・経験を備える必要があります。
(文責:弁護士 今村 公治)
弁護士に相談、依頼することのメリットを改めて考えてみると(弁護士 三井 伸容)
交通事故にあわれた被害者の方には、御身体の今後のこと以外にもたくさんの悩み事が生まれてしまいます。仕事、刑事処分を含めた加害者側への対応、お金の問題(治療費、休業補償等)、将来の生活等々、ひとつずつ挙げたらキリがありません。
突然の事故でこのような悩みを一度に抱えてしまった場合、どうして良いのかわからなくなり、パニックになってしまう方もいるのではないでしょうか。

実際にご相談にいらっしゃる方にも、私の感覚にはなりますが、①損害賠償の増額などの明確な目的をお持ちでご相談にいらっしゃる方と②漠然とした不安や悩みをたくさん抱えてしまい、どうしようもない状況でご相談にいらっしゃる方の2タイプがいらっしゃるように感じます。
私自身も含め、人間はただ生きているだけでも悩みが尽きませんので、そこに交通事故の悩みが加われば、とても不安な気持ちになるのは当然だと思います。
弁護士というのは人の悩みに触れる仕事ですので、事件の中で依頼者の方がどのような点に不安を感じていらっしゃるのかを考えることが多いです。私は、その中で「先行きがどうなるかわからない。今後の流れがよくわからない。」ということが人をとても不安にさせるのだなとよく感じます。そのため、私は、やや細かすぎるのかもしれませんが、ご相談時に今後の手順やありうる事態などを丁寧に説明するように心掛けております(もちろん、私は超能力者ではありませんので、先を全て見通すことはできませんし、また十分な根拠もなく楽観的な見通しを示すこともまた不誠実だと考えますので「現在想定し得る範囲で」という限定はついてしまいます。)。
なお、依頼者の方のお話を伺っていると、交通事故被害者が抱えるたくさんの悩みや不安の中にも、その一部は弁護士に依頼や相談することだけで大分軽くなることがあるようです。これは弁護士に依頼をすることの効果の一部である「加害者や保険会社と直接やりとりをしなくて済むようになること」や「たくさんの難しい選択を迫られる中で、その選択を一緒に考えたりアドバイスをしてくれる人が身近に出来ること」が大きいのではないかと思います。また、依頼者の方が非常に心配されていたことでも、それが誤解に基づいていたりして、弁護士に聞いただけであっさりと解決してしまうこともあるようです。そのため、ご相談者の方から「もっと早く相談しておけばよかったよ。」と言われることも多々あります。
交通事故に遭われた方が弁護士に相談することは現在において別に珍しいことではありません。病気にかかればお医者様に看てもらうように、交通事故に遭われたらお気軽に弊所にご相談頂ければ幸いです。
(文責:弁護士 三井 伸容)
11 事故後間もない時点での相談(弁護士 佐藤 寿康)
怒りっぽくなった。
治療も終わり、保険会社からの示談額の提案も受けたが、これで良いのかどうかわからないという相談を受けました。
詳しくお話をお伺いしますと、歩行中に自動車に衝突され、頭部と足部の受傷による嗅覚障害と可動域制限の後遺障害が認められたとのことです。
もちろん、保険会社の提案額は、認められた後遺障害との関係では、適正なあるべき損害額より低額のものでした。

ところが、さらにお話をお伺いしていくと、事故後は数日間意識が全くなかった、外傷性くも膜下出血といわれていたというのです。どうやら、高次脳機能障害の入口の要件は満たしていそうです。
さらに、一緒にお住まいの御家族によると、「人の名前が思い出せないということが多くなった。」「怒りっぽくなった。前に比べると、些細なことで怒る。」といったお話が出て参りました。
ところが、この方は事故直後からの入院が終わって退院した後、脳外科での治療はされていません。
そもそも高次脳機能障害を疑われず、整形外科と耳鼻科での通院だけをしていたのです。
治っていたかもしれない。
もちろん、高次脳機能障害がそもそもなかったのであれば、何の問題もありません。
しかし、事故前から一緒にお住まいであった御家族の感じられた被害者の方の性格の変化は、全てが気のせいであったと言い切ることはできないでしょう。
もし高次脳機能障害が発症しており、そのための適切な治療がなされていれば、その方は治っていたのかもしれません。
また、治療が行われてある程度は改善したものの能力低下が残ってしまっていたのであれば、それは後遺障害として評価され、適切に補償されるべきです。
ところが、既に事故から2年程度経過しており、それから脳外科を受診しても、治療上も損害賠償の観点からも有効ではありません。
結局、前記の嗅覚障害及び可動域制限の後遺障害が残ったことを前提として訴訟を提起し、解決しました。
事故後間もない時点での相談
医師は忙しく、患者1人当たりの診察時間を長くとることはできません。ましてや、事故の被害に遭う前の患者を知らないので、事故前と比較した患者の様子の細かな違いに気づくのは容易ではありませんし、それはやむを得ないことでしょう。
また、一緒にお住まいの御家族が感じた事故前との違いも、場合によっては些細なことや気のせいかもしれないと受け止められ、それっきりになってしまうかもしれません。実際、この件ではそうでした。
こうした事態が生じることはあってほしくないと強く思いました。この件では、できることがほかにあったかもしれません。
是非、事故後間もない時点で一度法律相談をするのをお勧めする次第です。
(文責:弁護士 佐藤 寿康)
初回相談において心掛けていること(弁護士 前田 徹)
初回相談
初回相談は、私たちが初めて相談者の方とお話しをする大切な場面です。
初回相談において、私は特に次の3点を心掛けています。

話を聞くこと
まずは、相談者の方のお話しをよく聞くことを心掛けています。
弁護士は初めて相談者の方からお話しをうかがう際には、法律的な観点から必要な内容は何かを意識してお話しを聞いています。
そうすると、つい、弁護士の側から一方的に、法律的に必要な部分だけを聞いてしまうことがあります。そうすると、相談者の方は自分の思いや辛さを弁護士に伝えることができずに初回相談が終わってしまうことがあります。
私は、初回相談では、時間を掛けて、できるだけ相談者の方の“思い”を聞くように心掛け、解決へ向けて“思い”を共有していきたいと考えています。
不安を解消すること
相談者の方の多くは、初めて交通事故の被害に遭い、弁護士に何かを相談することも初めてという方です。そして、多くの方は、今後の解決への道筋や、今何をすればよいのかという点に大きな不安を抱えていらっしゃいます。 初回相談では、できるだけ今後の解決への道筋を示し、今やるべきことをお伝えし、その点で少しでも不安をなくしていただければと考えております。
以前、バイク事故で入院されている方のご家族のご相談を受けました。被害者ご本人は入院中のためご来所はできなかったのですが、ご家族のお話から、ご本人の不安が大きいということが分かりました。私はすぐに日程調整をして、入院中の病院へうかがい、ご本人とお話をさせていただきました。
そこで、今後の解決への道筋や、いまやるべきことは治療に専念してもらうことで、保険会社とのやり取りなどに関して心配しなくて大丈夫ですということをお伝えすると、ご本人は安心されていました。
その後、ご本人は懸命に治療・リハビリに専念され、回復が進みました。このときには、ご本人のみならず、ご家族からも非常に感謝されました。
このように、初回相談では、被害者やそのご家族の方が抱える不安を少しでも解消していければと考えております。
真の被害者救済の観点から考えること
弁護士が交通事故の案件で果たすべき役割として、賠償金の獲得があります。もちろん賠償金の問題は非常に重要であることは間違いありません。
しかし、当事務所では、賠償金の問題のみならず、“真の被害者救済”を目指したいと考えております。例えば、重度の障害を負った被害者の方が、今後安全かつ快適に生活していくために、どのように自宅を改造すればよいのかにつき悩まれている場合には、専門家の意見をうかがいながら適切なアドバイスをしていきたいと考えております。
また、高次脳機能障害になってしまわれた被害者の方やそのご家族が、社会の中で孤立しないようにするために、高次脳機能障害の家族会などの団体をご紹介したりするなど、賠償問題以外の部分でも、被害者の方のお役に立ちたいと考えております。
初回相談時に、被害者の方の思いや辛さを十分に聞いて、“真の被害者救済”に向けてベストの解決方法を考えていきたいと思います。
(文責:弁護士 前田 徹)