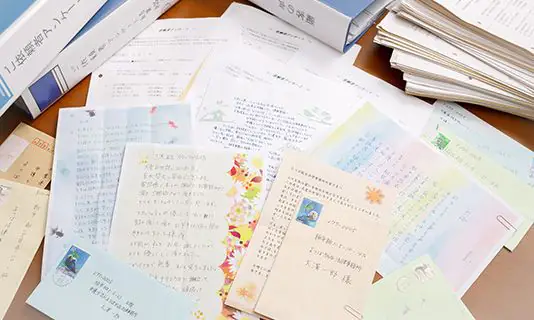後遺障害診断書を書いてくれない6つの理由と対応方法
最終更新日:2025年11月4日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博
- Q医師が後遺障害診断書を書いてくれません。どうすればよいですか?
-
後遺障害診断書の作成を医師に断られた場合でも、諦める必要はありません。まずは断られた理由を正しく把握し、それぞれに応じた適切な対応を取ることが重要です。
後遺障害診断書は、今後の損害賠償請求や後遺障害等級の認定に直結する、非常に重要な書類です。医師の判断には医学的根拠があることもありますが、制度の誤解や情報不足によるものも少なくありません。
理由を正確に把握し、状況に応じた対応を取るとともに、弁護士への相談も検討しましょう。

目次
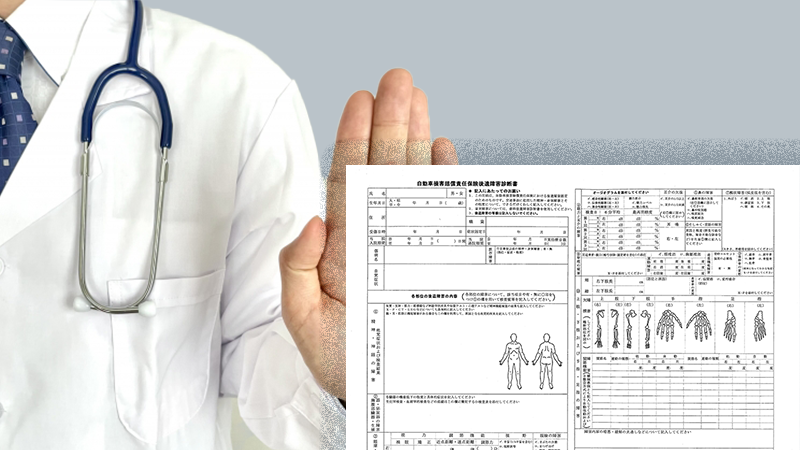
後遺障害診断書とは
交通事故の被害により、治療を受けても症状が完治せず、何らかの障害が残ってしまうケースがあります。そのような場合に必要となるのが「後遺障害診断書」です。
後遺障害診断書は、自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責保険に提出する正式な書類で、後遺障害の等級を決めるために使われます。
後遺障害等級の認定は、基本的に提出された書類だけをもとに行われるため、後遺障害診断書の内容が認定結果を大きく左右します。記載内容ひとつで、後遺障害が認定されるかどうかや、その等級、さらには賠償金の金額まで変わってきます。
後遺障害診断書は、国家資格を持った医師しか作成できません。整骨院や接骨院では作成できないため、通常は継続して診療を受けている主治医に依頼することになります。
また、作成のタイミングも重要です。診断書は「症状固定」後、つまりこれ以上治療を続けても大きな改善が見込めないと判断された時点で初めて作成します。
書式は自賠責専用のもので、A3サイズが基本です。
記載される内容には、入通院期間や症状固定日、現在の自覚症状、検査結果、関節の可動域測定結果などが含まれます。これらの記載内容があいまいだったり、情報が不足していたりすると、適切な等級が認められないこともあるため注意が必要です。
医師が書いてくれない場合の対処法
後遺障害診断書の作成を依頼したにもかかわらず、「まだ作成できません」「今回は対応できません」といった理由で断られることがあります。手続きの第一歩が思うように進まない状況では、不安を感じる方も少なくありません。
ただし、医師が作成を渋る背景には、何らかの理由があります。まずはその理由を正確に把握し、状況に応じた対応を取ることが大切です。
ここでは、よくあるケースと具体的な対応方法をご紹介します。
症状固定ではないと言われた場合
後遺障害診断書は症状固定時に作成するため、医師が「まだ治療効果が期待できる」と判断すれば、診断書の作成を見送るのは自然な対応です。
この場合は、医師に「症状固定と判断できる見込み時期はいつ頃ですか?」と尋ねましょう。その時期までリハビリや検査を継続し、後日症状固定と判断する際に再度依頼するのが現実的です。
後遺症はないと言われた場合
医師が「後遺症はない」と判断する背景には、レントゲンやMRIなどの画像所見で異常が見られないことから、後遺症と認識していないケースがあります。
しかし、自賠責保険上の「後遺障害」は、必ずしも画像で確認できる必要はなく、むち打ちなど見た目ではわかりにくい症状も対象です。たとえば、画像で確認できる異常がないとしても、むちうちの症状(首の痛みなど)について自賠責保険における後遺障害となる可能性もあるのです。
「腰が痛い」「手がしびれる」など現在の状況を伝え、「そのまま記載していただきたい」と丁寧に依頼しましょう。
事故による症状ではないと言われた場合
医師が「症状は事故と関係ない」と判断する場合、因果関係が証明されていない可能性があります。
このようなときは、救急搬送記録、初診時のカルテ、紹介状、画像データなどを集めて、事故直後からの経過を医師に提示しましょう。通院期間が空いてしまった場合は、通院できなかった理由も説明しましょう。
むち打ちなどでは事故前から椎間板の変性があったなどといわれることもあります。このような場合でも、事故によって症状が引き出された(出現した)のであれば、後遺障害の対象です。医師に丁寧にそのことを伝え、後遺障害診断書の作成をお願いしましょう。
健康保険の場合は書けないと言われた場合
医師の中には、「健康保険を利用していると後遺障害診断書は作成できない」と誤解している方もいます。
しかし実際には、健康保険を使用して治療を受けていたとしても、診断書の作成には全く問題ありません。保険の種類(治療費の支払方法)と診断書作成の可否は無関係です。
このようなケースでは、「後遺障害診断書は自賠責保険への後遺障害の申請に必要な書類であり、健康保険の利用とは関係がありません」と丁寧に説明し、改めて作成を依頼してみましょう。
病院の文書窓口とも連携して、自賠責専用のA3用紙を準備しておくと、よりスムーズな対応が期待できます。
治療の経過がわからないと言われた場合
転院や主治医の変更があった場合、現在の医師が事故直後からの経過を把握しておらず、「診断書は作成できない」と言われることがあります。
このような場合には、前の医療機関から紹介状や診療録、画像データなどを取り寄せ、現在の主治医に提出しましょう。治療経過を把握できるようにすることで、診断書作成の可能性が高まります。
また、医師から「転院したばかりなので、もう少し経過を見たい」と言われることもあります。その場合は指示された期間しっかり通院を継続し、一定の診療記録がたまった段階で改めて診断書作成を依頼しましょう。
診療した医師が病院にいないので書けないと言われた場合
担当医が退職や異動により不在となった場合、「現在の病院では診断書を作成できない」と言われることがあります。
まずは病院の文書担当窓口に相談してみましょう。過去の担当医と病院が連絡を取って、うまく対応してくれることもあります。
その病院での作成が難しい場合には、転院先で一定期間通院し、経過観察を経た上で、新しい主治医に改めて診断書作成を依頼する方法もあります。
どうしても作成が難航する場合には、交通事故案件に詳しい弁護士に相談し、診断書の依頼文や補足資料を整えてもらうことで、よりスムーズに進められる可能性があります。
よくあるご質問
後遺障害診断書に関して、実際によくいただくご質問をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
主治医以外の医師に作成してもらってもよいですか?
本来、継続的に診療を受けてきた主治医が、診断書を作成するのが最も適切です。治療経過を把握しており、通院記録や症状の変化などを診断書に反映しやすいためです。
一方で、主治医に依頼できない事情がある場合は、他の医師に後遺障害診断書の作成を依頼するという選択肢もゼロではありません。
その場合は、いきなり書類作成を依頼するのではなく、まずは一定期間別の病院に通院し、治療や症状の経過を観察してもらうことが前提になります。診療内容が不十分だと判断されれば、作成を断られる可能性もあるためです。
後遺障害診断書なしで手続きを進めてもよいですか?
後遺障害の等級認定を受けるには、後遺障害診断書の提出が必要です。この書類がなければ、申請手続きそのものを進めることはできません。
後遺障害診断書は、自賠責保険に対して後遺症の存在と程度を証明する、極めて重要な書類です。認定は原則として書面審査によって行われるため、診断書の内容がそのまま等級や賠償額に影響します。
もし医師から作成を断られている場合は、まずその理由を確認し、適切な対処を行うことが重要です。「症状固定ではない」「事故との因果関係が不明」「健康保険治療だから作成できない」など、よくある理由にはそれぞれ対応策があります。
どうしても診断書を入手できない場合、申請自体が不可能となるため、弁護士などの専門家に相談し、医師への依頼方法や資料の整え方などをサポートしてもらうとよいでしょう。
まとめ:後遺障害診断書を書いてもらえない場合は弁護士に相談
後遺障害診断書は、等級認定を受けるために欠かせない重要な書類です。しかし、医師に作成を依頼しても「症状固定とは言えない」「事故との因果関係が不明」「治療経過がわからない」などの理由で、断られてしまうケースも一定数あります。
こうした状況では、医師とのやり取りや必要書類の準備などを自分ひとりで対応するのは大きな負担になります。依頼の仕方がわからない、医学的な説明に自信がない、といった場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士であれば、医師への依頼文の作成や資料の整理、後遺障害等級の申請手続きまで幅広くサポートが可能です。
後遺障害の認定結果は、将来の賠償額や生活設計にも大きな影響を与えるため、早めに弁護士の力を借りて、適切な対応を進めましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博