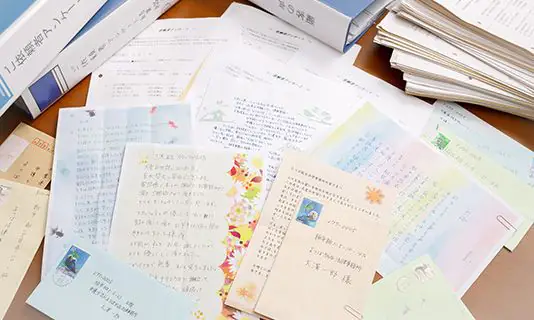後遺障害診断書の自覚症状の記入例や伝え方の5つのポイント
最終更新日:2025年10月31日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博
- Q後遺障害診断書の自覚症状の記入例や伝え方にはどのようなポイントがありますか?
-
症状の部位や程度を正確に伝え、漏れなく、一貫性をもって簡潔にまとめることが大切です。
自覚症状欄は、後遺障害等級認定を左右する重要な項目です。診断書にきちんと反映されなければ、どれほど強い痛みやしびれが残っていても「存在しない」と扱われるおそれがあります。

目次

後遺障害診断書とは
後遺障害診断書とは、交通事故などによって負ったけがが完治せず、何らかの障害が身体に残った場合に、医師が作成する診断書です。自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)において、後遺障害等級認定の申請に必要となる、非常に重要な書類です。
後遺障害診断書には、被害者の基本情報や受傷日時、症状固定日、通院期間、診断名、事故前からの既存障害、自覚症状、他覚所見、検査結果、そして今後の見通しなどが記載されます。形式は病院独自のものではなく、自賠責保険が指定する書式を使用する必要があります。
後遺障害等級の認定は医師が行うものではなく、提出された後遺障害診断書などの資料をもとに、自賠責損害調査事務所(損害保険料率算出機構)が判断します。
そのため、後遺障害診断書の内容が不十分であったり、必要な検査結果が記載されていない場合、適切な等級が認定されない可能性があります。これにより、受け取れる賠償額に大きな差が生じることもあります。
だからこそ、医師としっかり連携し、必要な検査や資料を整えたうえで、正確かつ充実した後遺障害診断書を作成してもらうことがとても大切です。
自覚症状を正しく伝える必要性
後遺障害診断書には、医師が客観的に認定する「他覚所見」だけでなく、被害者本人が感じている「自覚症状」も記載されます。この「自覚症状」欄に記載されていない症状は、原則として後遺障害として評価されません。
特に、むちうちのように外見や画像検査で異常が出にくい傷病では、自覚症状の内容が認定結果を大きく左右します。
自覚症状は、患者本人にしか把握できない主観的な情報です。痛みやしびれの出る部位、症状の発生時刻や頻度、日常生活への影響などを、診察時に具体的かつ的確に医師へ共有することが求められます。
あいまいなまま伝えると、カルテや診断書にも抽象的にしか反映されず、正しい評価が得られないおそれがあります。
後遺障害診断書は一度完成すると修正が難しいため、受診の前に日常生活で気になる症状を整理してメモしておくと安心です。
記載欄に入りきらない場合は、別紙にまとめて添付してもらうこともできます。事前に医師と相談して、正しく反映されるように準備しておきましょう。
自覚症状の伝え方のポイント
後遺障害診断書に自覚症状を正確に反映してもらうには、次の5つの点に注意しましょう。
- 正確に伝えること
- すべての場所の自覚症状を伝えること
- 事故直後から一貫していることを伝えること
- 常時性があることを伝えること
- 簡潔に伝えること
ここでは、それぞれのポイントを詳しく解説します。
① 正確に伝えること
医師が自覚症状を後遺障害診断書に正しく記載できるよう、できるだけ具体的で事実に基づいた情報を伝えることが大切です。
次の5点を意識して整理すると、伝え忘れや誤解が生じにくくなります。
- 症状が出た時期(事故当日から継続しているか)
- 症状が出ている部位(部位、左右、広がり)
- 症状の強さ(最も強いときを10とした現在の程度)
- 症状の質(ズキズキと痛い、ジンジン痛い、ビリビリしびれるなど)
- 継続性(断続的か、持続しているか)
これらの要素を含めて説明することで、症状の全体像が明確になり、診断書にも客観性と信頼性のある内容が記載されやすくなります。
たとえば、次のような表現で伝えると、症状が正確に伝わりやすくなります。
- 「事故当日から首にズキズキする痛みが継続。痛みは10段階で6程度。」
- 「右肩に常時痛みがあり、洗濯物を干す動作で特に悪化。痛みの強さは日中10段階で5、夕方以降は7まで上がる。」
一方で、次のように情報が不十分だったり、曖昧な表現になっていると、正確な診断や認定が困難になることがあります。
- 「首に違和感がある。」
- 「なんとなく首が重いが、うまく説明できない。」
このように、自覚症状を正確に伝えるには、内容の具体性と整理された説明が不可欠です。
医師に誤解なく伝えることができれば、後遺障害診断書の精度も上がり、後遺障害の等級認定においても、より適切な評価が得られる可能性が高まります。
② すべての場所の自覚症状を伝えること
後遺障害の等級認定では、症状が出ている部位を漏れなく伝えることが欠かせません。主要な症状だけを記載すると、それ以外の症状は後遺障害として評価されない可能性があります。
医師に伝える際には、痛みやしびれが出ている部位を漏れなく、具体的に説明するようにしましょう。抽象的な表現は避け、症状がある部位ごとに明記するのが基本です。また、片側だけに出ている症状は、左右どちらかを示すことも重要です。
次のように、部位ごとに整理され、症状の内容も具体的だと、医師にも伝わりやすくなります。
- 「頚部痛、右肩痛、右上腕のしびれ、腰痛」
- 「頚部から右上肢にかけてしびれ」
- 「右手指のしびれと脱力感」
- 「左膝痛。階段昇降時に特に強い」
- 「腰部痛が持続し、長時間立位で増悪」
一方で、次のような伝え方だと、症状の位置や程度が不明瞭で、医師が作成する後遺障害診断書の精度も低下します。
- 「首や肩がなんとなく痛い」
- 「足が変な感じ」
- 「しびれている気がする」
- 「全身がだるい」
このように、記載の具体性や明確さの有無が、後遺障害等級認定の判断に直結することもあります。
特に、症状が複数ある場合には、1症状につき1行で整理して伝えると、医師にも分かりやすく、後遺障害診断書にも正確に反映されやすくなります。
③ 事故直後から一貫していることを伝えること
後遺障害の認定では、症状が事故直後から現在まで継続しているかどうかが、因果関係を判断するうえで非常に重視されます。
たとえば、後遺障害診断書に「症状は事故後しばらくしてから出現」といった記載があると、事故との関係性が疑われ、適切な後遺障害等級認定がされないおそれがあります。
そのため、初診時点からの症状の経過を一貫した内容で伝えましょう。特に、複数の医療機関を受診している場合には、症状の表現をそろえ、記録に矛盾が生じないようにすることが大切です。
では、どのように伝えるのが望ましいか、例を挙げて確認していきましょう。
- 「事故当日から頚部痛が持続」
- 「右肩の痛みは初診翌日から継続している」
- 「初診時から右上肢のしびれが続いている」
- 「事故当初から頭痛があり、現在も頻度は変わらない」
これらの表現は、症状の発症時期が明確で、継続性もはっきりと伝わるため、事故との因果関係を示すうえで有効です。
一方で、次のような表現は、症状の継続性や発症時期が曖昧で、事故との関係を示しにくくなります。
- 「当院初診から2週間後に右肩痛を訴えるようになった」
- 「症状は最近になって強くなってきた」
- 「最初は違和感程度だったので伝えていない」
- 「以前は背中が重い感じだったが、今は痛い」
- 「最初は左手がしびれていたが、今は右手がしびれる」
なお、途中で症状名や表現を変えてしまうことにも注意が必要です。たとえば、「腰がだるい→腰痛→坐骨神経痛」と言い換えていくと、審査する側は同じ症状として認識できずに、一貫性がないと判断される可能性があります。
このような誤解を避けるためにも、可能であれば紹介状やお薬手帳なども参照して他の医療記録と表現をそろえておくことが大切です。
④ 常時性があることを伝えること
後遺障害の認定では、症状が一時的ではなく、常に存在していること(常時性)も重要な判断要素となります。
「たまに痛む」「特定のときだけしびれる」といった表現では、常に症状がある人より症状が軽く見られ、後遺障害と認められにくくなる可能性があります。
つまり、日常的に症状が続いていること、そしてそれが生活にどう影響しているかを具体的に伝える必要があります。
具体的には、次のような表現が常時性の伝え方として適切です。
- 「首の痛みが常に続いており、特に長時間歩いた後や雨の日には痛みが強くなる傾向がある」
- 「右手指のしびれが常にあり、キーボード操作で悪化する」
- 「常に腰部に重い痛みがあり、立位で特に強くなる」
これらの表現は、「常に存在する症状」があることを前提とし、さらに増悪する条件が添えられているため、常時性と生活への影響がともに伝わります。
一方で、次のような表現には注意が必要です。常時性が明確に伝わらず、「一時的な不調」と受け取られてしまう可能性があります。
- 「長時間歩行時に頚部痛」
- 「雨の日だけ痛い」
- 「寒いと肩がたまに痛くなる」
- 「仕事中だけしびれる感じがある」
こうした記載は、特定の条件下でしか出ない一時的な症状のように見えるため、後遺障害としての評価が難しくなるおそれがあります。
言い換えのポイントとしては、「時々痛い」「○○のときだけ痛い」といった表現ではなく、「常に痛みがあり、○○で特に強くなる」という形に統一するのが効果的です。このように記載することで、症状の常時性と、それが生活に与える具体的な影響の両方をバランスよく伝えることができます。シンプルに「首が痛い」「腰痛」といった記載でも問題ありません。
⑤ 簡潔に伝えること
自覚症状を診察の際に医師へ伝えるときには、できるだけ簡潔に整理して説明することが大切です。基本的には、1症状につき1行で表現すること。まとまりのある短文で、情報を絞りながらも要点を押さえておくことが効果的です。
特に、次の項目は伝えるように意識しましょう。
この形式を意識して伝えることで、医師も後遺障害診断書の自覚症状欄に反映しやすくなります。
次の記載は、上記の形式を踏まえたもので、簡潔でわかりやすい表現になっています。
- 「常に首がズキズキと痛い」
- 「頚部痛が常時あり、強さは10段階で6。長時間PCで特に増悪。就寝中に中途覚醒。」
- 「右肩痛が常時。腕の挙上で特に増悪。洗濯物の上げ下ろしが困難。」
- 「右前腕のしびれが持続。ペットボトルのふた開けが困難。」
一方で、次のような内容だと情報量が不足しており、具体的な後遺障害の程度が読み取れません。
- 「頚部痛に違和感」
- 「肩が痛いがたまに」
- 「しびれがある気がする」
このように、自覚症状を簡潔に伝えることは、読み手に正確に理解してもらうための基本です。要点を整理し、伝えるべき情報をわかりやすく表現できれば、医師の診断や診断書作成もスムーズになり、後遺障害等級の適切な認定にもつながります。
よくあるご質問
後遺障害診断書に関して、よくいただくご質問とその対応方法をまとめました。提出前のチェックや医師とのやり取りで迷ったときは、ぜひ参考にしてください。
後遺障害診断書でチェックすべきポイントはどこですか?
後遺障害診断書の提出前に、以下の6つの点をしっかり確認しておきましょう。どれも後遺障害等級認定に直結する重要な内容です。
-
症状固定日
医師が医学的に判断した日付になっているか確認します。症状固定日とは医学的にこれ以上治療をしても症状の改善が見込めない日を指します。
単に保険会社が「治療を打ち切った日」ではなく、症状の経過や生活状況とも整合が取れているかがポイントです。
-
入院・通院期間
初診日・最終受診日・入退院日・通院実日数などが正確に記載されているか自身の記録や、保険会社が所持している自賠責用診断書・診療報酬明細書と照らし合わせて確認しましょう。
-
自覚症状
痛みやしびれの部位・左右・範囲、強さ、質、連続性・常時性、日常生活への影響など、具体的に書かれているかを確認します。
「違和感」「しびれ感」「○○等」「なんとなく」などの抽象的な表現は避け、伝えるべき情報を明確にしましょう。
-
検査結果(他覚所見)
X線・CT・MRI、神経学的検査(反射・知覚・筋力など)が必要な範囲で実施・記載されているか確認しましょう。
また、自覚症状と検査結果に整合性があるかも重要なチェックポイントです。
-
可動域の測定
関節面の骨折があり、可動域に障害がある場合、左右差のある具体的な数値(他動値)が記載されているか確認します。
角度が基準を満たしていないと、後遺障害等級認定の対象にならないこともあるので注意が必要です。
-
増悪・緩解の見通し
症状が長期間にわたって安定している場合は、「症状固定」「緩解困難」など、実態に沿った表現になっているかを確認します。
不自然に軽快の見込みが強調されている場合は、後遺障害診断書の内容を再確認して医師と相談しましょう。
医師が後遺障害診断書を書いてくれません。どうすればよいですか?
医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合、まずは理由を確認することが第一です。理由に応じて、次のような対応を取りましょう。
-
「症状固定ではない」と言われた場合
これまでの治療経過を整理し、症状が継続している、自身の感覚して改善していないことを説明します。もし応じてくれない場合には、いつ頃症状固定と見込まれるか、具体的な見込みを確認しましょう。
-
「後遺症はない」と言われた場合
実際の自覚症状や生活への支障を、メモや具体例を使って丁寧に伝えましょう。必要に応じて、検査の追加を依頼することで、医学的な裏付けが取れる場合もあります。
-
「事故による症状ではない」と言われた場合
事故時の状況(車両の損傷写真や衝撃の程度)、事故直後からの症状の一貫性、事故前はこのような症状は一切なかったことを整理して医師に伝えましょう。自賠責保険では仮に事故前から変性等があっても、事故によって症状が引き出されたと考えられれば、後遺障害として取り扱います。どうしても医師が応じてくれない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
-
「健康保険で治療していると書けない」と言われた場合
自賠責保険や後遺障害の申請手続き上、健康保険の使用有無は、診断書の作成には関係ありません。後遺障害診断書がないと後遺障害の申請はできません。
病院の医事課などに確認したうえで、改めて診断書の作成を依頼しましょう。
-
「治療経過がわからない」と言われた場合
他院での診療記録や紹介状を持参し、医師が状況を把握できるようにサポートします。情報不足を補えば、診断書を書いてもらえる可能性が高まります。
-
「担当医が不在・退職している」と言われた場合
カルテが残っていれば、同じ病院の別の医師が後遺障害診断書を作成できることがあります。
それが難しい場合は、現在の主治医か、以前の担当医のどちらかに依頼できないかを確認しましょう。
まとめ:自覚症状の伝え方に悩んだら弁護士に相談
後遺障害診断書の内容は、後遺障害等級の認定や賠償額に直結する非常に重要なものです。
たとえば、むちうち14級の認定においては、「自覚症状」の伝え方は、書き方ひとつで評価が変わる可能性があり、細かな配慮が求められます。
どのように伝えるべきか迷ったときや、医師にうまく説明できるか不安がある場合は、早めに交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
症状整理のサポートや、診」断書作成時のポイント、医師への伝え方まで具体的にアドバイスを受けられるため、納得のいく認定と補償につながる可能性が高まります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博