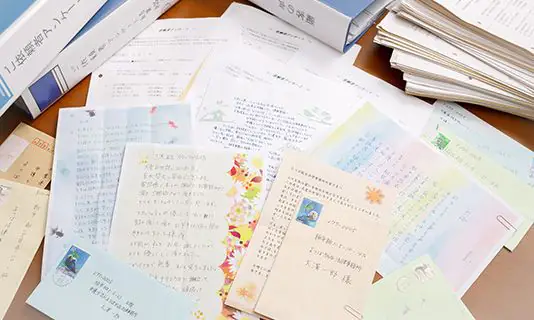交通事故の後遺障害診断書
最終更新日:2025年11月4日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博
- Q交通事故の後遺障害診断書とは何ですか?
-
交通事故でけがをすると、治療を続けても痛みやしびれ、関節の動きの制限などが残ることがあります。こうした症状が「後遺障害」として認められるかどうかを判断するために必要なのが、後遺障害診断書です。
後遺障害等級の認定は、原則として診断書を中心に書面だけで審査されます。
つまり、後遺障害診断書は、審査における最も重要な資料の一つであり、その記載内容が認定結果に極めて大きな影響を与えます。認定結果は、将来受け取れる慰謝料や逸失利益の金額にも大きく影響します。

目次
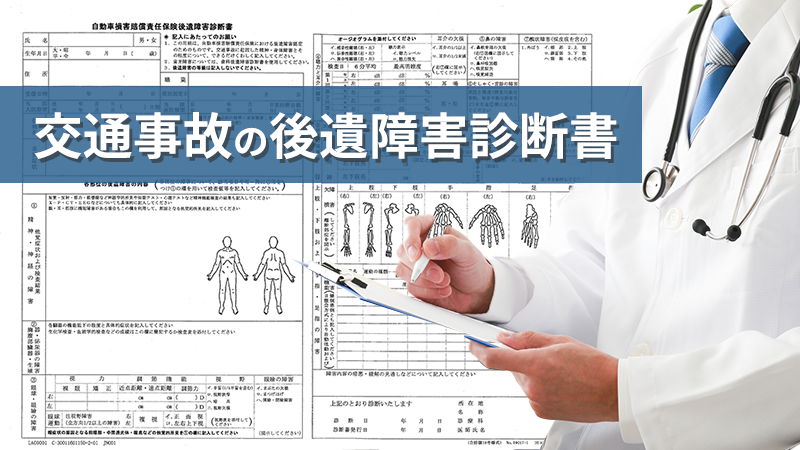
後遺障害診断書とは
後遺障害診断書とは、交通事故でけがをした後に後遺障害等級の申請を行うために必要となる書類です。正式名称は「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といい、後遺障害等級認定の審査に欠かせない基礎資料となります。
診断書には、症状の内容や程度、検査の結果、治療経過や通院期間などが詳しく記載されます。後遺障害等級の認定は基本的に書面審査で行われます。
後遺障害診断書は、審査における最も重要な資料の一つであり、その記載内容が認定結果に極めて大きな影響を与えます。
後遺障害の審査は、診断書に記載されている症状のみが対象になります。記載が不足していると、本来認められるはずの等級がつかず、慰謝料や逸失利益を十分に得られないおそれがあります。逆に、症状や検査所見、生活への影響が正しく反映されていれば、適正な等級認定と妥当な賠償につながりやすいです。
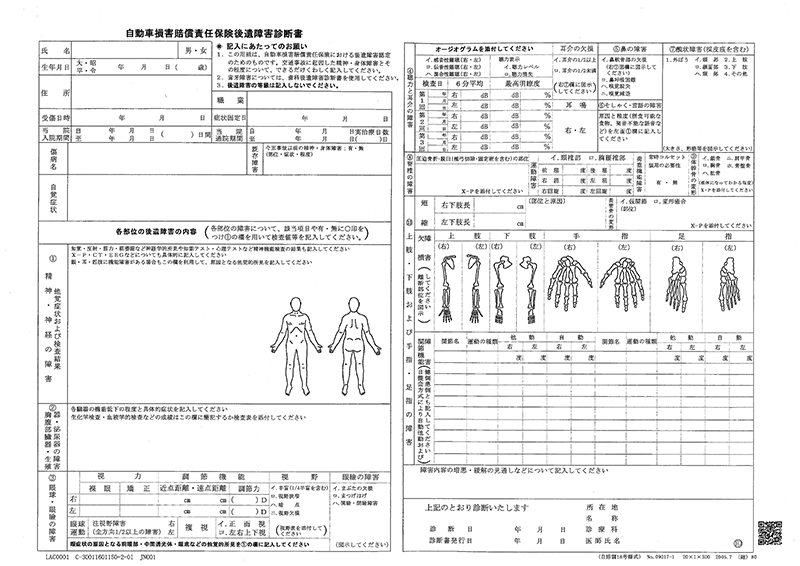
後遺障害診断書ひな形のもらい方
交通事故で後遺障害等級を申請するには、まず自賠責保険で決められた後遺障害診断書の用紙(ひな形)を用意する必要があります。この後遺障害診断書の用紙は、主に次の3つの方法で入手できます。
-
加害者側の任意保険会社から取り寄せる
加害者側の任意保険会社に連絡し、「後遺障害診断書の用紙を送付してほしい」と依頼します。すでに保険会社と連絡を取っている場合は、もっとも手間の少ない方法といえるでしょう。
-
自賠責保険会社から取り寄せる
加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険会社に直接依頼して、診断書の用紙を取り寄せる必要があります。交通事故証明書を取得し、そこに記載されている加害者の自賠責保険会社へ連絡して、診断書の送付を依頼します。
-
インターネットからダウンロードする
インターネットからPDFを入手できます。印刷はA3サイズで行いましょう。A4サイズだとやり直しになってしまうことがあります。
作成できるのは医師のみ
後遺障害診断書を作成できるのは、医師に限られています。法律で定められているため、柔道整復師など医師以外は作成できません。
整骨院や接骨院に通院している場合でも、診断書は病院(整形外科など)の医師に依頼する必要があります。後遺障害診断書の作成に協力してもらえるよう、月1回でも病院を受診し、継続的に経過を記録してもらうことが大切です。
作成時期は治療終了時
後遺障害診断書は、症状固定と判断されたときに作成されます。症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態をいいます。
症状固定の時期は、けがの種類や重さ、治療の内容や経過によって異なります。たとえば、交通事故で最も多いむち打ち(頚椎捻挫)で後遺障害の申請をする場合、事故から6か月程度治療を続けてから、症状固定となり後遺障害を申請するケースが多いといわれています。
スムーズに診断書を用意するためには、治療が長引きそうな場合でも、「症状固定が近づいたら後遺障害診断書を書いてほしい」とあらかじめ主治医に伝えておくと安心です。
後遺障害の申請手続きの流れ
後遺障害診断書を入手してから申請を行うまでの一般的な流れは、次のとおりです。
-
症状固定の診断を受ける
まずは、主治医から「症状固定」の診断を受ける必要があります。この診断を受けることで、後遺障害の申請手続きがスタートします。
後遺障害診断書の作成には、数日から1か月程度かかることもあるため、症状固定と判断された時点で、できるだけ早く作成を依頼するようにしましょう。
-
診断書の書式を入手する
後遺障害診断書は、自賠責保険で定められた専用の書式を使用する必要があります。
任意保険会社または自賠責保険会社に依頼する方法で入手してください。なお、歯に関する後遺障害については、専用の「歯科用の後遺障害診断書」が別途用意されていますので注意が必要です。
-
医師に診断書の作成を依頼する
専用書式が用意できたら、継続的に治療を受けている主治医に診断書の作成を依頼します。
また、複数の部位に後遺症が残っている場合は、担当する診療科ごとに診断書を作成してもらい、複数枚提出する必要があります。
-
診断書を自賠責保険会社に提出する
後遺障害の申請は加害者側自賠責保険会社が窓口となっています。そのため、後遺障害の申請を行うためには、完成した後遺障害診断書やその他の必要書類を加害者側の自賠責保険会社に提出します。
提出方法には次の2種類があります。①任意保険会社経由で提出する事前認定と②被害者が直接提出する被害者請求です。


事前認定と被害者請求どちらがよいか迷った場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害診断書のチェックポイント
後遺障害診断書を提出する前に、次の6つを確認してください。ここに不備があると、等級認定や賠償額に大きく影響する可能性があります。
-
症状固定日
医師がこれ以上よくならないと医学的に判断した日になっているか確認してください。保険会社が治療費を打ち切って、自費で通院を続けている場合、治療費打ち切りの日と症状固定日は異なりますので混同していないかを確かめましょう。
-
入院・通院期間
初診日・最終受診日・通院日数に漏れがなく記載されているかをチェックしましょう。
-
自覚症状
症状の部位・程度・種類が自覚しているとおりに書かれているかを見直しましょう。
-
検査結果
必要な検査が実施されているか、画像検査や神経学的検査の結果がしっかり記載されてしているかを確認しましょう。
-
可動域の測定
動きにくい関節の角度を測定して数値で示されているか、他動値(医師などが体を動かしたときの角度)や左右差が明記されているかを忘れずに確認しましょう。
-
増悪・緩解の見通し
症状固定や改善見込みの判断が、実際の経過と矛盾していないかを確認しましょう。ここで症状が治ると書かれていれば、後遺障害は認定されない可能性が高いでしょう。
不安な点があるときは、そのまま提出せずに弁護士へ相談し、必要に応じて医師に修正や追記を依頼することが大切です。
後遺障害診断書の自覚症状の伝え方
後遺障害診断書の「自覚症状」欄は、等級認定において非常に重要な役割を果たします。
誤解なく、正確に医師へ伝えるためには、内容を整理し、要点をおさえた説明が求められます。もし口頭で医師に伝えにくい場合は、あらかじめメモを作成して医師に渡してもかまいません。
次の5つのポイントを意識して、自覚症状を伝えるようにしましょう。
-
正確に伝えること
症状の部位・程度・種類などを正確に伝えましょう。違和感や重苦しさ、だるさなどといった曖昧な表現を避けるべきです。症状が常にあるのかたまに出現するのか、痛みなのかしびれなのかといった違いも非常に重要です。
-
すべての場所の自覚症状を伝えること
主な部位だけでなく、日常生活に支障があるすべての症状を漏れなく伝えます。特にむちうちの場合、首だけの症状なのか、左右の上肢にも症状(放散痛)が出ているのかといった点は重要です。小さな症状でも、後遺障害の判断に影響を及ぼす可能性があります。
-
事故直後から一貫していることを伝えること
発症のタイミングや、これまでの症状の経過を、時系列に沿って整理して伝えましょう。継続性や一貫性のある訴えは、認定において重要視されます。
他方、それまでなかった症状が、症状固定の段階で突如出現しても、交通事故による後遺障害として認定される可能性は低いです。
-
常時性があれば、常時性があることを伝えること
症状が一時的なものではなく、継続的または繰り返し起こることを明示します。時間帯、動作、状況などとの関係性にも触れておくと、症状の深刻さが伝わりやすくなります。
-
簡潔に伝えること
自覚症状については、できるだけ詳しく書きたいと思うかもしれませんが、たくさん書いてあったり、長いから認定可能性が上がるというものでもありません。
たとえば「朝起きると首が痛い」と記載があると、朝以外は首が痛くないものとして、常に首が痛い人よりも症状が軽いと見なされることもあります。症状を整理し、簡潔かつ的確に伝えるよう心がけましょう。
医師が作成してくれない場合の対処法
後遺障害診断書は、等級認定に欠かせない重要書類ですが、場合によっては医師に依頼しても「書けない」「必要ない」と断られることがあります。その理由にはいくつかのパターンがあります。
-
現時点では症状固定ではないと言われた場合症状固定と認められる時期の見込みを確認し、それまでは治療を継続しましょう。
-
後遺症がないと言われた場合自覚症状を整理し、診察時に具体的に伝えることで再度検討してもらえることがあります。
-
事故との因果関係がないと言われた場合事故現場や壊れた車の写真を資料で示しどのような機序で負傷したのか、発症時期や症状の経過を再度説明して事故との関係性を説明しましょう。必要に応じて専門医の診察も検討します。
-
健康保険での治療だから書けないと言われた場合健康保険の利用と診断書作成は無関係であることを伝え、誤解を解きましょう。
-
転院後で経過が不明と言われた場合前の病院の紹介状や検査記録を用意して、現主治医に経過を伝えることが大切です。
後遺障害診断書について弁護士に相談すべき理由
後遺障害診断書は、等級認定や損害賠償額に直結する重要な書類です。ところが、医師は治療の専門家であっても、後遺障害の認定基準や保険実務に詳しいとは限りません。
そのため、症状や検査結果が十分に反映されず、本来より低い等級で認定されたり、正当な賠償を受けられなかったりすることがあります。
こうしたリスクを防ぐには、診断書の作成前から弁護士に相談しておくのが安心です。
弁護士に相談することで、次のようなサポートが受けられます。
- 診断書作成前に、必要な検査や症状の伝え方について具体的なアドバイスが受けられる
- 完成した診断書の内容を確認し、不備がある場合は医師への修正依頼をサポートしてもらえる
- 適切な等級認定を受けるための書類準備や補足資料の作成を任せられる
- 損害賠償請求や申請手続きなど、保険会社とのやり取りも一任できる
診断書は一度提出すると原則として修正できないため、早めの準備と確認が欠かせません。
もし不安や疑問がある場合は、交通事故に詳しい弁護士に一度相談してみるとよいでしょう。
よくあるご質問
ここでは、後遺障害診断書に関して寄せられるご質問の中から、特に多いものをまとめてご紹介します。
作成にかかる時間はどのくらいですか?
後遺障害診断書の作成にかかる期間は、おおむね1週間から1か月程度が目安です。症状の内容や医師の診療スケジュール、病院の事務処理体制によって前後することがあります。
特に大きな総合病院では、長期間待たされるケースも珍しくありません。逆に、個人クリニックや小規模病院では比較的早く作成してもらえることもあります。
診断書作成をスムーズに進めるには、専用の書式を事前に用意して医師に渡すことが重要です。書式がなければ医師は作成に着手できないため、依頼時に忘れずに持参しましょう。
また、提出期限がある場合は、その旨を明確に伝えることで、優先的に処理してもらえる可能性もあります。必要なタイミングから逆算して、早めに依頼するのが安心です。
作成にかかる費用はどのくらいですか?
後遺障害診断書の作成費用は、一般的に5000円~1万円程度が相場です。大病院では文書料が規定で定められているため大きな差は出にくい一方で、個人病院やクリニックなどでは1万5000円前後のケースもあります。
後遺障害が認定された場合、費用は加害者側の保険会社負担となることが一般的です。一方、後遺障害が認定されなかった場合は、作成費用は自己負担のことが多いです。
作成にかかる費用が気になる場合、事前に保険会社に確認しておきましょう。
後遺障害診断書を作成してもらうデメリットはありますか?
後遺障害診断書の作成を依頼することに、大きなデメリットはありません。あえてデメリットを挙げるとすれば、次のような点です。
- 作成費用として5000円~1万円程度かかります。もっとも、後遺障害等級が認定されれば、保険会社負担となることが一般的です。
- 後遺障害診断書を準備したり、その他の書類を準備したりする手間がかかります。
- 後遺障害の認定手続きに3ヶ月前後かかることが多いので、解決までの期間が長引きます。
主治医に書き直してもらうことはできますか?
後遺障害診断書に誤りや不足がある場合、主治医に修正や書き直しを依頼することは可能です。
ただし、診断書は医学的判断に基づく公的な文書であるため、訂正できるのは医師本人のみです。被害者自身が内容を加筆・修正することはできません。
医師から「書き直しはできない」と言われた場合でも、「どの部分に誤りがあるのか」「なぜ修正が必要なのか」を診療記録や検査結果などをもとに丁寧に説明すると、対応してもらえる可能性があります。
主治医以外の医師に書いてもらうことはできますか?
基本的には、治療経過を一番よく把握している主治医に依頼するのが原則です。通院の記録や経過観察をもとに作成される書類のため、主治医が最も適任だからです。
ただし、主治医に依頼できない事情があるケースや、後遺障害の診断に慣れた専門医に依頼したい場合には、主治医以外の医師に作成をお願いすることも不可能ではありません。
その際は、いきなり診断書の作成を依頼するのではなく、前医の紹介状(診療情報提供書)を持参したり、転院先の医師に一定期間通院し、経過観察を受けたうえで作成してもらうのが一般的です。また、主治医と新しい医師で診断内容が異なる可能性や、転院による費用や手間が発生する点にも注意が必要です。
6か月以上通院しないと書いてもらえませんか?
「後遺障害診断書は6か月以上通院しないと作成できない」というわけではありません。実際の作成時期は、けがの種類や症状の経過によって異なります。
たとえば、むちうち(頚椎捻挫)の場合、6か月以上の治療実績が等級認定において重視されることが多く、症状固定の判断もこの時期を目安に行われます。
一方で、視力や聴力の喪失、骨の変形、四肢の切断など明らかな後遺障害が残る場合は、もっと早い段階で症状固定とされ、後遺障害診断書が作成されることもあります。
後遺障害診断書の有効期限はありますか?
後遺障害診断書そのものに有効期限はありません。一度作成された診断書は、後遺障害等級認定の申請において、期間の制限なく使用できます。
ただし、注意が必要なのは、損害賠償請求に関する消滅時効です。2年、3年、5年などの期間制限がありますので注意しましょう。
まとめ:後遺障害診断書は弁護士に相談
後遺障害診断書は、症状の評価や損害賠償の額に直結する非常に重要な書類です。作成のタイミングや内容、医師への伝え方ひとつで、後の等級認定や賠償結果が大きく変わる可能性があります。
診断書の準備や提出に不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談しておくと安心です。必要な検査や症状の伝え方、診断書のチェックポイント、保険会社とのやり取りまで、専門的なサポートが受けられます。
早めに相談しておくことで、結果に差が出ることもあるため、気になることがあれば一度弁護士に確認してみることをおすすめします。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博