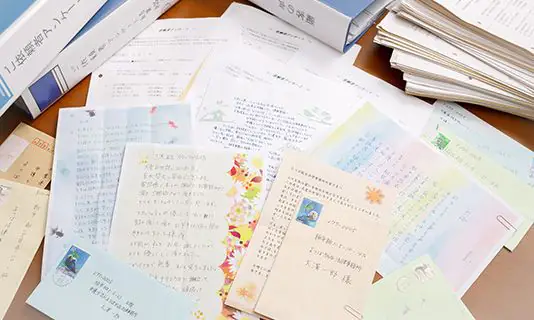後遺障害診断書の6つのチェックポイント
最終更新日:2025年12月17日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博
- Q後遺障害診断書でチェックすべきポイントはどのような点ですか?
-
後遺障害診断書を保険会社に提出する前に確認すべき主なポイントは、次の6つです。
- 症状固定日
- 入院・通院期間
- 自覚症状
- 検査結果
- 可動域の測定
- 増悪・緩解の見通し
これらはいずれも後遺障害等級の認定に大きく影響する重要な項目です。
誤りや漏れがあると、正当な等級が認定されなかったり、損害賠償額に差が出たりすることがあります。
診断書は医師が作成するものですが、内容の最終チェックは被害者本人に委ねられるケースが多いため、提出前にしっかり確認することが重要です。

目次
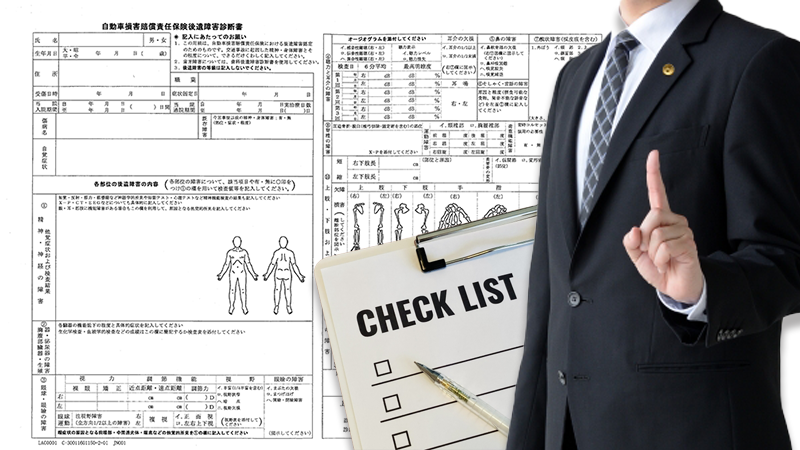
後遺障害診断書とは
交通事故によるけがの治療を続けても、それ以上の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。この時点で残った障害について、損害賠償の手続きに使うために作成されるのが「後遺障害診断書」です。正式名称は「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といい、後遺障害の等級認定に必要な重要書類です。
後遺障害診断書を作成できるのは、あくまで医師のみであり、整骨院や接骨院では発行できません。複数の診療科を受診している場合には、それぞれの科で作成を依頼することもあります。作成のタイミングは、あくまで症状固定後となります。
後遺障害診断書の様式は共通化されており、記載内容には、事故日や症状固定日、通院期間、傷病名、現在の症状、検査結果、将来の見通しなどが含まれます。
後遺障害等級の認定で最も重視されるのは、「症状固定時点で後遺障害の対象となる症状があること、これらの原因となる医学的・客観的所見が記載されていること」です。
必要な検査が未実施だったり、実施済みであるにもかかわらず記載がない場合、認定が難しくなることがあるため、主治医とよく相談し、必要な検査をすべて済ませたうえで診断書の作成を依頼することが望まれます。
正当な認定を受けるためには、作成のタイミング・検査の内容・医師への伝え方に十分注意し、必要であれば弁護士のサポートを受けながら進めることが望ましいでしょう。
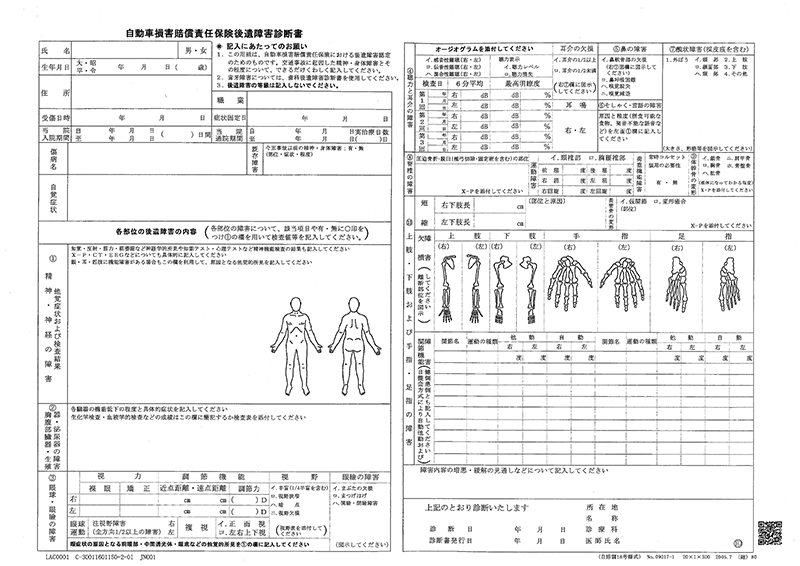
症状固定日はあっていますか?
症状固定日とは、医師が「これ以上の症状改善は見込めない」と医学的に判断した日を指します。この日付がずれると、治療の実態が正しく反映されず、後遺障害の等級認定で不利になるおそれがあります。
まれに、相手方の保険会社が治療費の支払いを打ち切った日が、誤って症状固定日として後遺障害診断書に記載されてしまうことがあります。しかし、打ち切り日はあくまで保険会社の判断によるもので、医学的な根拠があるとは限りません。
こうした誤りを防ぐためにも、症状固定日が本当に妥当かどうか、あらかじめ確認しておくことが大切です。
症状固定日欄のチェックポイント
後遺障害診断書の症状固定日が適切かどうか、次のような点をチェックしてみましょう。
- 医師の医学的判断に基づく日付であるか?
- 薬の処方・注射・リハビリの内容に変化はないか?
- 症状の改善が見込めなくなった、波が落ち着いたタイミングと一致しているか?
- 仕事復帰や家事の負担状況など、生活面の実態と矛盾していないか?
症状固定日が極端に早い場合、通院回数が少ない場合などは、症状が軽く評価されるリスクがあります。
重要なのは、医学的な判断と実際の治療経過・生活状況が無理なく一致しているかどうかです。症状の経過や日常生活の変化と照らし合わせて、自然なタイミングであるかを見極めましょう。
症状固定日欄を医師に確認・訂正してもらうには
症状固定日が適切かどうか不安に感じた場合は、診察の際に医師に相談してみましょう。
確認の際には、次のようなポイントを押さえておくと安心です。
- なぜその日が症状固定日なのか、医学的な理由を聞く
- 症状固定日とは医学的に症状が改善しないと認められる日であること、保険会社の打ち切り日と症状固定日は異なる概念であることを説明する
- 必要に応じて再診のうえ、正しい日付に修正してもらう
もし、医師への伝え方や対応に不安がある場合は、弁護士への相談も検討してみてください。弁護士であれば、後遺障害認定に関わるポイントを整理しながら、適切なアドバイスをすることができます。
入院期間や通院期間はあっていますか?
たとえば、入院期間や通院期間が実際より短く記載されていたり、通院回数が実際より少なく記載されたりすると、症状が軽く見られてしまうおそれもあります。
病院の方でも記録を確認して、期間や日数を記載することが通常ですが、何度も入退院を繰り返していたり、通院日数が多いと誤って記載してしまったりすることもあります。記載漏れがないかを確認しておきましょう。
入通院期間欄のチェックポイント
後遺障害診断書の「入通院期間欄」では、次の点に注意して内容を確認しましょう。
- 初診日と最終受診日が正確に記載されているか?
- 入退院の日付や期間に誤りがないか?
- 通院の日付や期間、実日数に誤りがないか?
入通院期間欄に不備があった場合の対応
入通院期間に誤りや漏れがある場合は、病院に訂正や追記を依頼しましょう。その場合には「どこをどう直すか」を明確に伝えることが大切です。明確な誤記であれば、訂正に応じてくれることが通常です。保険会社が自賠責用の診断書や診療報酬明細書を所持している場合は、写しを送ってもらうと通院の経過を把握しやすいです。
記載内容の修正に不安がある場合は、弁護士に相談することで、医師への依頼文や補足資料の整理をサポートしてもらえます。
自覚症状の記載に問題はありませんか?
後遺障害診断書の「自覚症状」欄は、症状固定時に被害者が訴えていた体の不調を記録する、非常に重要な項目です。後遺障害等級の審査は原則として診断書などの書面のみで行われるため、この欄に書かれた内容が、そのまま認定の判断材料となります。
そのため、どれほど強い症状があったとしても、診断書にきちんと記載されていなければ、「存在しない」と判断されてしまうおそれがあります。
こうした事態を避けるためには、自覚症状がどのように記載されているかを具体的に確認することが非常に重要です。
自覚症状欄の確認ポイント
次の点を中心に、後遺障害診断書の「自覚症状欄」に不備がないか確認してください。
- 症状が残っている部位(例:首、腰、手など)が具体的に書かれているか?
- 「痛み」「しびれ」などの症状が簡潔に記載されているか?
- 実態を反映した表現になっているか?
自覚症状は、少なすぎる記載も問題ですが、多すぎる記載も問題になることがあります。「痛み」「しびれ」などの症状が簡潔にまとまっていると、実態がより正確に伝わります。
他方、雨の日や寒い日だけ痛いなどなどと記載されてしまうと症状が軽く見られてしまいますので注意が必要です。
自覚症状欄に不備があった場合の対応
後遺障害診断書の自覚症状欄に記載漏れや不十分な点があった場合には、主治医に再確認を依頼し、必要に応じて補記や修正をしてもらいましょう。その際には、自身のメモや通院時の記録などをもとに、次の点を意識して説明するとスムーズです。
- どの部分に症状があるのか?
- どのような症状があるのか?
- いつころからその症状があったのか?
なお、後遺障害診断書の修正や再作成が可能かどうかは、医療機関の方針によって異なります。手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することで、医師への依頼方法や記載内容の整理についてサポートを受けることができます。
検査結果の記載は正確ですか?
後遺障害診断書には、画像検査や神経学的検査など、医師が客観的に確認できた異常(=他覚所見)が記載されます。これらの記載は、自覚症状と同様に後遺障害等級の認定に大きな影響を与える要素です。
そのため、後遺障害診断書の内容を確認する際は、「適切な検査が行われているか」と「その結果が正確に反映されているか」をチェックしましょう。
検査結果欄の確認ポイント
後遺障害診断書に記載された検査結果が、認定に必要な情報として正しく反映されているかどうか、次の点を確認しておきましょう。
-
画像検査(レントゲン・CT・MRIなど)の結果が反映されているか?
自覚症状に対応する異常所見が認められる場合、具体的に記載されていると後遺障害が認定される可能性が高くなります。もしこのような所見があると医師が説明している場合には、診断書に明記してもらいましょう。
-
神経学的検査(反射・知覚・筋力など)の結果が記載されているか?
後遺障害の認定のためには、神経学的検査を行っているか、その結果に異常が見られるかという点も重要です。
-
視力・聴力・関節の可動域など、症状に応じた検査項目が抜けていないか?
後遺障害診断書には視力や聴力、関節が動かない場合の可動域など、後遺障害の対象となる全て症状の検査結果を記載する欄が設けられています(歯の後遺障害を除く)。
症状があるにもかかわらず、該当する検査結果の記載がない場合は、記載漏れの可能性があります。
-
必要な検査自体が行われているか?
異常が見られなかったとしても、検査そのものが実施されていなければ、客観的な判断材料として認められにくくなります。
検査結果欄に不備があった場合の対応
検査結果に記載漏れや不十分な点がある場合は、主治医に内容を確認したうえで、追記や訂正を依頼しましょう。その際、次のような対応が有効です。
- 受けた検査と結果に関する医師の説明をメモしておき、それが反映されているかを照合する
- 必要な検査が実施されていない場合は、追加検査をお願いする
- 修正や追記に必要な資料(検査報告書など)を確認してから相談する
ご自身での対応が難しい場合は、後遺障害の申請実務に詳しい弁護士に相談すると安心です。不足している記載箇所の洗い出しや、必要な検査、医師への伝え方について、具体的なサポートを受けることができます。
動く範囲の測定は正確ですか?
交通事故によるけがの影響で、関節の動きに制限が残ることがあります。これを「可動域制限」といい、後遺障害等級の認定において「関節の機能障害」があるかどうかを判断する重要な根拠になります。
動く範囲の測定が正確に行われ、その結果が診断書に正しく反映されているかを確認することが大切です。
可動域制限欄の確認ポイント
可動域制限がある場合、次の点に注意して後遺障害診断書をチェックしましょう。
-
他動値での測定結果が記載されているか?
自賠責保険の後遺障害等級認定では、原則として他動値(医師が関節を動かして測る角度)をもとに判断されます。自動値(本人が動かした角度)のみの記載では、正しく評価されない可能性があります。
-
測定値が明確に数値で示されているか?
「動かしにくい」「あまり動かない」などの曖昧な表現ではなく、関節機能障害の記載欄に角度の数値として可動域が記載されているかを確認しましょう。
-
左右差がわかるよう記載されているか?
障害のある側(患側)と、正常な側(健側)の両方の可動域が記載されていないと、比較ができず、後遺障害の調査を進めることができません。一度申請したとしても、調査機関から追記を依頼されることが通常です。
-
対象となる関節について主要運動の可動域が測定されているか
後遺障害の認定においては、各関節について、可動域の測定方法が決められています。参照する測定方法を主要運動といいます。たとえば、肘関節であれば、「屈曲」と「伸展」の二つの測定方法が参照すべき主要運動です。
可動域測定に不備があった場合の対応
可動域測定の記載内容に不備や不足がある場合は、主治医に確認のうえ、修正や追記を依頼しましょう。
具体的には、次のような対応が有効です。
- 受けた検査内容や測定時の状況をメモしておき、診断書の内容と照らし合わせる。もし測定時の数値がわかるようであれば、後遺障害診断書に記載されている測定値と照らし合わせて確認する
- 他動値の測定がされていない、または記載されていない場合は、再測定をお願いする
- 左右の角度が比較できるよう、健側の測定も依頼する
- 主要運動の計測がなされているか。測定値が見当たらない場合は、追加記載を求める
- 医師に状態を正確に伝えるため、可動域制限による日常生活や仕事への影響も具体的に話す
可動域の測定は、角度の差が数度違うだけで等級が変わるケースもあります。正確な測定と適切な記載がされていなければ、不当に低い後遺障害等級や非該当となってしまうおそれがあります。
判断が難しい場合や、医師への説明に不安があるときは、後遺障害の認定に詳しい弁護士に相談して、アドバイスを受けるのもよいでしょう。
増悪・緩解の見通しは実態を反映していますか?
後遺障害診断書の「増悪・緩解の見通し」欄は、今後の症状が悪化(増悪)したり、和らいだり(緩解)する可能性について、医師が医学的に評価する項目です。たった数行の記載ですが、後遺障害等級の認定に直結する重要な内容です。
たとえば、症状が長期間続いているにもかかわらず、「今後改善する可能性あり」といった表現がされていると、審査で「完治する見込みがある=後遺障害ではない」と判断されてしまうことがあります。
症状の経過や生活への影響と照らし合わせて、診断書の見通しが実態に合っているかを確認しましょう。
増悪・緩解の見通し欄の確認ポイント
次のようなポイントに注目して、診断書に記載されている医師の見通しが実態と整合しているかを確認しましょう。
-
「症状固定と考える」「緩解は困難である」などの表現で記載されているか?
症状が何か月も変わらず続いているのであれば、「症状固定と考える」「緩解は困難である」といった表現が記載されていることが大切です。こうした記載があることで、「後遺障害が残っている」と認められやすくなります。
-
「緩解の見込み」「治癒の可能性あり」などが書かれていないか?
将来的に回復する可能性があることを示す表現は、「完治する見込みがある(後遺障害ではない)」と判断されるおそれがあります。医学的に改善の余地が小さいのであれば、その旨がはっきりと示されている必要があります。
-
実際の症状や検査結果と矛盾していないか?
診断書に書かれている見通しが、これまでの治療経過や検査所見と整合していない場合は注意が必要です。
たとえば、画像所見や神経学的検査で異常が確認されているにもかかわらず、「異常なし」「軽快の可能性あり」と書かれている場合には、内容の見直しを医師に依頼すべきでしょう。
-
生活への影響(就労制限、家事困難など)と整合しているか?
日常生活や仕事に明らかな支障があるにもかかわらず、「症状は軽快傾向にある」といった記載がされている場合、認定とのギャップが生じやすくなります。
見通しの記載が、日々の生活の実態と矛盾していないか確認しましょう。
増悪・緩解の見通し欄に不備があった場合の対応
たとえば次のような記載があった場合、見直しを検討する必要があります。
- 実際には治る見込みは極めて低いのに「緩解の見込みあり」と書かれている
- 治っていないのに「軽快した」となっている
こうしたケースでは、症状の経過、検査所見、生活上の制限といった客観的な事実を整理したうえで、医師に診断書の見通し欄の内容について相談しましょう。
このとき、単に「表現を変えてください」と依頼するのではなく、「この3か月、○○の症状が続いており、画像でも改善が見られません」「日常生活では○○に支障が出続けています」などと、事実をもとに認識のすり合わせを行うことが重要です。
もし、どのように伝えればよいか迷う場合は、後遺障害の認定に詳しい弁護士に相談するのも一つの方法です。資料の整理や医師への伝え方についてアドバイスが受けられます。
よくあるご質問
ここでは、後遺障害診断書について、よくあるご相談とその対応方法をご紹介します。
事実と異なる記載がありました。どうすればよいですか?
診断書に明らかな誤りがある場合は、まず冷静に内容を確認し、どの部分にどのような誤記があるのかを整理しましょう。
次に、診療明細書・通院記録・画像所見などの資料をそろえ、診察時に医師へ訂正を依頼します。医師の専門性を尊重しつつ、「なぜ訂正が必要なのか」を事実に基づいて丁寧に伝えることが大切です。
もし伝え方に迷う場合や、修正が難航している場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することで、医師への依頼方法や資料の整理など、具体的なサポートを受けられます。
加筆をお願いしたい事項があります。どうすればよいですか?
「症状が正しく書かれていない」「検査が漏れている」など、必要な内容が漏れていると感じた場合も、まずは該当箇所を特定し、追加してほしい情報を整理しましょう。
その際は、なぜその情報が必要なのかを医師にわかりやすく伝えることがポイントです。
診療メモや自分の記録、リハビリ内容などを見せながら、症状の継続性や生活への支障を具体的に説明すると、医師も意図を理解しやすくなります。後遺障害の審査のために必要な検査であることを端的に伝えるという方法もあります。
対応に不安があるときは、弁護士に相談し、依頼文の作成や伝え方について助言を受けるとスムーズです。
まとめ:後遺障害診断書で悩んだら弁護士に相談
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定を左右する非常に重要な書類です。記載内容に誤りや不足があると、正当な評価が受けられないおそれがあります。
診断書の内容に不安を感じたときや、「どのように医師に伝えればいいかわからない」と迷ったときは、交通事故の実務に詳しい弁護士に早めに相談することをおすすめします。
診断書の内容確認や、修正が必要な場合の伝え方、必要な資料の整理まで、実際の手続きに即したアドバイスや対応をしてもらえるため、心強い支えとなるはずです。
後遺障害認定は基本的に書類審査のみで行われるため、「内容が正しく伝わるかどうか」が結果を大きく左右します。
ひとりで悩まず、必要なサポートを受けながら、適切な認定と正当な補償を目指して進めていきましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博