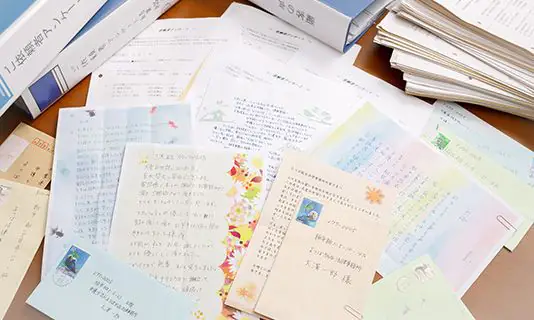後遺障害診断書について弁護士へ相談すべき5つの理由
最終更新日:2025年11月4日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博
- Q後遺障害診断書について弁護士に相談すべき理由は何ですか?
-
損害賠償額や等級認定に大きな影響を与える重要書類であり、適切に作成するためには弁護士のサポートが有効だからです。
医師は治療の専門家であっても、必ずしも後遺障害の認定基準には詳しくない場合があり、診断名や症状の記載漏れ、必要な検査の未実施などにより、適正な後遺障害等級が認められないケースもあります。
弁護士に相談することで、「医師への症状の伝え方」や「受けるべき検査」などについて具体的なアドバイスが受けられ、すでに後遺障害診断書が完成している場合でも、不備の確認や修正依頼、異議申立ての対応が可能です。
実際の後遺障害診断書をご覧いただくとわかるように、傷病名欄や自覚症状欄など注意すべきポイントは多いです。こうした細部を整えるためにも、早い段階から弁護士に相談しておくことが、正当な等級認定と適切な賠償を得るための近道となります。

目次
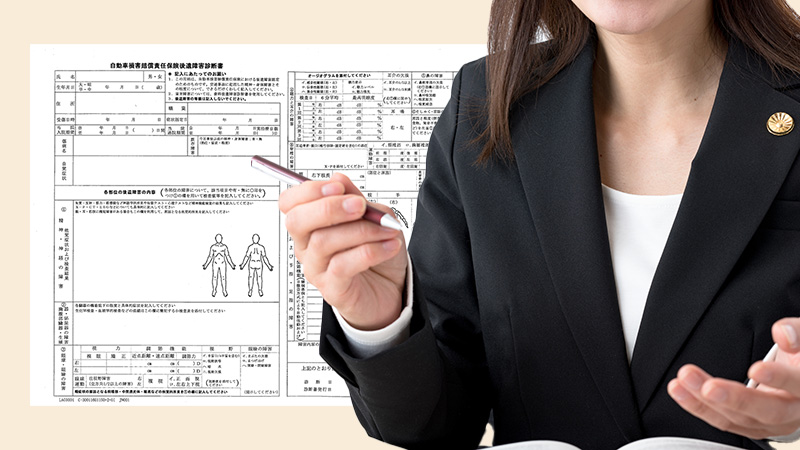
後遺障害診断書とは
後遺障害診断書とは、交通事故によるけがの症状が治療後も残った場合に、医師がその状態を医学的に記録する書類です。症状固定後の身体の状況を客観的に示すものであり、後遺障害等級の認定において最も重要な資料となります。
後遺障害診断書が重視される最大の理由は、後遺障害等級の審査が原則として書面のみで行われる点にあります。傷跡の障害など一部の例外を除き、審査機関が被害者本人の身体を直接確認することはありません。したがって、後遺障害診断書の記載内容が、そのまま認定の可否や等級に直結するのです。
後遺障害診断書を作成できるのは、被害者の治療や診察を担当した医師に限られます。医師は医学の専門家として、けがの部位や治療経過、画像検査の所見、神経学的検査の所見などを記録しますが、必ずしも後遺障害等級の認定基準や評価方法に精通しているとは限りません。
そのため、実際に後遺症が残っているにもかかわらず、後遺障害診断書の記載内容によっては適正な等級が認められないケースもあります。
もちろん、事実と異なる記載は許されませんが、同じ症状でも「どのように表現するか」「どの検査結果を示すか」によって評価が変わることは少なくありません。
医学的な事実を正確に伝えると同時に、認定基準に即した記載を意識することが、被害者にとって極めて重要です。
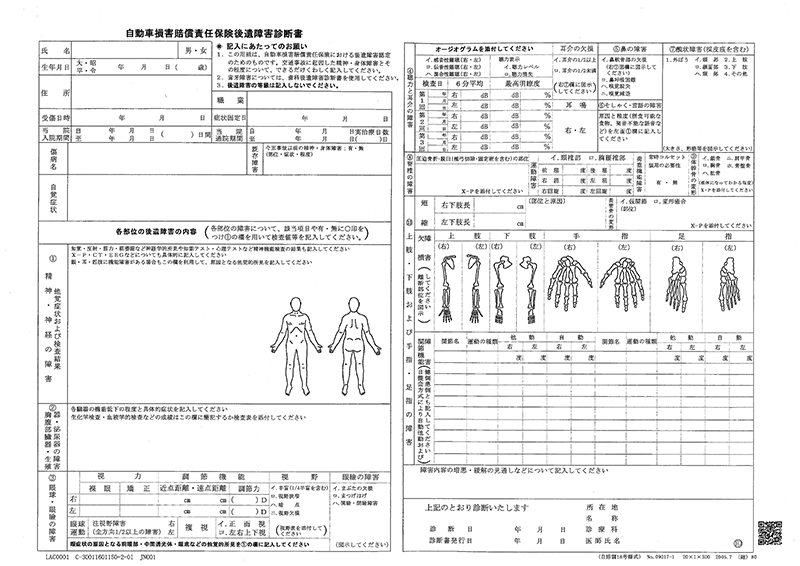
後遺障害診断書の作成の流れ
後遺障害診断書の作成は、次の手順で進められます。
-
症状固定の判断
まずは主治医が「治療を続けてもこれ以上の改善は見込めない」と判断した時点で、症状固定とされます。症状固定前に後遺障害診断書を作ることはできません。
-
書式の入手
後遺障害診断書には、自賠責保険の申請専用の書式を使用します。保険会社から取り寄せるのが一般的です。通常の診断書とは異なるため、誤って別の書式を使わないよう注意が必要です。
-
主治医に作成を依頼
専用書式を持参し、主治医に作成を依頼します。この際、多くの医師は再度診察や検査を行い、症状固定日・診断名・自覚症状・受傷部位・画像所見・各種検査所見・将来の見通しなどを記載します。
なお、複数の部位を負傷している場合には、それぞれの診療科で個別に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。たとえば、骨折は整形外科、歯の損傷は歯科などです。
-
診断書の受領と費用
後遺障害診断書の作成には、数日から2週間程度かかるのが一般的です。費用は1通あたり5000円〜1万円程度で、追加の検査が行われた場合は別途検査費用が発生することもあります。
これらの費用は一時的に自己負担となりますが、後遺障害等級が認定されれば保険金から補償されるケースが多いです。
-
内容の確認と提出
完成した後遺障害診断書を受け取ったら、内容を確認しましょう。治療期間や症状固定日、症状の部位、今後の見通しなどに誤りがあると、等級認定に不利となるおそれがあります。
そのうえで、事前認定の場合には加害者の保険会社に、被害者請求の場合には自賠責保険に提出します。


弁護士に相談すべき理由
ここでは、後遺障害診断書の作成にあたり、弁護士に相談すべき主な理由を5つに分けてご紹介します。
診断書を医師にお願いする前にアドバイスをもらえる
後遺障害診断書を医師に依頼する前に弁護士に相談することで、法的な観点からどのような検査を受けておくべきか、また症状をどのように記録に残しておくべきかについて、具体的なアドバイスが得られます。
後遺障害等級の審査では、通院頻度や治療期間に加えて、医学的な根拠となる検査結果が重要視されます。たとえば、脊髄症状や神経根症状がある場合にはMRI、四肢の神経損傷がある場合は神経伝導速度検査や針筋電図検査、可動域制限がある場合には角度計を使った計測など、具体的な検査データの有無が等級認定に大きく影響することがあります。
弁護士は、症状や生活への影響、治療経過を総合的に踏まえ、次のようなアドバイスができます。
- 適切な通院のペース
- 症状固定のタイミング
- 必要な検査の種類と時期
- 医師への症状の伝え方
後遺障害診断書の内容をチェックしてもらえる
後遺障害診断書が完成したあとでも、弁護士に相談すれば内容の不備や不足を専門的に確認してもらえます。
医師は治療の専門家ではありますが、後遺障害の認定基準には詳しくないケースも多いです。そのため、次のような問題が発生することがあります。
- 症状の一部が記載されていない
- 用語の使い方が基準とずれている
- 審査上必要な所見や検査結果が含まれていない
弁護士はこれらの点をチェックし、もし修正が必要な箇所があれば、ご本人から医師へ的確に追記や修正の依頼ができるよう、具体的な説明資料を作成するなどしてサポートします。
後遺障害診断書は専門的な文書であり、被害者自身では気づきにくい細かなミスや不足が、認定結果に大きく影響することもあります。このような見落としを防げる点は、弁護士に依頼する大きなメリットといえるでしょう。
適切な後遺障害等級を得やすい
弁護士のサポートがあれば、本来認定されるべき適正な後遺障害等級を獲得できる可能性が高まります。
後遺障害等級は1級から14級まで細かく分類されており、同じ症状であっても、診断書の記載の内容や表現の仕方によって認定結果が大きく変わることがあります。
弁護士は、これまでの認定実績や審査基準をふまえ、次のような後遺障害申請に向けた準備をします。
- 症状や認定可能性のある等級に応じた必要な検査・所見を洗い出す
- 医師に記載を依頼するための準備や伝達をサポートする
- 記載内容が認定基準に沿っているかを事前に確認する
こうした対応により、不適切な等級認定や、本来受けられるべき認定を逃すリスクを最小限に抑えることが可能です。
もらえる賠償金が増額しやすい
後遺障害等級が認められると、慰謝料や逸失利益などの将来にわたる損害賠償の金額が決まります。この賠償額は、「どの基準で算定されるか」によって、大きく差が生じます。
保険会社は一般的に、「自賠責基準」や「任意保険基準」といった低めの基準をもとに算出した金額を提示してきます。一方、弁護士が代理人として交渉する場合は、裁判例に基づく「裁判所の基準(弁護士基準)」を用いて、より高額な賠償を主張することが可能です。
たとえば、後遺障害14級の場合の慰謝料は、自賠責基準では約32万円、裁判所基準では約110万円が目安となります。このように、どの基準で交渉するかによって、受け取れる金額に大きな差が生じるのです。
適正な等級が認定されるだけでなく、その後の賠償交渉を弁護士が行うことで、最終的に受け取れる金額が大幅に増える可能性があります。この点も、弁護士に依頼する大きなメリットのひとつです。
複雑な手続きを任せることができる
後遺障害等級の申請には、さまざまな準備が必要です。
医療記録や検査結果の収集、書類の整備、保険会社とのやりとりなどを、治療中の本人が行うのは大きな負担となります。
弁護士に依頼すれば、こうした書類の整理・収集・提出はもちろん、保険会社との連絡・交渉、申請後の進捗管理、結果に不服がある場合の異議申立てまでを一括して任せることが可能です。
被害者は、手続きを気にすることなく、治療や生活の再建に専念できるため、精神的な安心にもつながります。
よくあるご質問
ここでは、後遺障害診断書に関するご相談で、実際に多く寄せられる質問とその回答をご紹介します。
作成前と作成後のいずれで弁護士に相談するのがよいですか?
可能であれば、後遺障害診断書を作成する前に相談するのが理想的です。
後遺障害診断書は、一度完成して提出してしまうと、あとから修正を依頼することが難しく、不備や漏れがそのまま等級認定に影響してしまうためです。
弁護士に相談すれば、これまでの治療記録などを確認し、傷病名の漏れや記載内容の不備がないよう整理した上で、主治医に依頼することが可能です。
また、自覚症状の欄には「被害者自身の訴え」を反映してもらう必要があるため、症状をどう伝えるかについても事前にアドバイスが受けられます。
さらに、認定される可能性のある等級を洗い出したうえで、それぞれに必要な検査を主治医に依頼できるよう準備してくれるため、適正な等級を得られる可能性が高まります。
とはいえ、すでに後遺障害診断書が完成している場合でも、弁護士に相談する意義は十分にあります。後遺障害診断書の内容が不十分だった場合、なぜ補記が必要かを丁寧に説明し、追記を依頼することも可能です。
特にもめていませんが、それでも弁護士に相談したほうがよいですか?
「問題が起きていない今だからこそ」弁護士に相談する価値があります。
「保険会社と普通にやり取りできているし、特にもめていないから大丈夫」と考える方は少なくありません。しかし、弁護士に相談するメリットは、トラブル発生後に対応してもらうことだけではありません。
むしろ大切なのは、将来の不利益を未然に防ぐことです。
後遺障害診断書の記載内容は、そのまま慰謝料や逸失利益などの賠償額に直結します。いまは順調に見えても、診断書の記載が不十分だったために低い等級しか認定されず、その後の示談交渉で不利になるというケースは少なくありません。
弁護士に相談すれば、後遺障害診断書の内容や申請手続きの方向性について事前にチェック・助言を受けることができ、認定や賠償に備えた準備を整えることが可能です。
結果として、適正な等級認定を受けられる可能性が高まり、最終的に受け取れる賠償額もより妥当な水準に近づくことになります。
大きなトラブルが起きていない今の段階こそが、安心して相談できるタイミングと言えるでしょう。
まとめ:後遺障害診断書は弁護士に相談
後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定を受けるうえで最も重要な書類です。
その一方で、記載が不十分なまま提出されてしまうケースは少なくありません。結果として、本来受けられるはずの等級や賠償を逃してしまうリスクもあります。
こうした事態を防ぐためには、後遺障害診断書の作成前から弁護士に相談し、準備段階から適切なサポートを受けることが重要です。後遺障害診断書の作成支援に加え、申請後の異議申立てや、賠償交渉への対応まで任せられるため、被害者にとって大きな安心につながります。
交通事故で後遺症が残ってしまった方にとって、後遺障害診断書は今後の生活を左右する極めて大切な書類です。不安を感じたら早めに弁護士に相談し、適切な等級認定と正当な賠償を受けられるよう準備を進めていきましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博