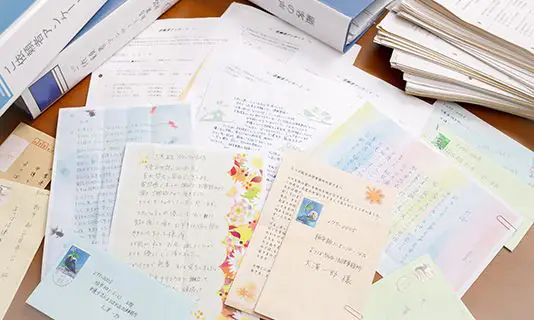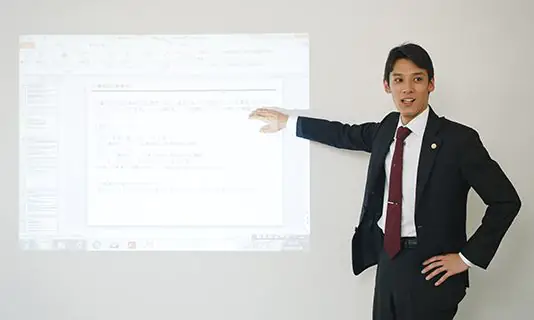自賠責基準と裁判基準で慰謝料が自賠責基準の方が多い場合
最終更新日:2025年02月07日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 坂口 香澄
- Q自賠責基準と裁判基準で自賠責基準の方が慰謝料が多い場合はどのような場合ですか?
-
次のような場合です。
- 被害者の過失が大きい場合
- 労災や健康保険を使って長期の通院をした場合
- 怪我が軽傷で通院期間が2週間以下の場合
ただし、慰謝料以外の損害項目も合算すると、裁判基準が有利となることが多いです。

1. 自賠責基準と裁判基準とは
自賠責基準とは自賠責保険の基準です。裁判基準とは裁判での基準です。
自賠責基準の慰謝料は、裁判基準の慰謝料よりも低いことが多いです。自賠責保険は被害者が最低限度を保証を受けるようにするための強制保険だからです。
そのため、交通事故の被害にあったときは、自賠責保険の賠償額は確保しながら、きちんと適正な慰謝料額を受け取ることが大切です。
そうはいっても、裁判基準よりも自賠責基準が有利になるケースはないのでしょうか?この記事では、自賠責基準が有利になるケースを解説します。2. 自賠責基準と裁判基準の慰謝料の計算方法
最初に、自賠責基準と裁判基準の慰謝料の計算方法を簡単に紹介します。
自賠責基準の慰謝料の計算方法
自賠責保険での慰謝料の計算方法は日額4,300円×対象日数です。対象日数は①通院回数の2倍と②総治療期間のうち少ない金額です。
たとえば、30日間の治療期間で10回通院した場合で考えてみましょう。
- 通院回数の2倍は20日です。
- 総治療期間は30日です。
少ないのは20日です。
そのため、自賠責基準の慰謝料は86,000円です。
【計算式】4,300円×20日=86,000円
また、たとえば、30日間の治療期間で20回通院した場合で考えてみましょう。
- 通院回数の2倍は40日です。
- 総治療期間は30日です。
少ないのは30日です。
そのため、自賠責基準の慰謝料は129,000円です。
【計算式】4,300円×30日=129,000円
自賠責保険は上限に注意
自賠責基準は日額4,300円で計算します。そのため、対象日数が増えるほど比例して慰謝料が増えます。
ただし、自賠責保険には120万円の上限があります。120万円の上限には慰謝料以外の治療費や休業損害も含みます。
たとえば、6か月間(180日間)に90回通院し、治療費が90万円とします。自賠責保険の上限は120万円なので、慰謝料は最大でも30万円です。
【計算式】自賠責保険の上限120万円-治療費90万円=慰謝料30万円
自賠責保険は上限がありますので注意しましょう。
裁判基準の慰謝料の計算方法
裁判基準の慰謝料は、入院や通院の期間で計算します。通院の回数はあまり慰謝料に影響しません。
たとえば、骨折等の大きな怪我で1か月通院したときの慰謝料の目安は28万円です。むちうちや打撲などの怪我で1か月通院したときの慰謝料の目安は19万円です。
2か月以降も、期間が長くなるにつれて慰謝料額の目安は上がります。ただし、上がり幅はだんだんなだらかになります。
| 通院期間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慰謝料の目安 | 19万円 | 36万円 | 53万円 | 67万円 | 79万円 | 89万円 | 97万円 | 103万円 | 109万円 | 113万円 |
なお、裁判基準は上限はありません。慰謝料以外の損害がいくら発生していようと、慰謝料として支払われるべき金額が支払われます。
3. 自賠責基準の方が賠償額が多くなる場合
多くのケースで自賠責基準より裁判基準の慰謝料が大きくなるのはお分かりいただけたでしょうか。では、どんなときも裁判基準の方が有利なのでしょうか?実はそうとも限りません。
自賠責基準が裁判基準より賠償額が高くなるケースを3つご紹介します。
① 被害者の過失も大きい場合
単純な慰謝料額という意味では、裁判基準が大きくなることがほとんどです。しかし、過失相殺後の実際に受領できる額という意味では、自賠責基準が高くなることがあります。
裁判を含む通常の賠償の場面では、被害者に少しでも過失があれば過失相殺 されます。しかし、自賠責保険は、被害者の過失がよほど大きくない限り、過失相殺しません。しかも、過失相殺するとしても最大で20%だけです。
| 被害者の過失割合 | 減額割合 |
|---|---|
| 70%未満 | 減額なし |
| 70%以上100%未満 | 20%の過失相殺 |
たとえば、むちうちの怪我で30日間治療し、20日間通院したケースで考えてみましょう。
慰謝料額は次の通りです。
- 裁判基準 19万円
- 自賠責基準 12万9,000円
ですが、仮に被害者にも50%の過失があった場合、裁判基準の慰謝料は50%の過失相殺の対象になります。
一方、自賠責基準は過失相殺されません。そのため、自賠責基準の賠償額の方が裁判基準よりも高くなります。 - 裁判基準 9万5000円(19万円×50%)
- 自賠責基準 12万9000円
しかし、仮に被害者に50%の過失があったとします。裁判基準の慰謝料は50%の過失相殺の対象になります。一方、自賠責基準は過失相殺されません。そのため、自賠責基準が裁判基準より高くなります。 - 裁判基準 9万5,000円(19万円×50%)
- 自賠責基準 12万9,000円
② 労災や健康保険を使って長期の通院をした場合
自賠責基準での慰謝料額が大きくならない理由の1つは、自賠責保険は治療費等もすべて含めて上限が120万円であることです。
しかし、自賠責保険は慰謝料など被害者本人が受け取るものを優先して支払うルールがあります。健康保険や労災保険で支払われたお金は後回しになります。
たとえば、10か月間(300日間)に150回以上通院し、治療費が90万円かかった場合で考えてみましょう。
自賠責基準の慰謝料は、計算上4,300円×300日=129万円です。120万円を超えていますので120万円が実際の支払額です。
しかし、治療費90万円を加害者の保険会社が支払ったときは、自賠責保険が支払う慰謝料は最大30万円です。自賠責保険は上限120万円だからです。
ただし、治療費90万円を負担したのが労災保険だったとしましょう。労災保険からの治療費の求償請求よりも、被害者本人の慰謝料請求を自賠責保険は優先します。
そのため、まず被害者に慰謝料120万円が支払われます。自賠責保険の上限の支払となりますので、労災保険からの治療費の求償請求を自賠責保険に行うことはできません。
他方、裁判基準の10カ月の通院慰謝料は113万円です。
- 自賠責基準 120万円
- 裁判基準 113万円
結果として、裁判基準より自賠責基準が高くなります。
③ 怪我が軽傷で通院期間が2週間以下の場合
怪我がむち打ちや打撲などで通院期間が2週間以下のときで、かつ最終通院日に「治癒」ではない場合、裁判基準より自賠責基準の慰謝料が高くなる可能性があります。
最終通院時の診断が「治癒」でないときは、最終通院日までの期間に7日を加えた期間を治療期間と考えるという特別ルール(プラス7日ルール)が自賠責保険にはあります。
「治癒」でないとは「治癒見込み」「転医」「中止(治癒していないけど何らかの理由で治療は終了)」などの場合です。
つまり、自賠責基準では、「治癒」以外で治療が終了すると、「治癒」の場合に比べて7日間分、つまり最大で3万100円(4,300円×7日)慰謝料が増える可能性があります。
たとえば、実際の通院期間は2週間(14日間)でも、「中止」で治療が終了している事案で考えてみましょう。
自賠責基準で慰謝料を計算するときの治療期間は14日+7日で21日間とみなします。14日間で11回以上通院していたとすると、自賠責基準での対象日数は21日です。他方、裁判基準は実際の通院期間である14日間で計算します。
その結果、慰謝料の目安は次の通りです。自賠責基準が高いです。
- 自賠責基準 9万0300円
- 裁判基準 8万8667円
ただ、プラス7日ルールで増えるのは最大でも3万100円だけです。実際の治療期間が2週間を超えたり、そもそも怪我が骨折などの重症であったりするときは、プラス7日ルールを適用しても自賠責基準より裁判基準が高くなります。
4. まとめ:自賠責基準と裁判基準で慰謝料が自賠責基準の方が多い場合
自賠責基準と裁判基準で自賠責基準の方が慰謝料が多いのは次のような場合です。
- 被害者の過失が大きい場合
- 労災や健康保険を使って長期の通院をした場合
- 怪我が軽傷で通院期間が2週間以下の場合

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 坂口 香澄