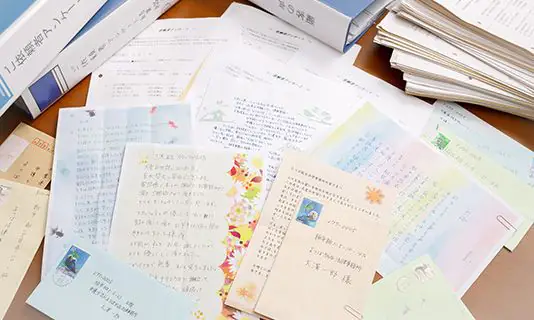交通事故における加害者の責任
最終更新日:2025年07月30日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博
- Q交通事故における加害者の責任はどのようなものですか?
-
交通事故の加害者は、民事・刑事・行政の3つの責任を負います。
治療費や慰謝料などを支払う「損害賠償責任(民事)」、罰金や懲役といった「刑事責任」、そして免許停止や取消しといった「行政処分」です。
これらの責任はそれぞれ別個に追及されるため、たとえば示談が成立しても、刑罰や行政処分が免除されるとは限りません。

目次

交通事故の加害者が負う3つの責任
加害者は、民事・刑事・行政の3つのルートで責任を問われます。
交通事故を起こした加害者には、次の3つの責任がそれぞれ発生します。
-
民事上の責任(損害賠償)
交通事故によって生じた被害について、加害者は被害者に金銭的な賠償を行う義務があります。
たとえば、治療費、通院交通費、休業損害、後遺障害に対する逸失利益、さらには慰謝料などが含まれます。
これは、加害者が自動車保険に加入している場合でも、加害者本人の責任として発生するものです。保険会社が賠償を立て替える場合でも、加害者の責任がなくなるわけではありません。
-
刑事上の責任(犯罪としての処罰)
加害者の運転に刑事手続きについての法令違反があると判断された場合、刑罰の対象になります。
代表的な罪名としては、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などがあり、罰金刑や拘禁刑が科される可能性があります。
なお、被害者との間で示談が成立した場合でも、事件が重大であると判断されれば、起訴され刑事裁判に進むこともあります。
-
行政上の責任(免許に関する処分)
交通事故を起こすと、運転免許の点数が加算され、一定の累積点数を超えると免許停止や取消しの処分が科されます。
処分の内容は事故の種類や加害者の過失の程度、被害の大きさなどによって異なります。
また、刑事処分が決定する前であっても、警察の判断で仮の行政処分が行われることもあります。このように、加害者の責任は一面的なものではなく、複数の制度によって重層的に問われることが特徴です。
被害者としては、どの制度がどのような結果に結びつくのかを知ることで、より的確な対応が可能になります。
民事上の責任
交通事故で被害者に生じた損害について、加害者は金銭で償う必要があります。
交通事故の加害者には、被害者が受けた損害に対して金銭的な補償を行う責任があります。
これは民法に基づく「不法行為による損害賠償責任」などとして問われるもので、事故の過失が加害者に認められる限り、損害額の大小にかかわらず発生します。
実際に請求できる内容は多岐にわたり、治療費や通院交通費、けがによる休業損害、後遺障害が残った場合の逸失利益、精神的苦痛に対する慰謝料、さらには壊れた車や持ち物などの物損までもが対象です。これらは事故の被害状況や後遺症の有無、収入状況などによって異なりますが、数十万円から数千万円以上にのぼることもあります。
なお、損害賠償の金額は「どの基準で計算するか」によっても変わります。たとえば、自賠責保険では最低限の補償しか受けられず、任意保険会社が提示する基準も、被害者にとって必ずしも妥当とは限りません。一方で、裁判所や弁護士が用いる「裁判所の基準」は、被害者にとって最も高額になりやすい基準とされています。
そのため、被害者が適正な賠償を受けるには、加害者側の保険会社の言い分をうのみにせず、早い段階で弁護士に相談し、裁判基準での請求を検討することが重要です。加害者の責任をしっかりと追及し、正当な補償を受けるための第一歩といえるでしょう。
刑事上の責任
交通事故によって人を死傷させたり、物を壊した場合、加害者は刑法上の罪に問われる可能性があります。
これは民事上の賠償責任や行政処分とは別に、国家が加害者の行為に対して科す「刑罰」です。仮に示談が成立していたとしても、事故の内容や悪質性によっては、検察が起訴し刑事裁判に進むこともあります。
加害者が問われる罪は、主に次の3つです。
過失運転致死傷罪
もっとも一般的に適用されるのが「過失運転致死傷罪」です。これは、自動車運転中に注意義務を怠り、その結果として人を死傷させた場合に成立する犯罪です。刑法ではなく、「自動車運転処罰法」に定められており、加害者が事故の発生を予測・回避できたにもかかわらず、それを怠った場合に適用されます。
たとえば、脇見運転や前方不注視、信号無視、スピードの出し過ぎ、わき道からの急な飛び出しへの不注意などが典型です。特に、日常的な不注意によって起きる事故(たとえばスマートフォンの操作や居眠り運転)はこの罪の対象になります。
罰則は比較的軽く見られがちですが、7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金刑が定められており、被害者にとっては決して軽視できない法的責任です。
加害者が真摯に反省しているか、被害者との示談が成立しているかなどの事情によって、起訴・不起訴や処罰内容が左右されることもあります。
危険運転致死傷罪
加害者の運転態様が、単なる過失ではなく極めて悪質・危険である場合には、「危険運転致死傷罪」が適用されます。この罪は、死亡事故や重傷事故が発生した際に、より重い処罰を科すことを目的として制定されたもので、社会的な注目も高い罪名の一つです。
対象となる行為には、次のような運転が含まれます。
- アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行(酒酔い運転等)
- 無免許(運転技能を有しない状況等)での運転
- 制限速度を大きく超えた走行(著しい速度超過)
- 急な車線変更や蛇行運転、赤信号無視など、故意に危険な運転を継続した場合
これらは、加害者自身が「事故を起こすかもしれない」という認識を持ちながら、あえて危険な運転をしたと評価される行為です。
罰則は非常に重く、傷害事故であっても15年以下の拘禁刑、死亡事故の場合は1年以上20年以下の拘禁刑とされています。悪質なケースでは執行猶予が付かず、実刑判決となる可能性も高いです。
過失建造物損壊罪
交通事故の被害が人ではなく、他人の家やフェンス、電柱、ガードレールなどの「物」に向けられた場合に成立するのが「運転過失建造物損壊罪」です。刑法ではなく道路交通法に規定されたもので、公共設備や他人の所有物を壊したときに適用されます。業務上必要な注意を怠った場合や重大な過失がある場合が対象です。
たとえば、居眠り運転でコンビニに突っ込んでガラスを破壊したり、ハンドル操作のミスで他人のブロック塀を壊したようなケースが対象となります。人身事故と比べると注目度は低いものの、財産に対する侵害行為として刑事責任が問われることもあります。
この罪の法定刑は6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金となっており、比較的軽い処分にとどまる傾向がありますが、同時に損害賠償請求(民事責任)も受ける可能性があるため、実際の負担は小さくありません。
行政上の責任
交通事故の加害者は、民事・刑事の責任とは別に、「行政処分」という形で責任を負うことがあります。これは、公安委員会が運転者に対して行う処分で、運転免許の効力に直接関わるものです。
行政処分の対象となるかどうか、またその内容は、事故の種類や過失の程度、被害の大きさ、違反歴などを踏まえて決定されます。
具体的には、「違反点数制度」に基づいて点数が加算され、一定の累積点数に達した場合には、免許停止や免許取消しといった処分が下されます。
点数制度
点数制度とは、交通違反や事故の内容に応じて加害者に点数を加算し、その累積点数によって免許停止や取消しといった行政処分を科す制度です。被害者にとっては、加害者が事故後にどのような行政的措置を受けるかを知るうえで、重要な情報になります。
この制度の特徴は、事故の内容や加害者の違反歴に応じて処分が自動的に決まることです。
たとえば死亡事故を起こした加害者には、一発で13点以上の点数が加算される可能性があります。軽傷事故でも3点、中等症なら6点、重症であれば9点以上が加算されることもあり、被害の程度が処分に直結する点で合理性があります。
ただし、点数だけで処分内容が一律に決まるわけではなく、加害者の「前歴」も大きく影響します。たとえば過去に免許停止歴がある場合、同じ点数でもより重い処分が科されるのが通常です。
次の表は、前歴がない場合の処分基準の一例です。
| 累積点数 | 行政処分の内容 |
|---|---|
| 6〜8点 | 30日の免許停止 |
| 9〜11点 | 60日の免許停止 |
| 12〜14点 | 90日の免許停止 |
| 15点以上 | 免許取消 (欠格期間1年以上) |
このような行政処分が下されることで、被害者としては「加害者が一定期間、社会的責任を果たした」という納得感につながることもあります。民事で損害賠償が支払われ、刑事で起訴されるだけでなく、社会的なルールの下で運転の自由が制限されるということが、事故後の心の整理に役立つ場面もあるのです。
免許停止
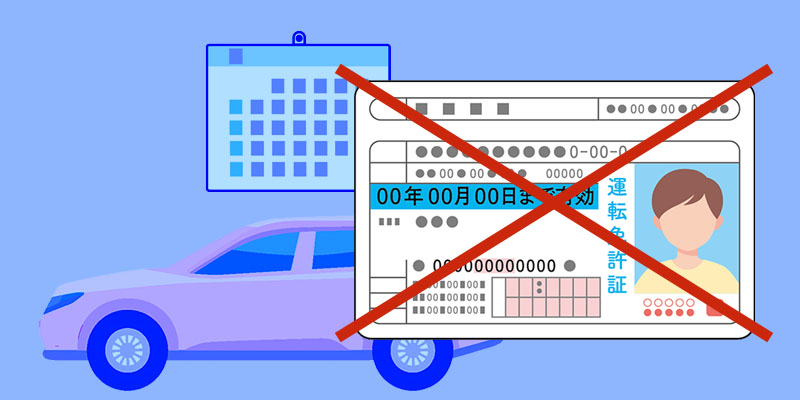
交通事故を起こした加害者が、交通違反や事故によって一定の違反点数に達した場合、公安委員会の判断により「運転免許停止処分」が科されます。これは運転免許の効力を一定期間一時的に停止し、その間、加害者は自動車等を運転することができなくなるという行政上の処分です。処分期間中に運転した場合は無免許運転として刑事罰の対象となります。
免許停止処分が科されるかどうかは、累積した違反点数と、過去の行政処分歴(前歴)によって判断されます。違反点数は事故の内容や過失の程度によって加算され、たとえば軽微な事故でも数点が加算されることがあり、重大事故では一度に10点以上が付されることもあります。
前歴がない場合には、累積点数が6〜8点で30日の停止、9〜11点で60日、12〜14点で90日といった段階的な処分が設けられています。これに対して、過去に免許停止や取消しを受けた前歴がある加害者については、同じ点数でもより重い処分が科される仕組みとなっており、たとえば120日、150日、180日といった長期間の免許停止となることがあります。
処分の対象となった場合、公安委員会から行政処分通知書が交付され、出頭日が指定されます。指定された日に本人が出頭して処分執行を受けると、そこから免許停止期間が開始します。刑事処分が確定していない段階でも行政処分は先行して実施されることが一般的であり、損害賠償請求や示談など民事的な手続きと並行して進められることもあります。
また、免許停止には一定の条件のもとで期間を短縮できる制度も設けられています。それが、公安委員会が実施する「停止処分者講習」です。この講習は1日で受講可能で、受講内容は運転マナーや交通ルールに関する再教育、安全運転の指導などを含みます。講習を修了すると、たとえば30日の処分期間が実質1日または短期間に短縮され、講習翌日から運転が再開できる場合もあります。ただし、講習による短縮措置が認められるかどうかは、違反の性質や処分歴などによって個別に判断され、すべての処分対象者に適用されるわけではありません。
なお、免許停止期間が満了すれば、別途手続を要することなく免許の効力は自動的に回復します。処分の満了後は通常通りの運転が可能となりますが、停止処分歴は公安委員会に記録として残るため、今後新たな違反を犯した際にはより重い処分の対象となる可能性があります。つまり、免許停止は一時的な制裁であると同時に、将来の処分判断にも影響を及ぼす制度上の前提となるものです。
免許取り消し
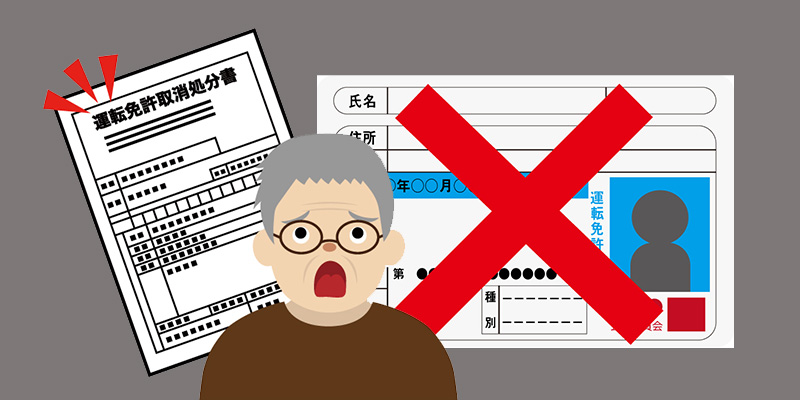
違反の内容や結果が重大である場合、あるいは累積点数が非常に高い場合には、免許そのものを取り上げられる「運転免許取消処分」が科されます。この処分は、免許の効力を一時的に停止する「免許停止」とは異なり、免許そのものが失われる措置です。加害者は、処分が執行された日以降、自動車等の運転が一切できなくなり、運転を再開するには新たに免許を取得し直さなければなりません。
免許取り消しの基準は、加害者に累積された違反点数や過去の行政処分歴(前歴)に基づいて定められています。たとえば、死亡事故や重傷事故、飲酒運転、無免許運転などの重大な違反行為がある場合には、一度の事故でも大量の点数が加算され、取り消しに直結するケースが多く見られます。前歴のない者でも、15点以上の累積点数に達した場合は取消処分の対象となり、前歴がある者の場合はさらに厳しい基準が適用されるため、同じ点数でも取消しに至る可能性が高まります。
免許が取り消されると、「欠格期間」と呼ばれる再取得の制限期間が設定されます。この欠格期間は、違反の内容や前歴の有無などを踏まえて決まり、最短で1年、最長で10年に及ぶ場合があります。
加害者が欠格期間満了後に免許を再取得するには、教習所に通学し、仮免許試験、技能試験、学科試験、適性検査といった各種の試験をすべて一から受験する必要があります。これには相応の費用と時間が必要であり、再取得までの道のりは決して容易ではありません。
また、免許取消の記録は公安委員会に残るため、再取得後も一定期間は保険料が割増になる、職業運転手としての就業に支障が出るなど、社会生活における間接的な不利益も生じます。
加害者に適正な処罰を受けさせる方法
加害者に正当な処罰を受けさせるには、被害者自身の行動と働きかけが重要な鍵になります。
交通事故の処理は、捜査機関や裁判所などの公的手続きにゆだねられる面が大きい一方で、被害者の対応によって結果が大きく左右される場面もあります。
たとえば、検察官が不起訴処分を決めようとしていた事件でも、被害者が強い処罰感情を表明したことで起訴に切り替えられることもあります。
ここでは、被害者としてできる主な4つの対応方法について、それぞれ概要と重要なポイントを解説します。
刑事手続きで意見を述べる
加害者の処罰については、警察や検察の判断に任せきりにするのではなく、被害者自身の考えや処罰に対する意見を検察官や裁判官に適切に伝えることが重要です。処分内容の判断にあたり、被害者の声が参考にされることもあるからです。
意見の伝達方法としては、被害者の供述調書を作成する際に、処罰に対する意見を聞かれることが通常ですので、しっかりと自分の考えを述べましょう。厳重な処罰を望むなら、しっかりその旨を書面に残しておかなければなりません。さらに詳細に意見を述べたい場合には、検察庁に対し「被害者意見陳述書」や「意見書」といった書面の提出が一般的です。これらの文書を通じて、「加害者が反省していない」「謝罪がなく誠意を感じない」「再犯の可能性が高い」といった具体的な事情や心情を伝えることができます。
また、被害者が刑事裁判に出廷して心情に関する意見を述べる「被害者意見陳述制度」や事実関係や法律の適用、量刑に関する意見を述べる「被害者参加制度」を利用することも可能です。
このような被害者の意見は、検察官の起訴・不起訴の判断や、裁判官による量刑判断に影響を与えることがあり、略式命令や不起訴処分ではなく、正式起訴に至ることもあります。
ただし、意見の伝え方によっては誤解を生んだり、かえって状況が複雑になって逆効果となることもあるため、弁護士に相談のうえ、法的に整理された形で提出することが望ましいでしょう。感情を正しく伝えるとともに、法的手続きの中で適切に扱ってもらうためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
慎重に示談する
示談交渉は、被害者と加害者の間で損害賠償や謝罪の方法などについて合意を交わす手続きです。
特に交通事故の場合、示談が成立すると、加害者の刑事処分が軽くなる、あるいは不起訴になる可能性があります。
示談書には「被害届を取り下げる」「処罰を求めない」といった文言が盛り込まれることもあり、加害者側から早期に提示されるケースも少なくありません。
しかし、内容をよく理解しないまま合意してしまうと、結果的に加害者の責任が不当に軽くなるリスクもあります。
示談は金銭的補償を受け取る手段であると同時に、刑事処分にも影響する極めて重要な交渉です。慎重に検討し、必要があれば弁護士に相談したうえで判断しましょう。
被害者参加制度を使う
「被害者参加制度」は、一定の重大事件について、被害者が刑事裁判に参加し、加害者に対して直接意見を述べたり、質問をしたりできる制度です。
交通事故であっても、一定の重大事件で加害者が正式に起訴されたケースではこの制度の利用が可能です。
この制度を使うことで、加害者の供述や態度に対して被害者の考えを裁判官に直接届けることができます。
また、証人尋問や量刑判断の場面で、被害者が自分の気持ちや損害の大きさを説明することも可能です。
被害者が、「ただ傍観するのではなく、自分の言葉で訴えることができて気持ちに区切りがついた」と感じられることがある制度でもあります。
制度の利用には検察の許可が必要であり、手続きや準備もあるため、活用を希望する場合は早めの相談が重要です。
検察審査会への不服申立てをする
加害者が起訴されず「不起訴処分」となった場合でも、それを覆す可能性があるのが「検察審査会」です。
検察審査会は、国民から選ばれた11人の委員で構成されており、検察の不起訴判断が適正であったかどうかを審査する制度です。
審査の結果、「起訴相当」と判断された場合、検察に対して再捜査・再判断が求められます。
それでもなお検察が起訴しなかった場合には、「起訴議決」が出され、自動的に起訴に移行する場合もあります(強制起訴)。
ただし、この手続きは基本的に書面による審査が中心となるため、感情的な訴えに終始するのではなく、不起訴処分に対する具体的な不満や納得できない理由を冷静かつ整理された形で伝えることが大切です。
まとめ:加害者との対応に悩んだら弁護士へ相談
交通事故の加害者には、民事・刑事・行政の3つの責任が発生します。
損害賠償、刑事罰、行政処分など、それぞれの制度は別個に機能しており、加害者に適切な責任を取らせるには、被害者側がその違いを理解し、必要に応じて働きかけることが重要です。
しかし、実際の手続きは複雑で、加害者側の対応や保険会社との交渉、検察や警察とのやりとりなど、精神的にも負担が大きくなります。
さらに、示談や意見陳述といった判断を一歩誤ると、加害者が実質的に軽い処分で終わってしまうおそれもあります。
そのようなときは、一人で抱え込まず、交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。
法的な選択肢を整理し、加害者の責任を正しく追及するための具体的なサポートが受けられます。
よつば総合法律事務所では、交通事故の被害者の立場に立ったサポートを多数行っており、初回相談は無料で受け付けています。
「何から始めたらよいかわからない」「加害者の処分に納得がいかない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博