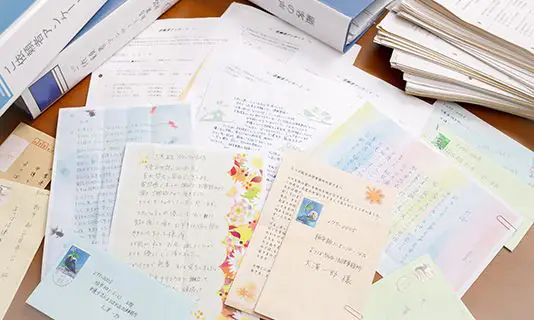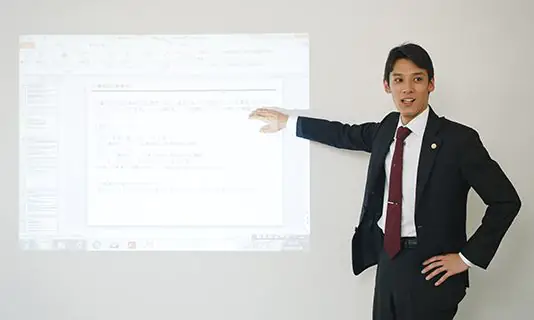逸失利益の労働能力喪失期間
最終更新日:2025年01月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
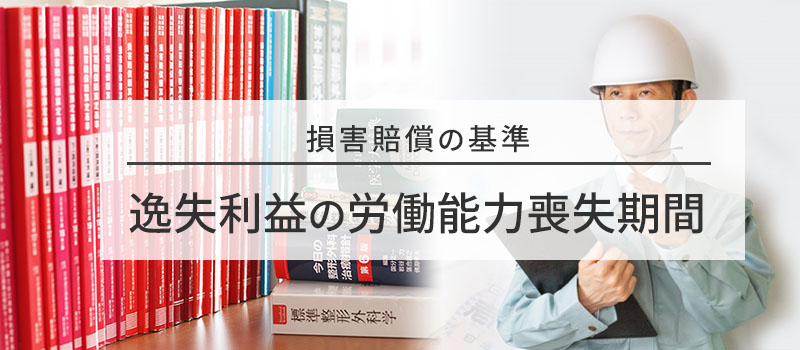
逸失利益の労働能力喪失期間は原則は67歳までです。ただし、例外が多いので間違えないようにしましょう。
この記事では交通事故被害者にむけて、逸失利益の労働能力喪失期間を交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
なお気になることがある場合、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
1. 労働能力喪失期間とは
逸失利益とは事故により発生する将来の収入の減少です。後遺障害が認定されたとき、逸失利益を請求できます。
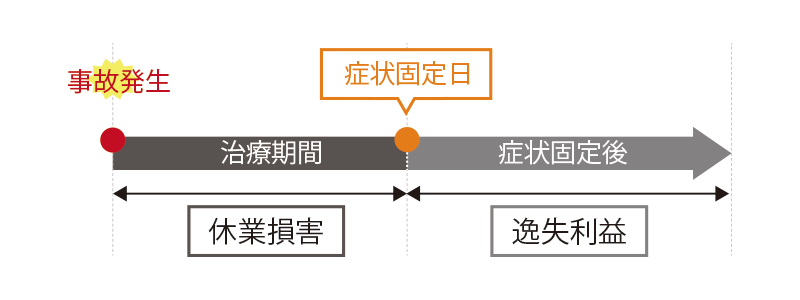
逸失利益の計算は次の通りです。
労働能力喪失期間とは、後遺障害により労働能力が失われる期間です。
労働能力喪失期間は原則67歳までです。ただし、例外が多いので間違えないようにしましょう。
2. 労働能力喪失期間の基準
では自賠責保険や裁判での労働能力喪失期間の基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。
赤い本の基準
- 労働能力喪失期間の始期は症状固定日とする。未就学者の就労の始期については原則18歳とするが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業時とする。
- 労働能力喪失期間終期は、原則として67歳とする。
- 症状固定時の年齢が67歳を超える者については、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とする。
- 症状固定時から67歳までの年齢が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなる者の労働能力喪失期間は、原則として平均余命の2分の1とする。 労働能力喪失期間の終期は、職種、地位、健康状態、能力等により異なる判断がされることがある。
- むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に(労働能力喪失期間を)制限する例が多く見られるが、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきである。
青い本の基準
- 就労可能年数まで、喪失期間を認める裁判例が多い。
- (むちうち損傷)については、後遺障害等級12級該当については10年、後遺障害等級14級該当については5年の労働能力喪失期間を認めた例が多い。ただし、これと異なる長期短期の喪失期間を定めた例もある。
基準の解説
被害者の状況に応じた労働能力喪失期間は次の通りです。
| 被害者の状況 | 労働能力喪失期間 |
|---|---|
| 通常の場合 | 67歳までの年数 |
| 18歳未満の子供 | 49年(18歳から67歳まで) |
| 大学生 | 大学卒常から67歳までの年数 |
| 67歳までの期間が短い場合 | 「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1の年数」のうち長い年数 |
| 67歳を超えている場合 | 平均余命の2分の1の年数 |
| むちうちの場合 | 14級は5年程度 12級は10年程度 |
- 注 個別事案によります。
平均余命は簡易生命表(厚生労働省)を利用することが多いです。
3. よくあるQ&A
- Q「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の労働能力喪失期間は何年ですか?
-
個別事案によります。頚椎捻挫(むちうち)、腰椎捻挫のときは5年が多いです。次のときは5年に限定しないことが多いです。
- 症状固定後相当期間が経過しているのに改善の兆候がないとき
- 脳挫傷など脳に傷害を負ったことに伴う神経症状のとき
- 痛みではなく運動障害や機能障害として実質は評価できるとき
- Q「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の労働能力喪失期間は何年ですか?
-
個別事案によります。頚椎捻挫(むちうち)、腰椎捻挫のときは10年が多いです。次のときは10年に限定しないことが多いです。
- 症状固定後相当期間が経過しているのに改善の兆候がないとき
- 脳挫傷など脳に傷害を負ったことに伴う神経症状のとき
- 痛みではなく運動障害や機能障害として実質は評価できるとき
- Q労働能力喪失期間で計算間違いをしやすいのはどのような場合ですか?
- 50~60代のときです。「67歳までの年数」と「平均余命までの2分の1の年数」のうち長い年数が正しい計算です。67歳までの年数で単純に計算すると計算間違いになることがあります。
4. まとめ:労働能力喪失期間
被害者の状況に応じた労働能力喪失期間は次の通りです。
| 被害者の状況 | 労働能力喪失期間 |
|---|---|
| 通常の場合 | 67歳までの年数 |
| 18歳未満の子供 | 49年(18歳から67歳まで) |
| 大学生 | 大学卒常から67歳までの年数 |
| 67歳までの期間が短い場合 | 「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1の年数」のうち長い年数 |
| 67歳を超えている場合 | 平均余命の2分の1の年数 |
| むちうちの場合 | 14級は5年程度 12級は10年程度 |
- 注 個別事案によります。
平均余命は簡易生命表(厚生労働省)を利用することが多いです。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎