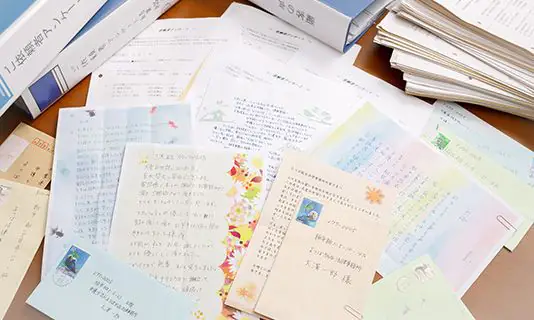交通事故直後の診断書
最終更新日:2025年08月19日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博
- Q交通事故の被害にあった直後です。診断書を作成してもらい提出したほうがよいですか?
-
交通事故でけがをしたときは、診断書を作成してもらい、警察や勤務先、保険会社など必要なところへ提出するのがよいでしょう。
診断書は、事故によるけがを客観的に証明する大切な書類です。必須ではない場合もありますが、客観的な証拠として提出することをおすすめします。
けがが軽いと思っても、あとから症状が長引くケースもあるため、事故直後に病院を受診し、適切な診断書を準備することが大切です。

目次

交通事故直後の診断書のもらい方
交通事故にあった後、診断書をどこでどのように受け取れば良いか、誰に提出するのかは、初めての方には分かりにくいものです。
ここでは、診断書の依頼方法や作成にかかる期間・費用、原本の扱い方について整理してお伝えします。
診断書は医師に依頼
交通事故に関する診断書は、被害者を診察した医師のみが作成できます。整骨院や接骨院には医師がいないため、診断書を作ることはできません。柔道整復師が発行する「施術証明書」はありますが、これは医師が作成する診断書の代わりにはなりません。
医師法では、「実際に診察していない医師が診断書を交付すること」は禁じられています。
そのため、診断書を作成できるのは、実際に診察した医師のみです。
診断書を適切な内容にするためには、診察時に自覚症状を正しく、具体的に伝えることが重要です。とくにむちうちなど外見では分かりにくい症状は、毎回の診察で症状を丁寧に伝えておくことで、後の後遺障害の認定などで不利に扱われるリスクを防止できます。
また、診断書を作成してもらう際は、提出先(警察用・保険会社用)や用途を医師に事前に伝えておくと、必要な情報が漏れなく記載されやすくなります。
作成にかかる期間の目安
診断書の作成にかかる期間は提出先や内容によって異なります。
警察に提出する診断書であれば、けがを証明するだけの比較的簡易な内容のため、即日で発行されることも多いです。
保険会社に提出する診断書は、治療の経過や症状など詳しい内容が必要になるため、即日~1週間ほどかかることがあります。
作成にかかる費用の目安
診断書の作成費用は医療機関によって異なりますが、一般的には3,000円~10,000円程度が相場です。
警察に提出するための診断書の費用は、最終的には相手方の保険会社が負担することが一般的です。ただし、一度被害者が立替払する必要があることもあります。
加害者の任意保険会社に提出する診断書の費用は、最終的には相手方の保険会社が負担することが一般的です。一度被害者が立替しなくてもよいことが多いです。
費用を自己負担したときは、示談で適切に精算してもらうために、領収証は保管しておきましょう。診断書が複数必要になることもあるので、必要に応じて事前に保険会社へ確認しながら進めると安心です。
必要な数の原本を依頼
診断書は原則として原本を提出します。コピーでは受け付けてもらえないことが多いです。警察用、保険会社用など、必要な提出先の分だけ原本を発行してもらうように医療機関に依頼してください。
なお、勤務先に提出する場合はコピーでも認められることがあります。事前に職場へ確認しておくと安心です。
警察へ提出
交通事故でけがをした場合は、医師に診断書を作成してもらい、速やかに警察へ提出することが大切です。診断書を提出することで事故が「人身事故」として扱われる可能性が高くなり、「人身事故の交通事故証明書」が発行されます。
もし診断書を出さずにいると、事故は「物損事故」として処理されてしまいます。物損事故のままだと被害者が損害賠償請求で不利益を受けることもありえます。
さらに、警察に診断書を提出しないと一般的には細かい捜査が行われず、「実況見分調書」などの詳細な記録が残りません。万が一、相手側と事故状況について意見が食い違ったときに有力な証拠がなく、示談交渉で不利になることもありえます。
軽いけがであっても、人身事故扱いにすることは後の適切な損害賠償を受ける大切な備えになります。面倒に思えても、診断書を提出しておくことをおすすめします。
加害者の任意保険会社へ提出
交通事故で適切な損害賠償を受け取るためには、加害者側の任意保険会社が診断書を確認することが重要です。診断書がないままでは、けがの事実や治療の必要性を保険会社が確認できず、治療費や慰謝料などの補償が計算できなかったり、減額される可能性があります。
保険会社用の診断書は書式が決まっており、傷病名、受傷部位、治療開始日と治癒または見込み日などが記載されます。
診断書、診断書(歯科用)などがあります。
なお、加害者が加入している任意保険会社が、被害者に代わって治療費を病院に直接支払っている場合があります。これを一括対応と言います。一括対応の場合、必要な診断書は病院から保険会社へ直接送付されるため、被害者が診断書を用意して提出する必要はほとんどありませんが、同意書の提出を求められることがあります。
保険会社が一括対応しない場合は、被害者が診断書を取得する必要がありますが、診療科や用途によっても診断書の書式が異なります。悩んだら、記載内容やその後の見通しについて弁護士に相談することをおすすめします。
職場へ提出
会社で働いている方が交通事故の被害にあった場合は、まず勤務先に事故にあったことと、治療や休業が必要であることを正確に伝えることが大切です。休業を認めてもらうためには、交通事故で負傷した事実を客観的に示す診断書の提出を求められることが一般的です。
また、通勤中や勤務中に交通事故にあった場合には、労災保険が適用される可能性があります。労災手続きを進める際にも、けがの内容や治療の必要性を証明する書類として診断書が役立ちます。職場に提出する診断書については、会社側がコピーの提出で足りるとしている場合もありますので、事前に担当者へ確認しておくと安心です。
警察へ提出するメリット・デメリット
交通事故でけがをした場合、警察に診断書を提出して人身事故として処理してもらうようお願いするか、物損事故のままにするかは、将来の損害賠償や過失割合の証明に関わることがあります。
一般的には、適切な補償を受けるためには人身事故として扱ってもらう方が有利です。ただし、場合によっては、あえて物損事故のままにすることを選ぶ人もいます。
警察へ提出するメリット
診断書を提出して人身事故として扱われると、警察による実況見分調書が作成されます。
この記録は事故状況を客観的に残す重要な証拠となり、過失割合などで相手と争いが生じたときのトラブルを防げる確率が上がります。
また、人身事故扱いにすることで「人身事故の交通事故証明書」が発行されるため、慰謝料や治療費などの損害賠償を請求する際に必要な手続きをスムーズに進められることが多いです。
さらに、人身事故として届け出ることで、加害者側に刑事責任や行政処分が科される可能性が上がります。被害者としては精神的にも納得しやすくなるというメリットもあります。
警察へ提出するデメリット
警察に診断書を提出し、人身事故として処理されると、実況見分への立会いや事情聴取などで一定の時間と手間がかかる点は、被害者にとっての負担になります。軽傷の場合でもこうした手続きが必要になるため、忙しい方にとっては面倒に感じることがあるでしょう。
さらに、状況によっては人身事故扱いにすることで被害者側にも不利に働く場合があります。たとえば、被害者自身の過失が大きいときや、加害者もけがをしていて責任の所在が複雑なときは、物損事故のままにしたほうが自らの刑事責任や行政処分の点で有利に働くことがあります。
このように、警察への診断書提出には多くのメリットがある一方で、状況次第では物損のままの方が結果的に被害者にとって負担が少ない場合もあります。迷うときは、交通事故に詳しい弁護士に相談して判断するのがおすすめです。
加害者の任意保険会社に提出するメリット・デメリット
交通事故の損害賠償を受けるには、加害者の任意保険会社に対して適切に診断書を提出することが重要です。ただし、提出方法やタイミングを誤ると、補償額に影響する可能性もあります。ここでは、任意保険会社に診断書を提出することのメリットと留意点を整理します。
加害者の任意保険会社に提出するメリット
加害者が任意保険に加入している場合、治療費や慰謝料、休業損害などの賠償は基本的に保険会社が加害者に代わって支払います。保険会社は、提出された診断書をもとにけがの程度や治療の必要性を判断し、補償額を算定します。
適切な内容の診断書が提出されることで、けがの状況や治療にかかった費用が客観的に証明されるため、治療費や慰謝料が不当に減額されるリスクを防ぐことができます。必要に応じて正しい様式で準備しておくことが大切です。
加害者の任意保険会社に提出するデメリット
診断書を保険会社に提出すること自体に大きなデメリットはありませんが、提出が遅れたり内容に不備があったりすると、本来受け取れるはずの補償額が低く見積もられるおそれがあります。
また被害者が訴えている症状と診断書の記載が食い違っていると治療の必要性を疑われたり、事故との関係が不明であるなどと指摘を受けることがあります。また、事故前から同じ症状がある等の記載が診断書にあると、不利に扱われることがあります。
よくあるご質問
交通事故の診断書に関してとくに多いご質問をまとめました。
警察に出す診断書に全治1~2週間のけがと書いてありますが、問題ないですか?
「全治1~2週間」と書かれていても、その期間で必ず治療を終えなければならないわけではないので心配いりません。
診断書に記載されている「全治1週間」「全治2週間」というのは、あくまで医師がけがの回復にかかるおおよその目安を診断書作成時点で示したものです。実際には、むちうち(頚椎捻挫)や軽い打撲などでは当初の見立てよりも痛みやしびれが長引くことも多いです。
無理に通院をやめてしまうと、後から後遺症が残った場合に「なぜもっと通院しなかったのか」などと損害賠償の場面で不利に扱われるおそれがあります。
治療を続ける際は、主治医と相談し、適切な治療計画を立てたうえで、保険会社にも治療継続の必要性をあらかじめ伝えておくと安心です。ただし、必要以上に過剰な通院を続けると、保険会社から治療費の支払いを途中で打ち切られることがあるので注意が必要です。
医師が診断書を作成してくれません。どうすればよいですか?
粘り強く医師や病院に状況を説明しましょう。経験上、医師が診断書の発行を最後まで拒絶する事案は少ないです。
迷ったらまずは弁護士に相談
交通事故にあうと、けがの痛みや不安がある中で、診断書をいつ誰に出すべきか、費用の負担や示談交渉をどう進めるかなど、考えなければならないことがたくさんあります。
体がつらいときに、慣れない手続きを一人で抱えるのはとても大変です。だからこそ、少しでも不安や疑問があるときは、一人で抱え込まずに、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。とくに後遺障害や保険会社とのやり取りで少しでも迷いがあるときは、早めに弁護士へ相談することで思わぬトラブルを防げるケースが多くあります。
よつば総合法律事務所では、交通事故に強い弁護士が、被害者の立場に寄り添ってサポートします。初回相談料は無料です。後遺障害の認定や保険会社との示談交渉も、法律と医学の両面からしっかり支援します。
一人で抱え込まずに、まずは交通事故に詳しい弁護士へ相談し、納得できる解決策を一緒に見つけましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博