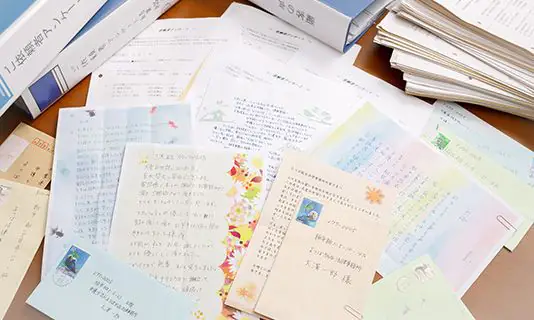労働能力喪失率
最終更新日:2025年08月25日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博
- Q労働能力喪失率とは何ですか?
-
労働能力喪失率とは、交通事故によって後遺障害が残った場合に、事故前と比べて「働く力」がどの程度失われたかをパーセンテージで示したものです。
この労働能力喪失率は、交通事故における損害賠償のうち、特に「逸失利益」の算定に欠かせない重要な要素です。逸失利益とは、事故がなければ将来得られたはずの収入が、後遺障害のために得られなくなった分を補償するものです。
つまり、労働能力喪失率は、後遺障害によって将来の収入がどれだけ減るかを、客観的に数値で評価するための指標だといえます。

目次

労働能力喪失率とは
労働能力喪失率とは、交通事故で後遺障害が残った場合、その影響により仕事がどれほど困難になったのかをパーセンテージで表したものです。
労働能力喪失率は逸失利益の計算に必要
交通事故で後遺障害が残ると、事故前と同じように働くことが難しくなることがあります。たとえば、重い痛みやしびれ、手足の麻痺などにより、仕事の効率が落ちたり、職場での役割をこなせなくなったりした結果、収入が減少してしまうこともあるでしょう。
このように、交通事故による後遺障害がなければ得られたはずの利益を「逸失利益」といいます。
逸失利益を計算するためには、まず「労働能力がどれくらい失われたのか」を数値で示す必要があります。このとき使われるのが、労働能力喪失率です。労働能力喪失率は、「50%」「60%」といった形で表されます。パーセンテージが大きいほど、労働能力の減少が大きいと判断され、その分、補償される金額も増加します。
逸失利益とは
逸失利益とは、交通事故の後遺障害によって得られなくなった利益のことです。被害者は加害者に対して、これを損害賠償として請求することができます。
交通事故の損害賠償には、治療費や入通院慰謝料、休業損害などがありますが、逸失利益はそれらとは異なり「未来の損害」に対する賠償です。
たとえば、事故によって手足が動かしづらくなり、今後フルタイムで働くことが難しい場合、将来的に収入が下がると見込まれます。
その収入減を「逸失利益」として請求することで、被害者が将来得られるはずだった利益が補償されます。
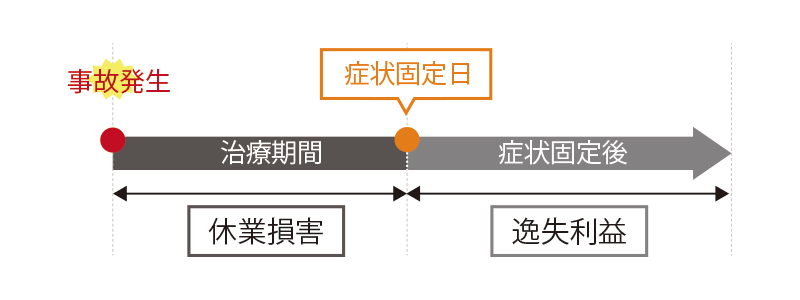
逸失利益の計算方法の具体例
逸失利益は、次の計算式を使って求めます。
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
それぞれの項目について、簡単にご説明します。
基礎収入
基礎収入とは、事故にあわなければ得られていたはずの年収を意味します。会社員であれば事故前の給与収入、自営業者であれば確定申告書の所得金額欄などを参考にするのが一般的です。主婦や学生、パートの方の場合には、別の基準で算定されることもあります。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害のために労働能力がどの程度失われたかをパーセンテージで表すものです。後遺障害等級に応じた目安が存在しますが、職業や症状の内容によって増減することもあります。
ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、「将来得られるはずだった収入を、今一括でもらう場合に、どのくらいの金額になるか」を調整するための係数です。
交通事故の損害賠償は原則として一括払いで支払われますが、実際の収入は本来、毎年分割で受け取るものです。そのため、将来の収入をまとめて先に受け取ると、そのお金を運用することで利益(中間利息)が発生することになります。
被害者に過剰な利益が生じるのを防ぐため、この中間利息をあらかじめ差し引く必要があります。その調整に使われるのがライプニッツ係数です。年齢や就労可能年数に応じて数値が決まっています。
計算方法の具体例
たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。
- 被害者の年齢:40歳(就労可能年数は27年で計算)
- 基礎収入:600万円
- 労働能力喪失率:79%(後遺障害は5級に相当で計算)
- ライプニッツ係数:18.327
この場合、逸失利益の計算は次のようになります。
600万円×0.79×18.327=8686万9980円
なお、実際の金額は、後遺障害等級や年齢、収入状況などによって大きく異なるため、個別の事情をふまえた専門的な判断が必要です。弁護士に相談して、正確な金額を計算してもらうことをおすすめします。
労働能力喪失率のよくあるご質問
ここでは、労働能力喪失率に関するよくあるご質問にお答えします。
後遺障害の等級認定があれば、労働能力喪失率は自動的に決まりますか?
等級認定があれば目安の喪失率は決まりますが、必ずしも「自動的」ではありません。
自賠責保険や裁判では、後遺障害等級ごとに定められた労働能力喪失率を基準としますが、あくまで「目安」です。12級であれば14%、14級であれば5%などの目安です。
たとえば、実際の仕事への影響が大きい場合には、目安を上回る喪失率が認定されることがあります。逆に、後遺障害が仕事にほとんど影響しない場合には、目安より低く認定されることもあります。
労働能力喪失率の交渉のポイントは?
労働能力喪失率を適切に評価してもらうためには、職業や業務内容と後遺障害との関係性を具体的に示すことが重要です。
保険会社は、後遺障害等級に応じた喪失率をそのまま提示してくることが多いですが、これはあくまで「目安」にすぎません。実際には、後遺障害が仕事に与える影響の大きさによって、より高い喪失率が認められるケースもあります。
たとえば、料理人にとっての味覚や嗅覚、職人・技術者にとっての指、アナウンサーや声優にとっての声帯など、職務の遂行に欠かせない部位に障害を負った場合は、後遺障害等級に定められた基準以上の喪失率が相当と判断される可能性があります。
また保険会社は、事故前より収入が上がっていたり、実際の仕事への影響が少ないとして、目安を下回る労働能力喪失率を提示してくるケースも多いです。ひどい場合は労働能力喪失率が0%であると主張してくることもあります。
労働能力喪失率は逸失利益の算定や金額に大きな影響を与えるため、医師の診断書だけでなく、症状固定後の治療状況に関する資料、業務内容や後遺障害の影響を裏付ける資料(業務日報、仕事内容の説明、上司の証言など)をそろえて交渉することが、喪失率の引き上げにつながる重要なポイントです。
減収がない場合、労働能力喪失率はゼロですか?
収入に変化がなくても、労働能力の喪失が認められれば喪失率はゼロにはなりません。
その時点で収入が減少していなくても、将来的に減収が見込まれると認められた場合には、逸失利益が認められることがあります。
大切なのは「労働能力そのものがどれだけ低下したか」です。減収がなかったとしても、労働能力が低下しているのであれば喪失率はゼロとは限りません。
14級の労働能力喪失率は5%の計算になりますか?
原則として、後遺障害等級が14級と認定された場合、労働能力喪失率は5%と評価されます。これは、自賠責保険や裁判実務で用いられる基準に基づくもので、あくまで「標準的な目安」です。
ただし、被害者の職業や実際の業務内容によっては、14級の後遺障害でも仕事に大きな支障をきたすことがあり、そのような場合には、喪失率が5%より高く評価されることもあります。
たとえば、嗅覚障害(嗅覚減退)や味覚障害(味覚減退)により14級の後遺障害が残ったケースで、被害者が料理人・調香師・ソムリエといった専門職に就いていた場合には、後遺障害が職務に与える影響が極めて大きく、裁判や示談交渉で5%以上の喪失率があると判断されることがあります。
このように、14級だからといって一律に5%と処理されるわけではなく、職業や後遺障害の性質に応じた柔軟な判断が求められる場面もあります。
12級の労働能力喪失率は14%の計算になりますか?
原則として、後遺障害等級が12級に該当する場合、労働能力喪失率は14%と評価されます。
ただし、こちらも14級の場合と同様に、被害者の職業や後遺障害の内容・程度によって、実際の労働能力喪失の程度が異なることがあります。
「12級だと14%」というのはあくまでスタートラインであり、被害者個人の事情や仕事への影響を具体的に主張・立証することで、より高い補償を受けられる可能性があります。
まとめ:労働能力喪失率
交通事故で後遺障害が残ると、将来の収入に影響が出る可能性があります。その損失を補償するうえで重要になるのが、「労働能力喪失率」という考え方です。
労働能力喪失率は、事故前と比べてどれだけ働く力が失われたかをパーセンテージで示すもので、逸失利益(将来の収入減)を計算する際の大切な指標になります。
後遺障害等級ごとにおおよその目安はあるものの、実際の仕事の内容や後遺障害が与える影響の程度によっては、それを上回る喪失率が認められるケースもあります。
さらに、現在の収入が維持されている場合でも、将来的に減収が見込まれるのであれば、逸失利益がまったく認められないとは限りません。
働き方も後遺障害の影響も人それぞれです。労働能力喪失率や逸失利益の評価も、画一的ではなく個別の判断が求められます。
少しでも不安があるときは、早めに交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博