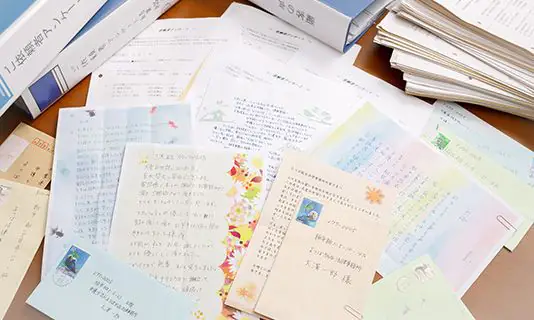自賠責保険|補償内容や請求の流れを解説
最終更新日:2025年06月17日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博
- Q自賠責保険の補償内容や、請求の流れはどのようなものですか?
-
自賠責保険は、交通事故で人がけがをしたり亡くなったりしたときに、最低限の補償を受けられる制度です。けがの場合は最大120万円、後遺障害がある場合は最大4000万円、死亡事故では最大3000万円までが補償されます。
保険金を受け取るには、診断書や事故証明書などの必要書類を保険会社へ提出し、その後、損害の内容について中立的な調査が行われます。調査結果をもとに支払額が決定され、問題がなければ保険金が支払われる流れです。

目次
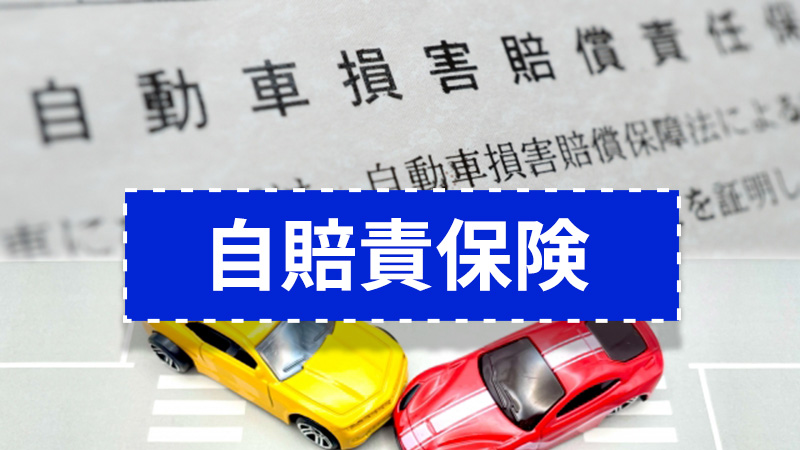
自賠責保険とは
自賠責保険とは、すべての車やバイクに加入が義務づけられている保険で、「強制保険」とも呼ばれています。これは「自動車損害賠償保障法」という法律に基づいて定められており、自動車を使う人は、必ずこの保険に入らなければなりません。
もし自賠責保険に入らずに運転すると、法律違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、運転免許の停止処分を受けることもあるので、非常に重いペナルティがある制度です。
では、なぜこのような保険が義務づけられているのでしょうか?
交通事故が起きたとき、けがをした人は、事故を起こした相手に損害賠償を請求することになります。しかし、相手が任意保険に入っていなかったり、賠償できるだけのお金を持っていなかったりすると、被害者は必要な補償を受けられなくなってしまいます。
そこで、すべての車やバイクに最低限の保険をかけておくことで、被害者が泣き寝入りしないようにする。それが自賠責保険の目的です。あくまでも被害者を救うための制度であることから、自賠責保険が使えるのは人がけがをしたり、亡くなったりした「人身事故」のときだけです。車や物が壊れただけの「物損事故」では、補償の対象にはなりません。
自賠責保険の補償内容
自賠責保険では、事故の被害者に対して一定の金額まで補償される仕組みになっています。
ただし、補償には上限があり、すべての損害をカバーできるわけではありません。
① 傷害の補償内容と限度額
交通事故でけがをした場合、自賠責保険から支払われる金額には上限があります。けがに対する補償は、1人あたり最大で120万円までと決められています。
ただし、この120万円は、病院の治療費だけではありません。通院時の交通費や、事故のせいで仕事を休んだ場合の収入の減少、看護の費用、義手や義足などの補助器具代まで、さまざまな項目が含まれています。
さらに、けがをしたことで入院や通院が必要になった人が感じる精神的な苦痛に対しても、入通院慰謝料という補償があります。この入通院慰謝料も120万円に含まれます。
次の表は、120万円の補償に含まれる主な費用の一覧です。
| 費用項目 | 内容の説明 |
|---|---|
| 入通院慰謝料 | けがによって通院や入院を強いられたことによる心の負担に対する補償 |
| 治療費 | 診察代、入院料、薬代、検査・手術費など医療にかかるお金 |
| 通院交通費 | 病院へ通う際の電車・バス・タクシー代など |
| 休業損害 | けがで働けず、収入が減った分の補償 |
| 看護費 | 入院や通院に付き添ってくれた人への日当など |
| 補助器具の費用 | 義足、義眼、松葉づえ、補聴器などの購入費用 |
| 診断書などの手数料 | 診断書や診療明細などを発行してもらう際の費用 |
| 各種証明書の費用 | 事故証明書、住民票、印鑑証明などの取得にかかる費用 |
| 入院中の雑費 | テレビカード、タオル、日用品などの購入費用 |
より詳しい支払い基準について知りたい場合は、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払い基準」(金融庁・国土交通省)をご確認ください。
② 後遺障害の補償内容と限度額
事故によるけがが治らず、体に後遺障害が残ってしまった場合は、症状の重さに応じて補償額が決まります。75万円から最大4000万円まで補償されます。
この補償には、精神的な苦しみに対する後遺障害慰謝料や、働けなくなったことで失う将来の収入(逸失利益)が含まれます。ただし、後遺障害の補償を受けるには、専門の機関から後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
より詳しい支払い基準について知りたい場合は、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払い基準(金融庁・国土交通省)をご確認ください。
③ 死亡の補償内容と限度額
もし交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、自賠責保険からは最大で3000万円まで支払われます。
この中には、亡くなった方の精神的苦しみや、ご遺族の悲しみに対する死亡慰謝料、事故によって失われた将来の収入(逸失利益)、そして葬儀にかかった費用などが含まれます。
より詳しい支払い基準について知りたい場合は、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払い基準(金融庁・国土交通省)をご確認ください。
自賠責保険の請求の流れ
自賠責保険から保険金を受け取るには、所定の手続きが必要です。ここでは、請求から支払いまでのおおまかな流れを紹介します。
まず、保険金を請求する人(加害者または被害者)が、自賠責保険を扱っている損害保険会社や共済組合に書類を提出します。書類がそろったら、保険会社はその内容を確認し、専門機関である損害保険料率算出機構にある調査事務所へ送ります。
この調査事務所では、公正な立場から事故の状況やけがの内容、保険金の対象になるかどうかなどを調べます。調査結果は保険会社に報告され、その内容をもとに支払額が決定されます。特に判断が難しいケースは、専門の審査会で検討されることもあります。
こうしたステップを経て、保険金が請求者に支払われます。時間はかかることもありますが、手順に沿って進めれば受け取ることができます。
詳しい流れや図解は、自賠責保険・共済ポータルサイト(国土交通省)に掲載されていますので、そちらも参考にしてください。
自賠責保険の請求に必要な書類
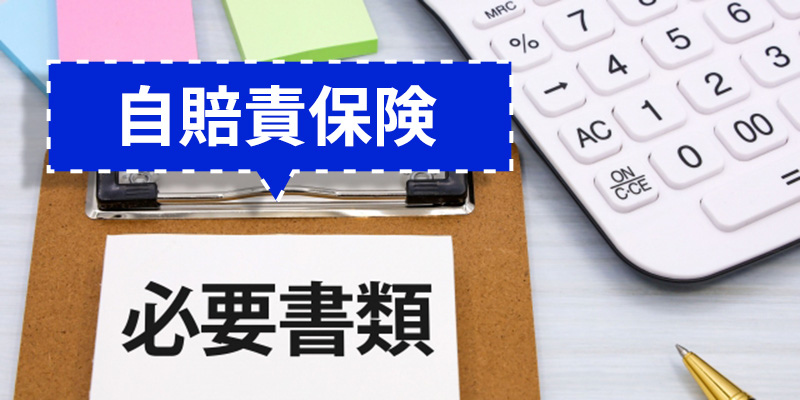
自賠責保険を請求するには、事故の内容やけがの状況などを証明するための書類が必要です。事故の種類(けが・後遺障害・死亡)や請求方法(加害者請求・被害者請求)によって必要な書類は多少異なりますが、主に次のような書類が求められます。
- 保険金支払請求書(自賠責保険会社や共済組合で用紙を取得)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得)
- 医師の診断書、または死体検案書(病院から取得)
- 診療報酬明細書(病院から取得)
- 通院のために使った交通費の明細書
- 付添看護の自認書や看護費の領収書
- 休業損害を証明する資料(勤務先の証明書、確定申告書、納税証明書など)
- 印鑑証明書や戸籍謄本などの本人確認書類
被害者自身が直接請求する「被害者請求」の場合、これらの書類を自分でそろえて手続きをします。また、治療中などで早めにお金が必要な場合は、「仮渡金」という制度もあります。これは簡単な手続きで先に一部の保険金を受け取ることができる仕組みです。
なお、自賠責保険の請求には時効があります。被害者は、事故や症状固定から3年以内に手続きをしないと請求できなくなることがありますので、できるだけ早めに準備を始めることが大切です。
書類の詳細やケース別の注意点については、支払いまでの流れと請求方法(国土交通省)で最新情報を確認できます。
よくあるご質問
ここでは、自賠責保険に関するよくある質問をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
自賠責保険と任意保険の違いは何ですか?
自賠責保険と任意保険は、どちらも交通事故が起きたときに使える保険ですが、内容には大きな違いがあります。
まず、自賠責保険はすべての車やバイクに加入が義務づけられている「強制保険」です。
事故で人がけがをしたり亡くなったときに、その被害者を守るための最低限の補償をします。物に対する補償(車や建物など)は含まれていません。
一方で、任意保険は入るかどうか自由に選べる保険です。こちらは自賠責で足りない部分をカバーします。たとえば、けがの治療費が120万円を超えた場合、その超えた分を任意保険で補うことができます。また、物が壊れたときや自分の車の修理費なども、任意保険の契約内容によっては補償されます。
ただし注意が必要なのは、被害者側にも過失があるときです。自賠責保険は、被害者に大きな過失がなければ減額されません。しかし任意保険は、過失の割合に応じて補償額が減る仕組みです。
自賠責保険(強制加入)の特徴のまとめ
- 加入の義務:あり
- 補償の対象:人のけがや死亡
- 補償の上限:傷害120万円、後遺障害4000万円、死亡3000万円
- 被害者の過失:重い過失がある場合のみ減額
任意保険(自由加入)の特徴のまとめ
- 加入の義務:なし
- 補償の対象:人のけがや死亡に加えて物の損害
- 補償の上限:契約内容により異なる。無制限が多い。
- 被害者の過失:過失割合に応じて減額
自賠責限度額を超える損害は、どうすればよいですか?
自賠責保険の限度額を超える損害については、原則として加害者の任意保険から補償を受けることになります。
たとえば、けがの治療費などが120万円を超えた場合、自賠責保険で補償されるのはその範囲までです。それを超える部分については、加害者が任意保険に加入していれば、その保険から支払われるのが一般的な対応となります。
一方で、加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者が加害者本人に対して、超過分の損害賠償を直接請求する必要があります。加害者の支払い能力によっては、回収が難航することもあります。
また、加害者側からの補償が不十分な場合には、被害者自身が加入している保険(人身傷害保険)を活用する方法もあります。契約内容によっては、自分の保険で不足分をカバーできるケースもあるため、加入している保険の補償内容を早めに確認しておくことが大切です。
被害者に過失があると、補償額が減ってしまいますか?
被害者に重大な過失がある場合、自賠責保険の補償額が減額されることがあります。
ただし、自賠責保険は被害者救済を目的とした制度であるため、たとえ被害者に一定の過失があったとしても、原則として満額の補償が支払われます。
減額が適用されるのは、被害者の過失割合が7割を超えるようなケースです。そして、減額されるといっても、過失の割合そのままに支払いが減るわけではなく、決まった範囲内での調整がされる仕組みになっています。
たとえば、被害者に8割の過失がある場合でも、補償が8割減るのではなく、実際の減額幅は2〜3割程度にとどまります。
なお、被害者に100%の過失(完全に自己責任)があると認定された場合には、自賠責保険による補償は一切受けられません。
| 被害者の過失 | 傷害の補償 | 後遺障害・死亡の補償 |
|---|---|---|
| 7割〜8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
| 8割〜9割未満 | 2割減額 | 3割減額 |
| 9割〜10割未満 | 2割減額 | 5割減額 |
自賠責保険では、被害者に一部過失がある場合でも、補償が過失割合に応じて減るわけではありません。事故状況に不安がある場合は、早めに保険会社や弁護士に相談しておくと安心です。
加害者が自賠責に入っているか不明です。どうすればよいですか?
まずは、交通事故証明書を取得しましょう。これがあれば、加害者が入っている自賠責保険の会社名や保険の証明番号がわかります。
交通事故証明書は、警察に事故を届け出ていれば自動車安全運転センターで発行してもらえます。ただし、事故のときに警察に通報していなかった場合は、この証明書に保険情報が載っていないこともあります。事故後は必ず警察を呼ぶことが大切です。
加害者が自賠責に入っていません。どうすればよいですか?
加害者が自賠責保険に入っていない場合でも、被害者は「政府保障事業」を利用することができます。
自賠責保険は加入が義務づけられていますが、中には期限切れなどで無保険状態の加害者もいます。そのようなとき、被害者を救済するための制度が「政府保障事業」です。国が最低限の補償をしてくれます。
手続きの流れは、自賠責保険への請求と似ています。まずは自賠責を扱っている保険会社に連絡して、政府保障事業の請求書類を送ってもらいましょう。どの保険会社でも対応してもらえます。
届いた書類と一緒に、診断書や医療費の明細などの必要な書類を提出します。審査を経て、補償が決まります。
補償される金額や上限は、基本的に自賠責保険と同じです。自由診療で高額な治療を受けた場合などは、全額出ないこともあるので注意が必要です。
なお、まれに「任意保険には入っていたのに、自賠責には入っていなかった」というケースもあります。この場合は、まず政府保障事業から支払いを受け、そのあとで加害者の任意保険が足りない分を補うという流れになります。
つまり、自賠責がなくてもすぐにあきらめる必要はありません。国の制度を活用して、正当な補償を受けることが可能です。困ったときは、保険会社や専門家に相談してみましょう。
車両など物の損害は、自賠責保険の補償の対象ですか?
車両など、「物」の損害は、自賠責保険では補償されません。
自賠責保険は、交通事故で人がけがをしたり、亡くなったりしたときだけ使える保険です。つまり、「人身事故」だけが対象で、「物損事故」には使えません。
たとえば、事故で「車が壊れた」「壁にぶつかった」「自転車が壊れた」こういった物への損害は、自賠責保険からは一切支払われない決まりです。
物の損害を補償してもらいたい場合は、加害者が任意保険に入っていれば、任意保険会社に請求できます。もし加害者が任意保険に入っていなければ、加害者本人に直接請求することになります。
まとめ:自賠責保険の補償内容や請求の流れ
交通事故が起きたとき、被害者の命や生活を守るための最低限の備えとして機能するのが自賠責保険です。すべての車やバイクに加入が義務づけられたこの保険は、人身事故を対象とし、けが・後遺障害・死亡といった被害に対して一定の金額まで補償が行われます。
ただし、自賠責保険の補償には限度があるため、それを超える損害がある場合は、加害者の任意保険を利用したり、加害者が無保険であれば政府保障事業に請求したりといった方法で、被害者救済を図ることができます。特に、後遺障害が残ったり高額な損害が発生したりするケースでは、専門知識を持った弁護士のサポートが重要です。
よつば総合法律事務所は、交通事故に関するご相談を数多く受けてきました。自賠責保険の請求手続きはもちろん、後遺障害等級の取得や、慰謝料・損害賠償の増額交渉にも対応しています。被害者の方が納得のいく補償を受け取れるよう、法的視点から全力でサポートいたします。
事故後、どう動いていいかわからないとき、ひとりで悩まずに、まずは私たちにご相談ください。法律の知識がない方にもわかりやすく丁寧に説明し、ご不安を少しでも軽くできるよう努めます。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博