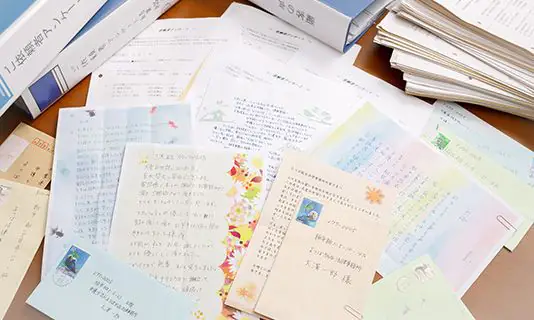通院1日の慰謝料
最終更新日:2025年09月04日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博
- Q交通事故で通院1日だと慰謝料はいくらもらえますか?
-
4,300円〜6,300円程度です。
通院1日だけの場合、慰謝料の目安は約4,300円〜6,300円程度です。
慰謝料の具体的な金額は、どの基準で算定するかによってかなり異なります。自賠責基準で計算すると4,300円、任意保険会社が設定する基準では4,300円〜5,000円程度、裁判所(弁護士)基準ではおおよそ6,300円程度が相場となっています。
なお、1日だけで通院が終了することは少ないです。通院回数や期間が増えると慰謝料も増えます。医師の診察を踏まえて、適切な期間・日数の通院をしましょう。

目次
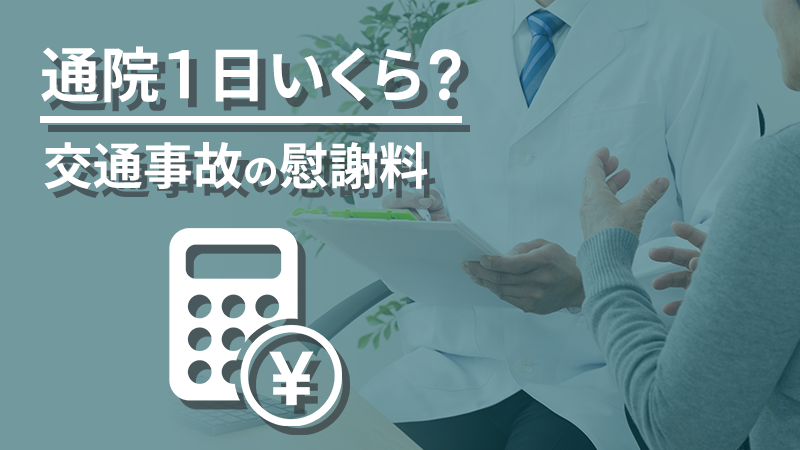
慰謝料とは
交通事故でけがをした被害者は、加害者に対してさまざまな損害賠償を請求する権利があります。具体的な損害賠償の項目としては、治療費や通院交通費、休業損害、後遺障害による逸失利益などが挙げられますが、その中でも特に精神的な苦痛に対して支払われるものを「慰謝料」と呼びます。
慰謝料には、主に次の4つの種類があります。
- 交通事故によって病院へ通院や入院をした際に感じる肉体的・精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。通院日数や入院期間などに基づいて金額が計算されます。
- 交通事故のけがの治療が終わっても、完全に回復せず後遺症が残ってしまった場合に、その後遺症によって受ける精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。後遺症の程度に応じて等級が認定され、その等級によって慰謝料の金額が大きく異なります。
- 交通事故により被害者が死亡した場合、その生命が失われたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。被害者ご本人が扶養していた家族の有無や人数などによって金額が決まってくることが多いです。被害者本人の慰謝料に加え、遺族にも一定額が支払われることがあります。
-
近親者慰謝料被害者が重大なけがを負ったり死亡したりした場合、被害者本人だけでなく家族など近親者にも精神的苦痛が及びます。その精神的苦痛に対して支払われる慰謝料で、特に被害者が死亡した場合や重篤な後遺症を負った場合に認められることが多いです。
この記事では、「入通院慰謝料」を中心に詳しく解説します。
入通院慰謝料の3つの基準
交通事故による入通院慰謝料の金額は、どの基準を使って算定するかで大きな差が生じます。実際には、保険会社が提示してくる金額と、弁護士に依頼した場合に得られる金額が異なることも少なくありません。
慰謝料の算定には、主に次の3つの基準が使われています。
-
自賠責基準自賠責基準とは、すべての自動車に法律で加入が義務付けられている自賠責保険(強制保険)によって定められた基準です。被害者救済を目的とした最低限の補償を前提としているため、慰謝料の金額は3つの基準の中で最も低額になる傾向があります。
-
任意保険基準各保険会社が独自に設定している内部基準です。会社ごとに異なり、非公開のため詳細は明らかにされていません。
-
裁判所(弁護士)基準裁判所(弁護士)基準は、過去のさまざまな裁判例を参考にして裁判所や弁護士が実務上よく利用している基準です。慰謝料を算定する際に使用される3つの基準のなかでは、最も高額で被害者側にとって有利な基準とされています。
それぞれの基準で通院1日の慰謝料がいくらになるのか、詳しく見ていきましょう。
自賠責基準で通院1日の場合
自賠責基準では、入通院1日あたりの慰謝料は4,300円と定められています。
したがって、慰謝料は、次の計算式により算出されます。
4,300円×対象日数=自賠責基準の慰謝料
対象日数は、「実際の治療期間」と「実通院日数×2」のうち短い方が採用されます。つまり、通院1日のみの場合、実通院日数で計算すると「1日×2=2日」となりますが、実際の治療期間が1日であれば短い方の1日が適用されます。
したがって、この場合の慰謝料は4,300円となります。(通院が1回限りの場合の金額の目安です。)
裁判所の基準で通院1日の場合
裁判所や弁護士が使う「裁判所基準(弁護士基準)」では、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している損害賠償額算定基準(通称:赤い本)をもとに慰謝料を計算します。
損害賠償額算定基準には、症状の重さに応じて2種類の計算表が掲載されています。
交通事故で通院が1日だけだった場合、多くのケースではむち打ちや打撲などの軽傷と判断されるため、別表Ⅱを使って慰謝料を算出するのが一般的です。
別表Ⅱによると、通院1か月(30日間)に対する慰謝料は19万円と定められています。
そのため、通院1日だけだった場合には、次のように日割りで計算します。
19万円÷30日=約6,333円
つまり、裁判所基準で通院1日の慰謝料は約6,300円程度と見込まれることになります。
(通院が1回限りの場合の金額の目安です。)
加害者の任意保険会社の基準で通院1日の場合
任意保険会社が提示する慰謝料の金額は、各社が独自に定めた基準に基づいています。ただし、この基準は公開されていないため、どのような根拠で金額が決まっているかは、被害者側にはわかりません。
実務上、任意保険会社の基準は自賠責基準よりやや高めに設定されることが一般的ですが、裁判所基準と比べると低くなる傾向があります。
通院1日だけの場合、任意保険会社から提示される慰謝料は、おおむね4,300円から5,000円程度と言えるでしょう。
(通院が1回限りの場合の金額の目安です。)
今後通院する必要があるか慎重に検討
通院が1日で終わってしまうと、慰謝料はどうしても少額にとどまります。通院1日の慰謝料額が想像より少なかった場合、「もう少し通院して慰謝料を増やしたい」と考える気持ちも分かります。
しかし、慰謝料は単純に通院の回数や期間だけで決まるものではありません。慰謝料を請求できるかどうかで一番重要なのは、「医師が通院治療の必要性を認めているかどうか」という医学的な判断です。
医師が「もう通院する必要はありません」と判断したにもかかわらず、自分の判断だけで通院を続けてしまった場合には、次のようなリスクがあります。
- 慰謝料の支払い対象として認められず、通院分が無駄になってしまう可能性がある
- 治療費が保険会社から支払われず、全額自己負担となってしまうおそれがある
- 不必要な通院と判断され、後にトラブルになった場合に不利になったり、被害者としての信頼性が損なわれたりするリスクがある
一方で、医師から「まだ症状が落ち着いていないので、しばらくは通院を続けましょう」と言われているのであれば、無理に通院を中止する必要はありません。その場合は、適切な頻度で医師の指示に従って通院を継続することが重要です。
治療をきちんと継続すれば、症状が悪化して後遺症が残るのを防ぐことにもつながりますし、慰謝料を含めて正当な補償を受けるための根拠にもなります。
さらに、治療を継続するかどうかの判断について保険会社から「そろそろ治療は終了ですね」と言われたとしても、最終的な判断の権限は医師にあります。もし保険会社と意見が異なる場合や、判断に迷ってしまうようなことがあれば、まずは医師に相談しましょう。
また、不安な点が残る場合は交通事故に詳しい弁護士へ相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
通院期間ごとの慰謝料の目安
ここでは、月に15日程度(週3~4回)の通院があった場合を前提に、裁判所基準(弁護士基準)による慰謝料の目安をご紹介します。なお、むち打ちや捻挫など、他覚所見がない軽傷を想定し、「別表Ⅱ」に基づいて金額を記載しています。
通院1か月の場合
通院期間が1か月程度であれば、交通事故後の初期的な治療期間としては標準的なケースといえます。週2~3回の頻度で継続的に通院していた場合、裁判所の基準による慰謝料の目安は19万円です。
この金額は、医師の診断に基づき、必要な治療を計画的に受けていたことが前提となります。通院の間隔があまりに空いていたり、医師の指示と合致しない通院があった場合には、慰謝料が減額されることもあるため注意が必要です。
通院3か月の場合
3か月の通院となると、治療の長期化がある程度見られるケースです。裁判所の基準による慰謝料の目安は53万円です。
3か月経過すると、保険会社から「そろそろ治療は終了ではないか」と治療費の打ち切りを示唆されることがあります。しかし、実際に治療が必要かどうかは医師の判断が尊重されます。医師の診断書や治療計画に基づいて正当に通院を継続している場合には、裁判所基準での慰謝料が認められる可能性があります。
打ち切りを求められた際は、通院の必要性を医学的に説明できる資料を整えておくとともに、不安な場合には弁護士に相談することが望ましいです。
通院6か月の場合
通院期間が6か月に及ぶ場合、軽傷(別表Ⅱ)としては比較的長期間とされ、裁判所の基準による慰謝料の目安は89万円です。
このようなケースでは、治療の継続が医学的に本当に必要だったかが問われることがあります。たとえ症状が残存していても、医師からの具体的な治療指示や、症状の具体的な変化、痛みや痺れを裏付ける客観的な所見がなければ、通院の必要性が疑問視され、慰謝料が減額されたり、そもそも治療費の対応を拒否されることもあります。
特に、むち打ちなど自覚症状中心のけがでは、保険会社が長期通院に対して慎重に対応してくることがあります。正当な補償を得るためには、治療が必要・相当であるという医師の意見とあわせて、法的観点からのアドバイスを受けることが重要になります。
慰謝料で悩んだら弁護士に相談
ここまでご紹介してきたように、慰謝料の金額は通院日数や通院期間、そしてどの算定基準を用いるかによって大きく変わります。同じ1日の通院でも、自賠責基準と裁判所基準では金額が数倍違うこともあります。にもかかわらず、実際には保険会社から低い金額を提示され、そのまま示談に応じてしまう被害者の方も少なくありません。
通院日数が少ないからといって、必ずしも慰謝料の請求ができないというわけではありません。正しい医学的根拠や通院実績があれば、裁判所基準に近い水準での補償が認められる可能性は十分にあります。とはいえ、慰謝料の適正額や通院頻度・期間の評価がどのように判断されるかは、専門的な知識がなければ見極めが難しいのが現実です。
私たちよつば総合法律事務所は、こうしたお悩みに応えるために、交通事故分野に特化したチームを組み、事故直後からのご相談・治療中のサポート・示談交渉・裁判対応まで、一貫してお手伝いしています。
被害者の方にとって本当に納得のいく解決となるよう、法律的な知識だけでなく、医療や保険制度の知見も活かして全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博